 哲学談戯
哲学談戯 意識という科学では説明できないもの – マルクス・ガブリエル『「私」は脳ではない』
マルクス・ガブリエル『「私」は脳ではない - 21世紀の精神のための哲学』(2019)Markus Gabriel, Ich ist nicht Gehirn: Philosophie des Geistes für das 21. Jah...
 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯 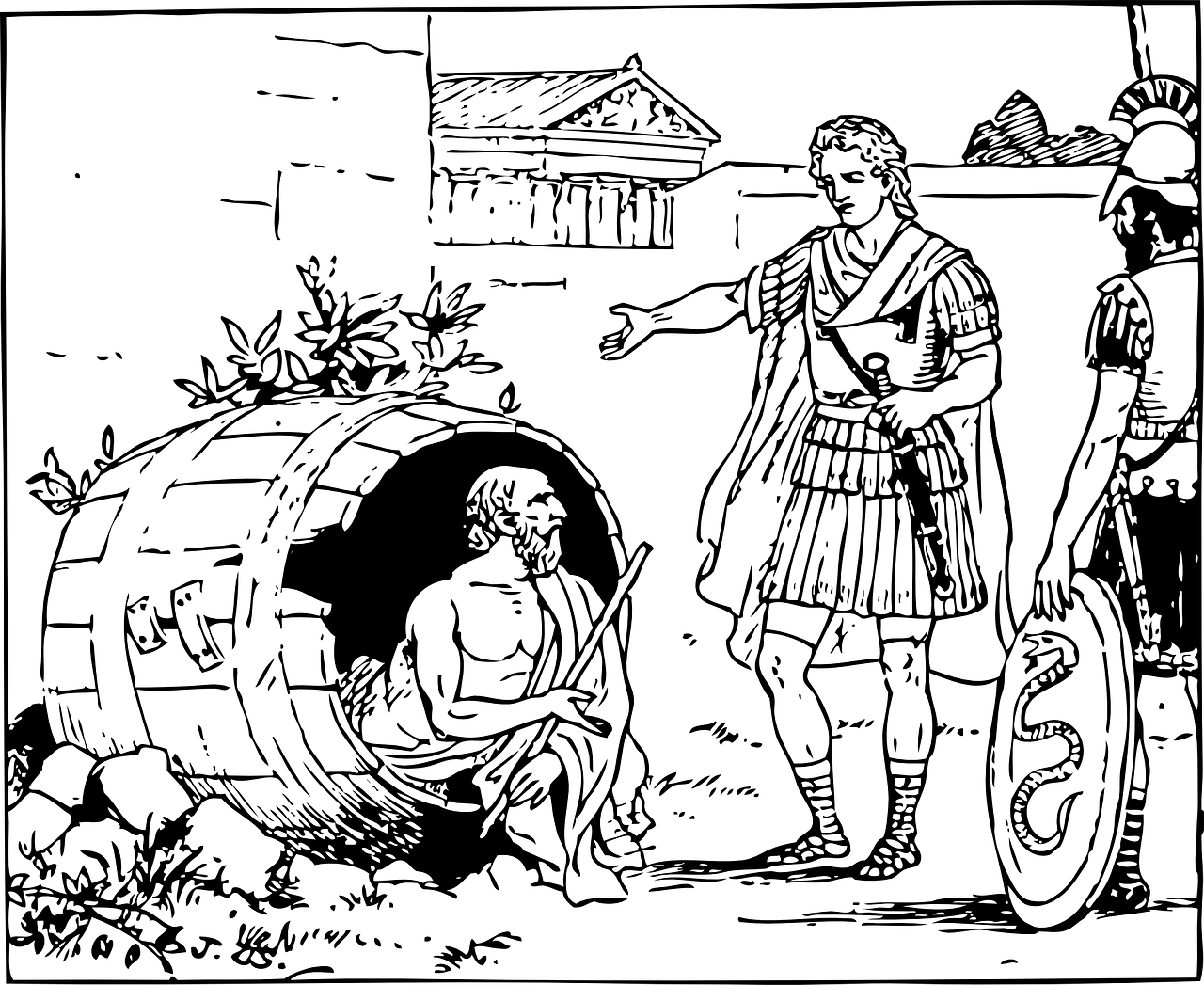 哲学談戯
哲学談戯 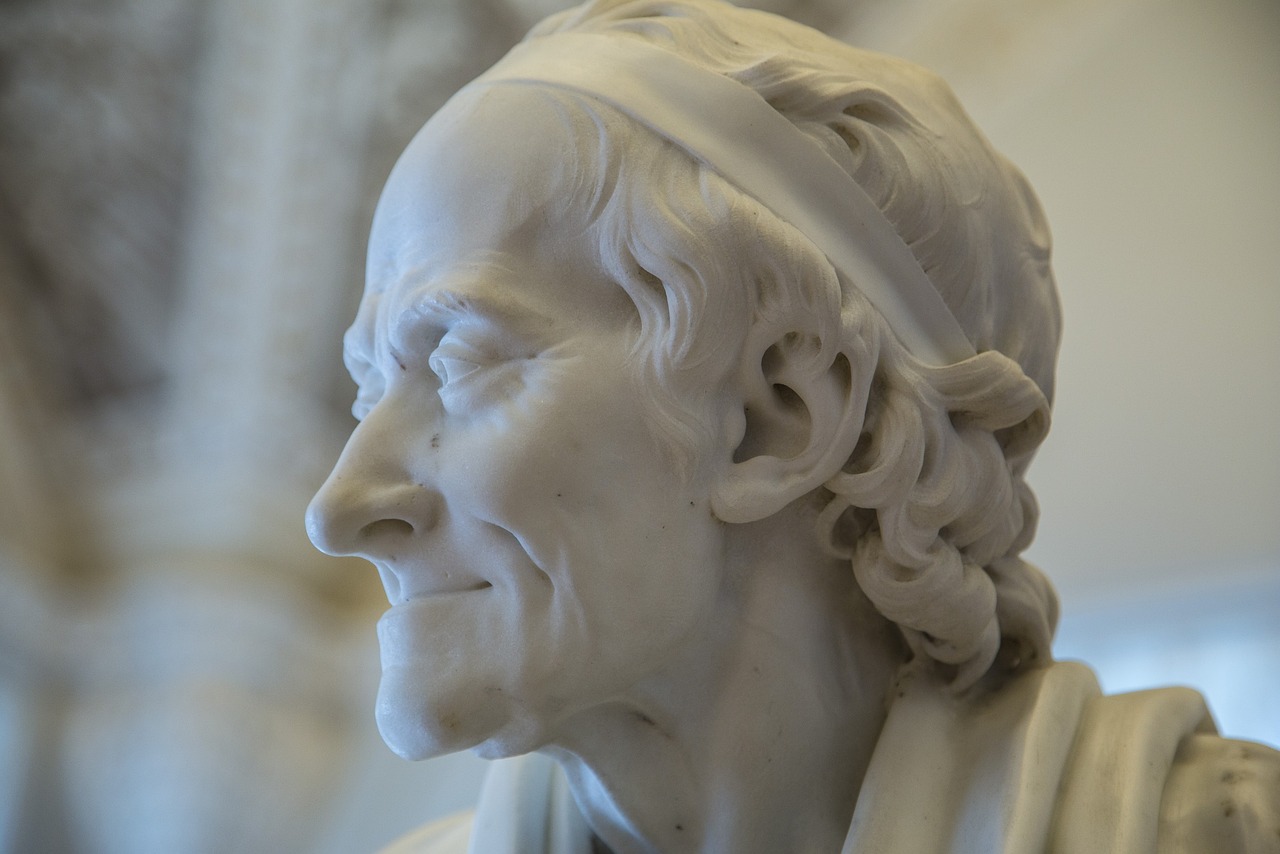 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯 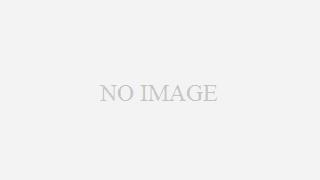 哲学談戯
哲学談戯 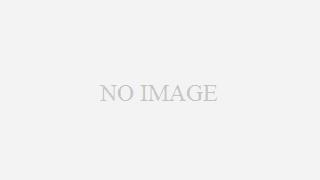 哲学談戯
哲学談戯 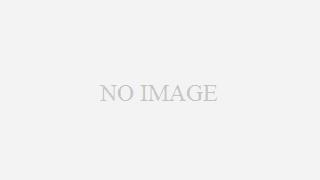 哲学談戯
哲学談戯 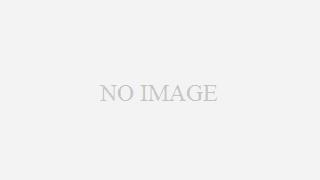 哲学談戯
哲学談戯