 科学半解
科学半解 クオリアと意識のハード・プロブレム ― 現代脳科学が直面する理論的限界
クオリアとは何か クオリア(qualia)とは、「赤が赤く見える」「痛みが痛みとして感じられる」といった、主観的な経験に伴う質的側面のことである。これは、単なる情報処理ではなく、「何かを感じるとはどういうことか」という第一人称的な体験を指す...
 科学半解
科学半解  科学半解
科学半解 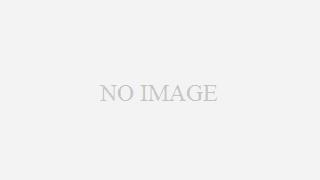 科学半解
科学半解 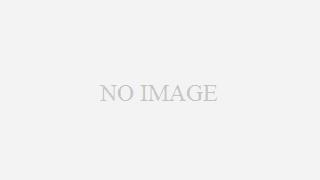 科学半解
科学半解 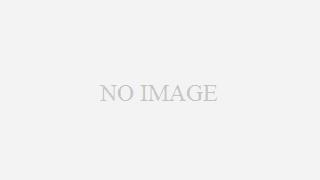 科学半解
科学半解 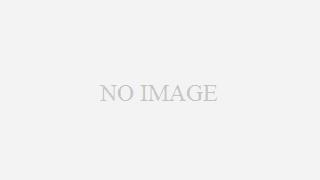 科学半解
科学半解 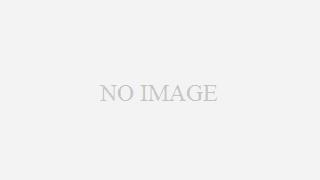 科学半解
科学半解  科学半解
科学半解  科学半解
科学半解 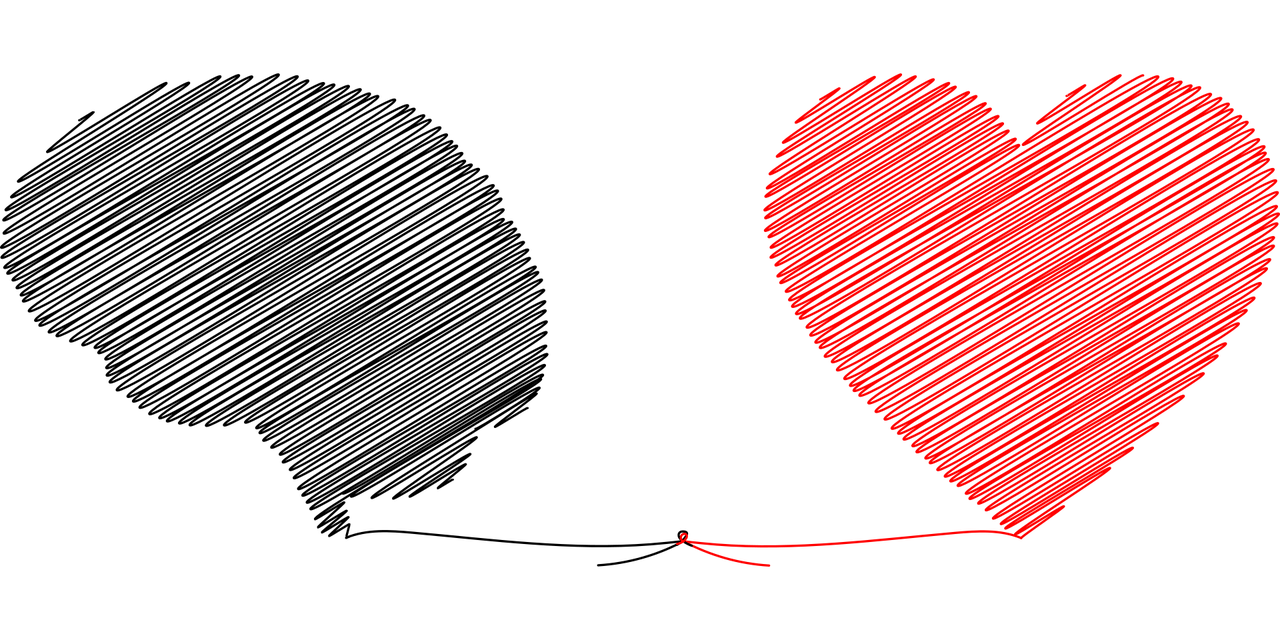 科学半解
科学半解