偽書と疑われた作品
プラトンの作品として現代まで伝わっているものは、帝政ローマ期にトラシュロスがまとめた36編が基本となっている。『アルキビアデス』はその中に含まれる作品だが、古代、中世、近代を通じてプラトンの真作として、その真偽が疑われることはなかった。
だが、『クレイトポン』と同じく、19世紀ドイツの文献学者シュライアマハーが、プラトンの偽作との説を唱えて以来、現在に至るまで、真偽問題が絶えない作品となっている。
プラトンの著作として伝わっているもので『アルキビアデス』と名の付く作品は二つあり、「人間の本性について」という副題を持つものと「祈願について」という副題のものがあり、前者を『アルキビアデスⅠ』、後者を『アルキビアデスⅡ』と便宜的に呼び分けている。
『アルキビアデスⅡ』は、分量も少なく、作中の対話において、アルキビアデスがただソクラテスに同意するだけの役割しか果たしておらず、作品として稚拙であること、文体がプラトンのものと異なる点があることから、偽作とする見方が主流だ。
問題は、『アルキビアデスⅠ』の方だ。(ここでは単純に『アルキビアデス』と呼ぶ。)この作品は、現在では真作とする説の方が主流となっている。特に計量文献学による語彙や文体の統計調査が進み、プラトンの真作の可能性が極めて高いという調査結果が複数出てきている。文体的にプラトン初期の作品で、紀元前390年頃に書かれたのではないかと見られている。
ただ、この作品。。。
初読の印象が、「プラトンっぽく」ないのだ。(まぁ私個人の印象だが。)
議題が次々と移り変わり、議論が錯綜し、さまざまな問いが宙に浮いたまま終わりを迎える。プラトンの偽作として疑われたのも無理はないという印象だ。
二つの主題
副題は「人間の本性について」。
おそらく本書の主題は二つある。一つは哲学的な主題であり、「知っている」ということは何を意味しているのか、という自らの知識へ問いである。ソクラテスとの対話を通じて、アルキビアデスは、自らの持つ知識が、実は自分では何も理解していないものであること、そして、それに気付き、自己の知識の不確かさを理解していく過程全体が描かれる。「無知の知」の自覚を促すソクラテスの有名な議論だ。
そして、もう一つ、この作品では「魂」という宗教的な問題を主題としている。
『アルキビアデス』は、後の新プラトン主義で、最も重視された作品だという。自己の知識の不確かさを自覚させ、自己認識を改めさせることで、魂への配慮へと導こうとするソクラテスの姿は哲学者というより宗教者的だ。
この作品における「無知の知」は、正しい知識への探究を促すものというよりも、純粋な自己の存在、すなわち「魂」への配慮を導くものとして描かれている。
この点が、後の新プラトン主義に評価され、一方、現代の研究者たちにプラトンの作品としての疑念を抱かせた一つの原因だろう。
この作品は、哲学的には、自己の知識のあり方への自覚を問い、宗教的には、魂という自己の存在への自覚を促すことを主題としている。
自己認識の確立がこの作品の大きな意味での主題となっているという評価は、古代においても現代においても変わってはいない。
自己を知るということは、哲学的にも宗教的にもこの作品で重要な意味を持つ課題となっている。
「知っている」とはどういうことか?
この作品は、先ずソクラテスが政治的な野心を抱いているアルキビアデスに対し、知識の確かさを問うことから始まる。
造船、医療、キタラの演奏、レスリング、これらについて「より良い」と言われているものは、すべて技術に即したものであり、それぞれ内容は異なる。では、政治についてはどうか。平和に関して「より良い」と言われていることと、戦争に勝つために「より良い」と言われていることは、同じではない。
では、「より良い」とは、いったい何を指しているのか。ソクラテスはそのように問う。
この問いに対して、答えられなかったアルキビアデスは、自らが「より良い」ということの意味を全く知らなかったことに気づかされる。
ここでのソクラテスの議論は、自らの持つ知識に関して、どれほど自分自身が自覚を持っているかを問うものだ。
ソクラテスは、正しいということについての知識は教えられて得たものなのか、自ら発見したものなのかをまず問う。そして、自らが知っているということを知ったのはいつなのか、それはどのようにして知ったのかをさらに問い詰めていく。
ソクラテスは知識に関して次のように説く。人に教えようとする者は、自分自身がまずそれを知っていなければならない。そして、それを知っている者たちはそれについて同じ考え(意見)を持っていなければならない。だが、正しいと思う事柄に関して、人々の間で不一致があるからこそ争いが起き、戦争が起こるのではないか、と。
人々の間に意見の不一致があるということは、「正しいこと」を誰も知らないということになる。では、人から教えられることもできず、自ら発見することもできない知識をどのようにして知ることができるのかと、ソクラテスはアルキビアデスに問う。アルキビアデスは自らの無知を認めざるを得なくなる。
人より優れて知っていると自認していたアルキビアデスに、ソクラテスは、民会で演説する前に、そして、さらには政治家として身を立てる前に、「自分自身を知ること」の重要さを解く。
自己の富や地位は、人間の本質を表さない。「自分自身を知れ」というのは、「自分に付属するもの」すなわち、失ったり支配されたりすることのあるものではなく、何物にも支配されない自らの「魂」を配慮することであり、それは「節度(sophrosyne)」を保つことによってなされるものだという。
ソクラテスは言う。自ら知らないものを知っていると思い込む者こそが、過ちを犯すのだと。そして、「無知の知」を知ることを通じて、節度を持ち、魂への配慮を促していく。
ここでのソクラテスの対話は、魂への配慮を促すことに重点が置かれている。「無知の知」は自分自身を知ることの契機となるものであり、節度を通じて魂への配慮へと向かわせるものだ。そして、後のデマゴーグとなっていくアルキビアデスに対して、徳を身に付けることを説いて、この対話は幕を閉じる。
ソクラテスの粗雑な論駁
自己認識の確立を主題とした本書だが、その自己認識へと導こうとするソクラテスの議論は、非常に入り組んでいて、読み解くのは難しい。
一見すると、読者に議論が錯綜している印象を与え、読みにくさを感じさせる。
議題は多岐にわたるが、アルキビアデスの問いに対し、ソクラテスが論駁して、答えが宙に浮いたまま、さらに次の問いへと移っていく。そして、何よりもソクラテスの論駁が、強引な論証に基づくものであるという印象を抱かせる点が多い。
たとえば、ここでのソクラテスの議論には、定義や論証を与え、相手にそれを認めさせた上で、今度は三段論法的にその前提の矛盾を指摘するという場面がいくつか見られる。
ソクラテスは正義と利益は同じものかと問う。ソクラテスは、まず正義にかなったことは「利益」になるということを論証したのちに、今度は、それが成り立たない場合があることをアルキビアデスに認めさせている。
同じような問いは、「友愛」をめぐっても繰り返される。友愛は同じ考えを持つ者の間で成り立つものという定義を与えた上で、その定義に従うと人々の間に友愛が成り立たなくなることを示す。
ここでの議論は、相手の矛盾を引き出すためだけの強引な詭弁のような類のものだ。ソクラテスの議論は、相手の「無知の知」を自覚させることだけに主眼があり、知識の内実を問おうとはしていない。正しい知識の在り方を探求しようとしたプラトンとは対照的だ。
このような点も偽書として疑われた要因の一つなのだろう。
ソクラテスの本来の姿
「正しい知識」の獲得こそを探究したプラトンの思想から考えれば、無知の知が魂への配慮へと収斂していく議論には違和感がある。プラトンにとって「無知の知」は、むしろ、絶対的に正しい知識を獲得するための探究を促すものだった。だが、『アルキビアデス』をプラトンの思想を表した作品ではなく、ソクラテスの議論を忠実に描いた作品だと考えた場合、見方は変わってくる。
プラトンは、初期後半から中期にかけて自らの思想を確立し、中期以降の作品では、ソクラテスの口を借りて、自らの思想を表現していった。プラトンの思想や思考方法から見ると、『アルキビアデス』での議論の進め方には異質な点が多く見られる。「利益」や「友愛」に関しての議論はその典型だろう。これは、プラトンが独自の思想をソクラテスに語らせようとした作品ではなく、忠実にソクラテスの思想を描いた作品なのではないだろうか。
もし、『アルキビアデス』がプラトンの真作であるとするならば、これはプラトン最初期の作品だろう。プラトンが独自の思想を築く前、つまり、師匠であるソクラテスの忠実な姿を後世に伝えようとしていた時期の作品だ。その意味で、自分はこの作品には、自己の存在を見つめ、魂の在り方を追求したソクラテスの純粋な議論の姿が描かれているように思える。

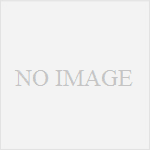
コメント