中村雄二郎『哲学の現在』(1977)
[adcode]
近代知性のAlternative
自我、身体、認識、宇宙像(cosmology)のそれぞれにおいて、近代的知性の限界を論じた書。
近代的知性の問題とは何だろうか。著者によればそれは、科学的知識とドグマの対立だという。
近代的知性は、確実性の意味が主観と客観において乖離していく事態を引き起こしている。そして、この両者の確実性は互いに交わることなく、対立することになった。
確実性は、もともと主観と客観の二つの方向軸を持っている。客観的知性は、物事の認識についての確実性であり、存在を対象的に、分析的に捉える。もう一方の主観的知性は、自己の主体性に確信を与えるような確実性であり、世界を意味のある存在として捉える。
近代において、この二つの確実性は過去に例がないほど甚だしい乖離を示している。主客という二つの軸に沿った知性の働きは、一方で、ドグマ的なもの、形而上的なものとなって現実から乖離していき、他方において、科学の内に哲学の発展的解消を見る科学万能主義の形態をとった。
このような主客分離が生じた背景には、近代哲学の心身二元論と近代科学の機械論的世界観が存在する。
近代の知がこのように二極化していく中で、哲学が知識と知恵の統一を通して再生するためには、「近代的知性」の否定を通して、知性の在り方への可能性を探る思考することがどうしても必要になる。それが理性の持つ批判理論の精神である。哲学の歴史とは、理性に対する絶えざる問いかけ、問い直しの歴史なのである。
中村氏は、近代知性とは異なる知性の在り方を自我、身体、認識、宇宙論のそれぞれの場面で論じている。その知性の在り方(alternative)を、以下、まとめてみたい。(ただし、本書の記述は論理的に飛躍していると感じる点もままある。多少の自己流解釈も含めて記述していく。)
[adcode]
自我をめぐって
心身二元論は西欧哲学の出発点であり、それと同時に近代的世界観の前提となった。精神と物体とを峻別することによって、一方では人間精神の主体性と自由を確保するとともに、他方では自然科学の数量化や数学的把握を可能にした。それは、極めて普遍性を持った考え方であり、同時に近代科学を受け入れる上で重要な価値観であった。そのため、心身二元論は、自由や平等という近代的価値観のみならず、科学技術を導入するためには、受け入れなければならない価値基準であった。現在、この価値観を完全に拒否しえる社会は、存在しえなくなった。この価値体系を生み出すことによって、西欧近代は人類全体にとって特別な意味を持つものになったと言える。
しかし、世界のすべてに人々に普遍的に当てはまる価値観というものは果して存在するのだろうか?どのような価値観も、その前提となる思想が存在する。近代における「自我」という観念も決して無条件に成立するものではなく、その背後には西欧の歴史に根付く思想が存在する。
中村氏は、近代の「自我」に対して、その自明性に疑いをかける。主体の確実性の根拠を自己意識の自明性に求める近代的自我は、その自己意識の自明性というものそのものが虚構であることを隠蔽しているという。
意識とは語る主体である。そして、語る主体は、言葉へと分散し拡散する。
意識は、決して全く「意味」を持たない価値不在の世界に生まれるわけではない。個人の意識的な意味付与に先立つものとして、既成の意味の層が存在している。それは、言葉という社会的共同の産物によって作られている。意識は、「語る主体」において共同主観の一部へと拡散し、そしてまた「私」の主体は、「考える主体」として共同主観の上に回復されるのである。
身体をめぐって
普段、われわれは自分の身体をそれほど意識することがない。それは身体が自己にとっての客体ではないからだ。われわれは、身体を持つのではなく、身体を主体とし、身体そのものを生きている。
活動するこのような主体としての身体は、生理的な身体の限界を超えて外部へと拡がりを持つ。ここに身体の二重性が生まれる。それは一方において、一人一人の内に身体を通して内面化される空間的な広がりである。それと同時に、他方において、その身体は他者によって外側から捉えられる対象としての身体でもある。
われわれは主体としての身体と対象としての身体との二重性の内に生きており、まさにそのことによって私の存在が他者と自己との関係性の内に成り立つのである。
[adcode]
認識をめぐって
現実の認識は、全体的で混乱した知覚から出発する。知覚においては最初に与えられるのは対象の総体であり、そのようなものとして外部世界を感覚の個別性を超えて全体的に捉えている。明晰な認識は、この混乱した総体的知覚を様々な感覚の要素に区別し分析することによって形作られる。
個別の感覚は、古来より自己の判断を誤らせ、信頼に足らないものとされてきた。個人の感覚は、その人固有の体験であり、言葉で伝えることはできても、感覚そのものを他人と共有することはできない。また、錯覚はいずれの場合も本人の「感覚」にとっては真実であり、その真偽を自己の感覚を根拠に論じることはできない。
さらに言えば、錯覚はしばしば知覚という総体的認識によって生じるものであり、感覚作用そのものによって起こされるのではない。そうではなく、知覚が習慣的になされる場合、そこに習慣がもたらす判断が入ってくる。それが錯覚として捉えられる。
知覚とは様々な感覚がばらばらに働くのでもなければ、ただ瞬間的に働くものでもない。感覚の個別性を超えた次元で働いている。具体的な知覚とは、過去の経験に基づく記憶や連想、そして習慣がもたらす判断をすでに含んでいる。
感覚の個別性を超えた次元として、知覚の他に、もう一つ、共通感覚と呼ばれるものがある。
共通感覚は、種類の違う感覚印象を対比させ、総合する。運動、静止、形、大きさ、数、同一性といった概念は、感覚の働きを離れては感知されないが、しかし個別の感覚によっては捉えられない。これらを知覚する場合、個々の感覚によって感知されたものを、もう一度、反省的に捉え直さなくてはならない。個々の感覚を超えて働くのが共通感覚である。
近代世界では見ることが重視され、大きな意味を持っている。しかし、よく見ることは視覚だけが働くことではない。それは、視覚を中心とした諸感覚の協働による知覚なのである。諸感覚が出合い統一して働く全体的な直感、つまり共同感覚が働いているのである。
知覚や共通感覚は、想像の働きに深く関わる。想像は与えられている限られた諸事実からは直接には知覚し認識することのできない物事を推測して知る上で役に立つ。想像力は、さらに現実的なもの、実在的なものを超えて、あるがままにある物事や現実を自由に解体し再構成することを通して、新しい可能な世界を切り開く、いわば可能的な知覚なのである。
[adcode]
世界像をめぐって
近代科学の中で最初に輝かしい成果を収めたのは、古典物理学である。ここで前提となっていたものは、確実な事実から出発し、論理を組み立てていけば、更なる全体像へとつながるという確信である。だが、物理学に続いて化学や生物学などの新しい分野の発展が進むと、判明している事実から必ずしも明晰な事実が得られるとは限らなくなった。
対象は、それを捉える見方によって異なる姿を現す。例えば、結晶質の単純な物質はその作用を明確に捉えにくく、逆にガラスなどのような非結晶質の複雑な物質はしばしばその作用を明確化しやすい。生化学の対象となる生命体は、物質の観点から見ると極めて複雑であるが、その器官の示すさまざまな働きは恒常性を保っている。
物質の面から実体的に見ると単純であった対象が作用の面からみると複雑になり、また逆に、物質の面から見ると複雑であった対象が作用の面からみると単純になるという現象が次々に発見されていった。このようなことが次第に自覚されるようになって、科学的知による対象化は複雑なものから単純なものへの分析という方向を必ずしもとるべきではないことが一層意識されるようになる。
その結果、確実性のあるものから論理を積み重ねていくのではなく、全体像をまず統一的に把握する知性が再度見直されるようになった。その最も原初的な形は、神話の知性である。
神話の知の基礎にあるのは、われわれを取り巻く物事とそれから構成されている世界とを自己の存在にとって意味のあるものとして捉えたいという根源的な欲求である。
神話の知は、すぐれて象徴的であるとともに体系的である。近代科学とは異なる別種の論理、すなわち具象の論理とでもいうべきものを持ち、それによって全体として体系化されている。
科学の知が概念を構成要素としているのに対して、神話の知を構成しているのは意味を担った象徴である。抽象的な概念ではなく、具象的な像(image)であり、それは象徴として、すぐれて隠喩的に働く。神話はこの象徴の重なり合いによって表現される。神話において語られる単語や文章が言説として概して論理や整合性に欠き、一見、前論理的でありながら、深い宇宙論的意味を表すことができるのはそのためだ。
そこでは心象が体系化され日常の意味の世界が背景に退く代わりに、別種の意味の世界が立ち現れることになる。そして、神話は何度も繰り返し語られ、読まれることによってその構造性を一層強め、日常の背後から、日常の意味そのものを支える根拠として働くのである。
呪術はこの神話的世界に働きかけようとする技術である。近代科学の前提が、自然を支配する因果律への確信であるとしたら、呪術的知の前提となるものは、世界の中に存在する偶然性への関心である。呪術の知の根底にあるのは、偶然に満ちた世界の中で自分たちの運命を左右する超自然的な存在の意志を知ろうとする願いである。この偶然性、あるいは運命は、時として因果律への不信をさえ抱かせる。自然の持つ法則性に対して無関心な文化は存在せず、どのような民族も経験に基づいて自然の法則に適応した生活を送っている。その上で予測しがたい偶然の力を目に見えない存在の意志の働きとして恐れるのである。呪術はそれを操作しようとする技術論だと言える。
近代は乗り越えられるのか?
本書では、自我、身体、認識、宇宙像にわたって近代知の在り方とは別の知の在り方を模索してきた。しかし、それは果して近代の代替(alternative)としての役割を果たせるのだろうか。
当初の問題であった二極化する知性の総合という課題に対する答えは、これらの代替的知の在り方からどのように答えるのだろうか。それは、本書からは見えてこない。
中村氏はこの後、『共通感覚論』(1979)、『臨床の知とは何か』(1992)、等で、その知の具体的な在り方を論じていく。本書はそのための序論という位置付けだろう。
[adcode]

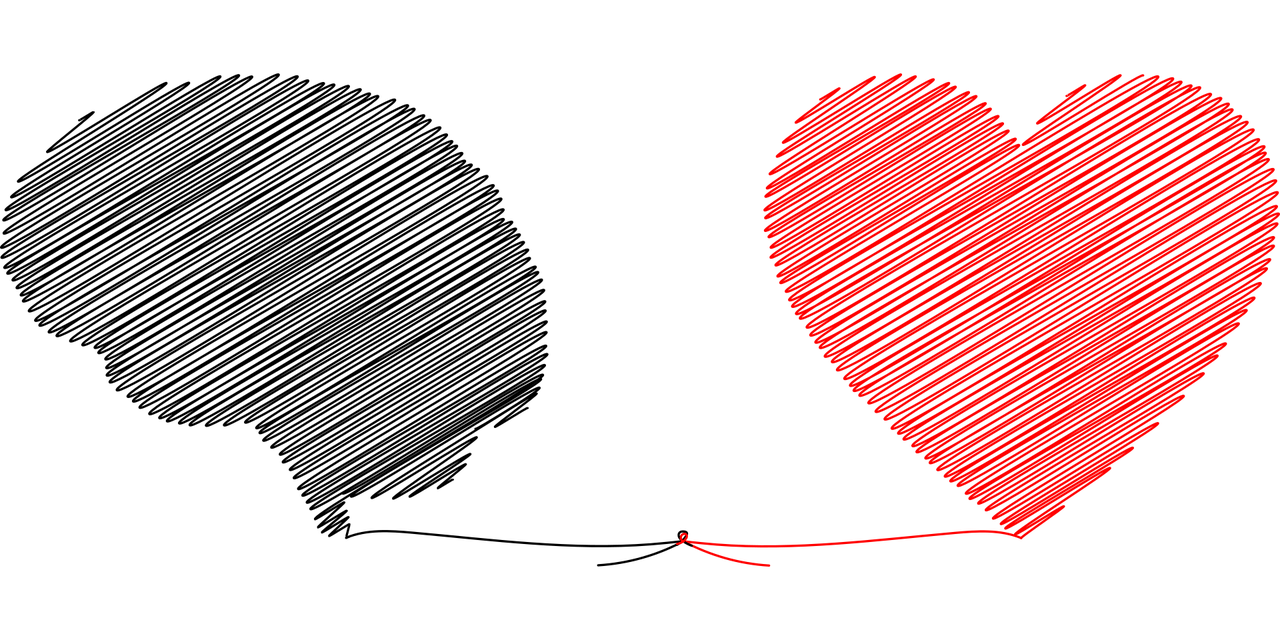

コメント