[adcode]
意識の科学的探究へ
意識を定義してください―――
そう言われたら、あなたはどう答えますか?
意識ってなんだろう?
心?それとも、脳?
実証研究を基礎としてきた近代科学において、「意識」は、極めて捉えがたい存在だった。
客観的な対象としては、その物質としての性格が不明瞭で「モノ」として捉えることができない。だが、一方で、意識の存在は、自分自身にとっては確実なものとして現れている。自己意識の存在は、自分にとって常に経験している「現実」だ。
対象化することが極めて困難である一方、自分自身には極めて明瞭に現れている意識――
このような捉え所のない「意識」を科学はどのようにして対象化してきたのだろう?今回は、「意識」の科学史をざっくりと素描してみよう。
[adcode]
内観法 – 自己記述の心理学
19世紀中葉のドイツ、ライプツィヒ――
生理学者ヴィルヘルム・ヴントが、それまでの哲学的、形而上学的な心理学を排して、実験を中心とした心理学を構想した。彼は、心理学を経験科学として位置付け、実証を重視した。近代科学としての心理学は、彼の実験心理学が始まりとされている。その後、19世紀末には「意識」は、科学の研究対象として心理学の中心を占めるようになる。
では、ヴントはどのようにして意識を科学的な対象として取り扱ったのだろうか?
ヴントの実験心理学が提唱した手法は、「内観法」と呼ばれるものである。
意識の過程をいくつかの心理的要素――さまざまな感情や心理状態――に分け、それらが互いにどのように結びつき、関係するかを明らかにすることが目標とされた。その方法として用いられたのが被験者自身が自らの心理状況を内観するというものだ。
内観法は、自己観察によって心理や感情の働きを見る方法である。自分自身が体験した自己の心理の働きを自ら観察し、それを口述や筆記などによって報告する。
実験科学としての再現性を確保するために、統制された状況下で意識の観察が行われた。具体的には、例えば被験者に一定の条件下である思考課題が与えられ、その課題を考察する際に心に浮かんだ感情や精神状態をすべて口頭報告させるというものであった。
内観法という実験の導入によって、意識は実証科学の対象となった。だが、それが直ちに科学的に正しいものとして受け入れられたわけではなかった。
内観法による実験が、どれほど統一的な条件下で客観的な観察基準を用いて行われたとしても、被験者自身の主観性を完全に排除することは不可能だった。被験者によって語られる心理内容は、その正確さと客観性を担保するものがなにもなく、そのため、どれだけ実験を重ねても、その結果が科学的に正しいものとして保障することができなかった。内観法は、科学的な方法論としては、実験結果から仮説や考察を導く範囲にとどまってしまった。
また、別の観点からも問題が提起された。それは意識を対象として正しく捉えているのか、というものだった。内観法では、意識の中で被験者が自覚化される部分のみを記述するため、意識の捉え方が非常に狭い範囲に限られることになった。自ら気付かない部分、無意識的な部分はすべて対象化されることができなかった。そのため意識という現象の捉え方そのものに疑問が投げかけられていった。
[adcode]
行動主義心理学の登場
内観法は被験者の内観報告に基づくもので主観性が強く、そのため研究者から広く支持を得ることができなかった。内観法は、20世紀初頭に登場した行動主義心理学によって次第に取って代わられるようになる。
行動主義心理学は、アメリカの心理学者ジョン・ワトソンが提唱した。彼は、心理過程という客観的な観察が不可能な存在を研究対象とするのではなく、心理過程の結果として現れた被験者の「行動」を観察した。
行動主義心理学の基本的な考え方は、心理過程の結果はすべて行動として表されるというものだ。したがって、意識の研究は、行動の観察によって可能になると考えられた。
第三者の観察者による客観的な把握が可能な「行動」のみが観察対象とされたため、実証科学としての性格はより強くなった。
しかし、行動主義は心理学としてはある種倒錯していた。というのも、意識や心理の働きは、行動から間接的に推測される対象となってしまったからだ。科学としての性格を維持するために、意識それ自体の存在が、意図的に研究の対象から外されたのである。
そして、その後、心理学の中で「意識」の存在は、科学的な研究対象としては扱われなくなっていった。この過程の中で、実験を中心とする行動主義心理学と、臨床に基づく解釈学的な精神分析とが分離し、互いに異なる発展を遂げていった。
[adcode]
脳科学の登場
20世紀中ごろから脳の生理的機能を検査する科学技術が飛躍的に進歩したことで、心理学を取り巻く状況が一変する――
脳科学が急速に進展したことを受けて、脳の働きを通して意識を考えることが科学的に検証可能になってきたのだ。
1929年、ドイツの神経科医ベルガーによって頭皮上に置いた誘導電極から、脳の集合電位変動がはじめて記録された。これを機に、意識を研究する上で、言語記述に依存しない検証に耐えうる指標として、脳の電位変動、すなわち脳波を調べる方法が一般化された。
脳波は、脳のニューロン集合の活動を反映し、樹状突起でのシナプス後電位より生じる。脳波は生きている限り停止することはなく、脳は常に様々な周波数からなる電気の振動を発生している。周波数帯域ごとに区分され名前が付けられており、それぞれ異なった生理学的な意義を有している。
脳科学の観測技術と情報科学の発展により、認知心理学がおこり、再び意識が注目されるようになった。「意識」の存在が再び科学の対象となったのだ。
意識の実証研究を可能にしたのは、脳を直接観測できる先端設備の整備である。たとえば、脳の血流量を調べるPET(ポジトロン断層法)、磁場をかけて脳を調べるMRI(磁気共鳴画像法)、液体ヘリウムに浸した超電導量子干渉計(SQUID)を用いて脳の微小磁場を調べるMEG(脳磁場計測法)などが、ニューロンの働きなどを解明しつつある。
脳の生理機能が明らかになるにつれ、意識とは脳の情報処理の一様式と捉えられるようになった。現代心理学において、意識とは、生物の生存、存続という志向性を持つ脳の情報処理の一様式であり、認識と行動を束ねる高次機能として定義されている。
また、ここで冒頭の問いに戻ろう。
意識とは、何か?
現代の心理学や脳科学では、意識とは、脳による不断の情報処理の結果として生じる「現象」であり、かつその「機能」を指すもの、と捉えられている。
つまり、意識を存在としてではなく、その機能として捉え、その振る舞いを科学的対象として記述しているのである。
[adcode]
参考図書
苧阪直行『意識とは何か』(1996)
[adcode]
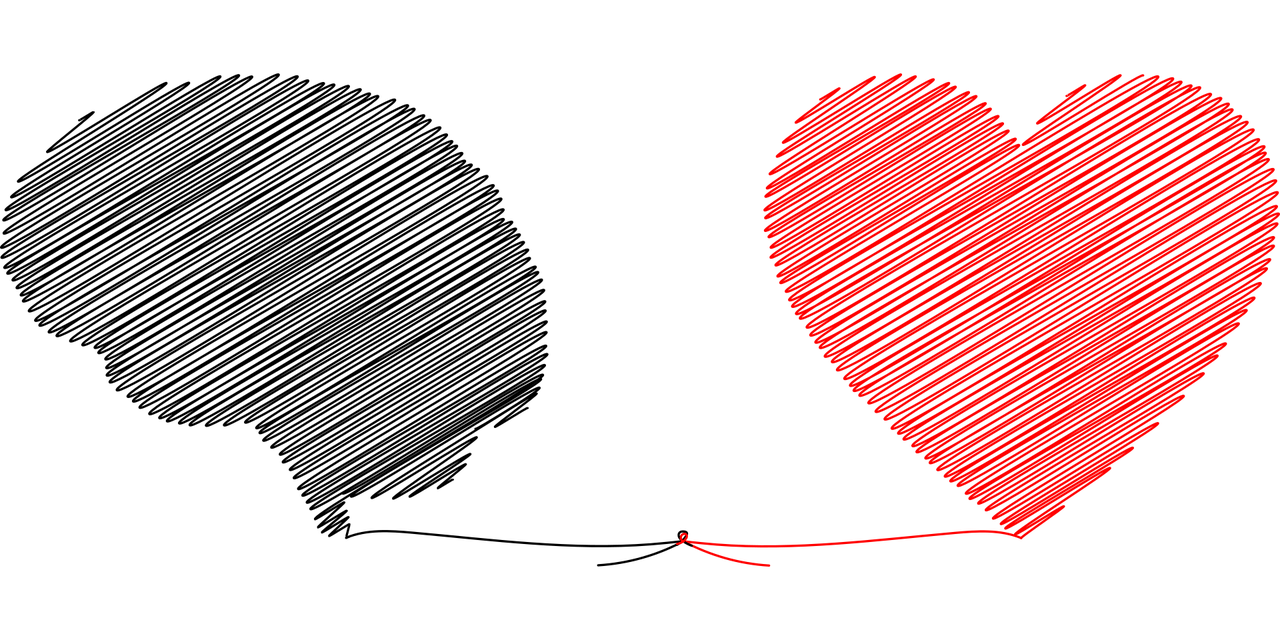


コメント