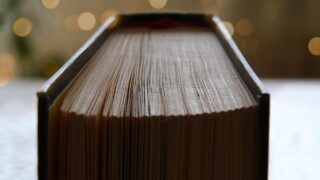 哲学談戯
哲学談戯 生への礼賛──ニーチェ『喜ばしき知恵』に見る療癒と意志の再生
ニーチェ『喜ばしき知恵』(1882)「生」への賛美へ 来るべき勝利が、いや、かならずや訪れる、ことによるとすでに到来しているかもしれない勝利が……。 およそ予想外のことが起こったかのように、感謝の念がそこここに溢れ出ている。快癒した者の感謝...
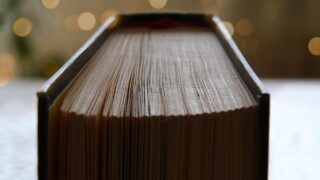 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯 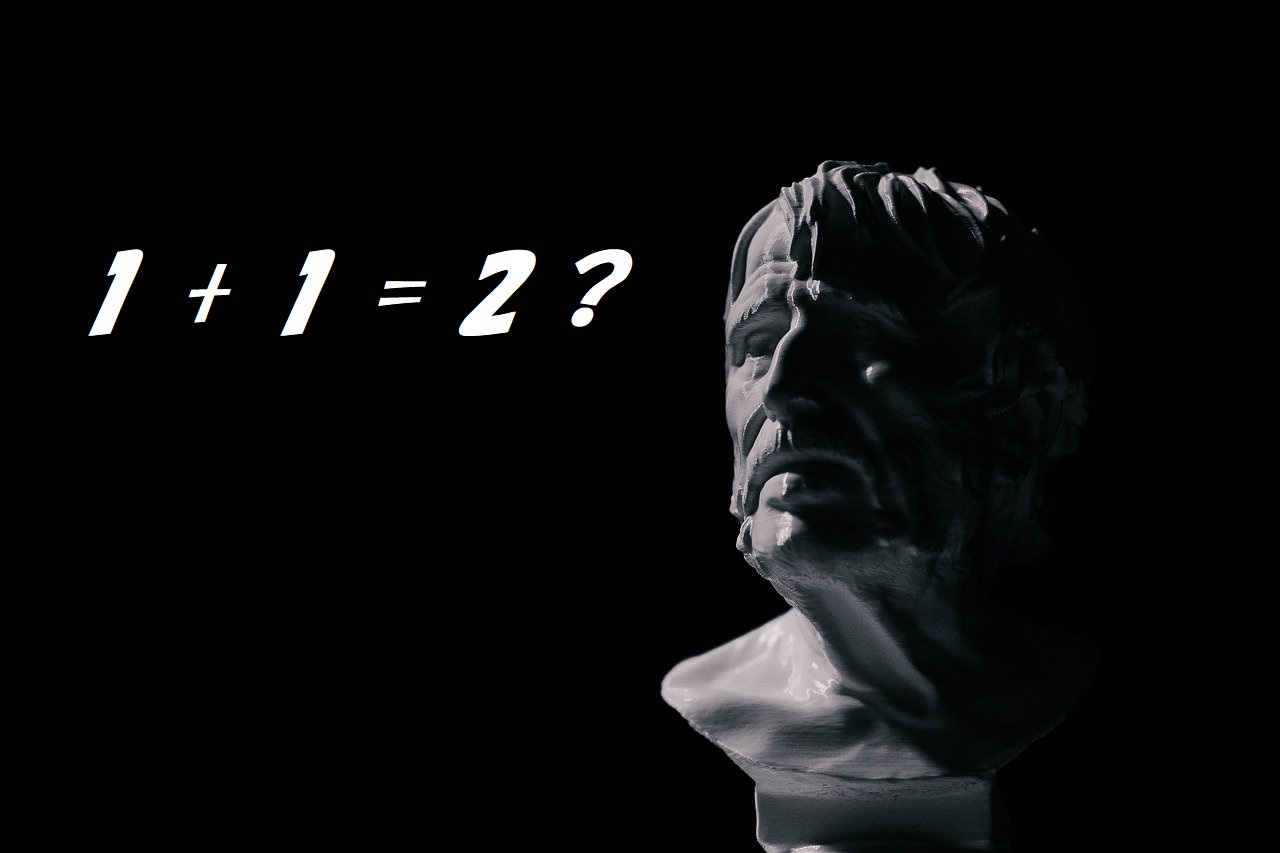 哲学談戯
哲学談戯  晴筆雨読
晴筆雨読  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  方々日誌
方々日誌