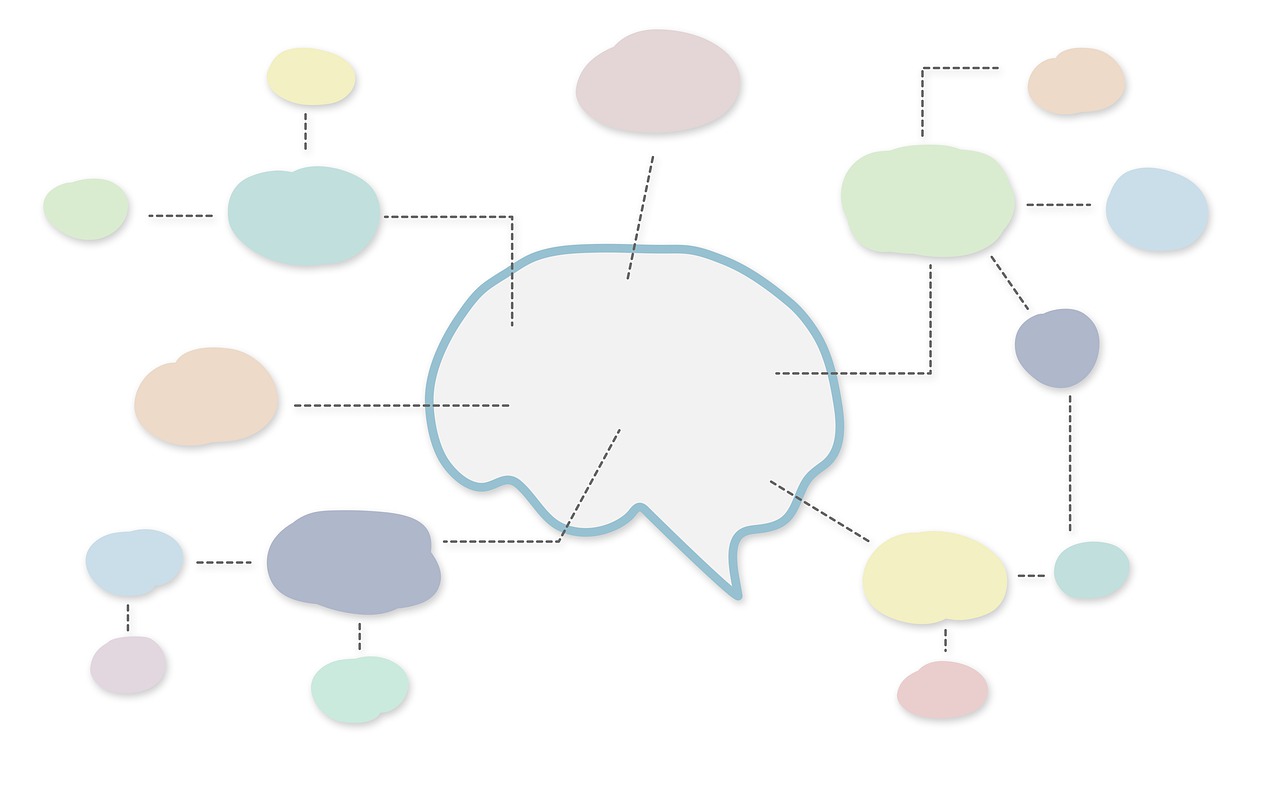 科学半解
科学半解 脳科学はチョムスキー理論を証明できるのか? – 脳機能の普遍性と情報処理の普遍性の違い
言語相対論からチョムスキーの普遍文法論へ 言語が異なれば、物事の捉え方や把握の仕方も異なる——— このような考え方は、「言語相対論」と呼ばれる。 19世紀から20世紀にかけて西欧諸国が植民地を拡大する中で、非西欧文明との接触が進み、世界の多...
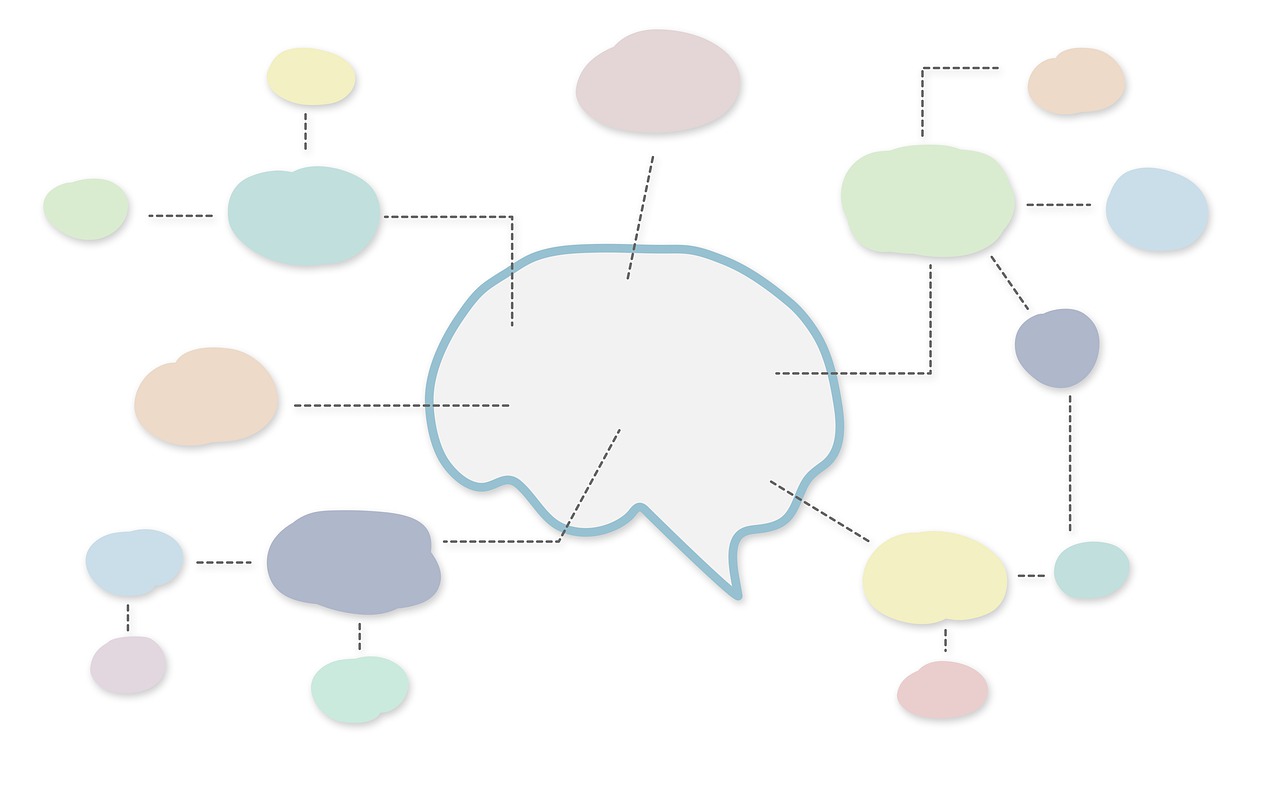 科学半解
科学半解 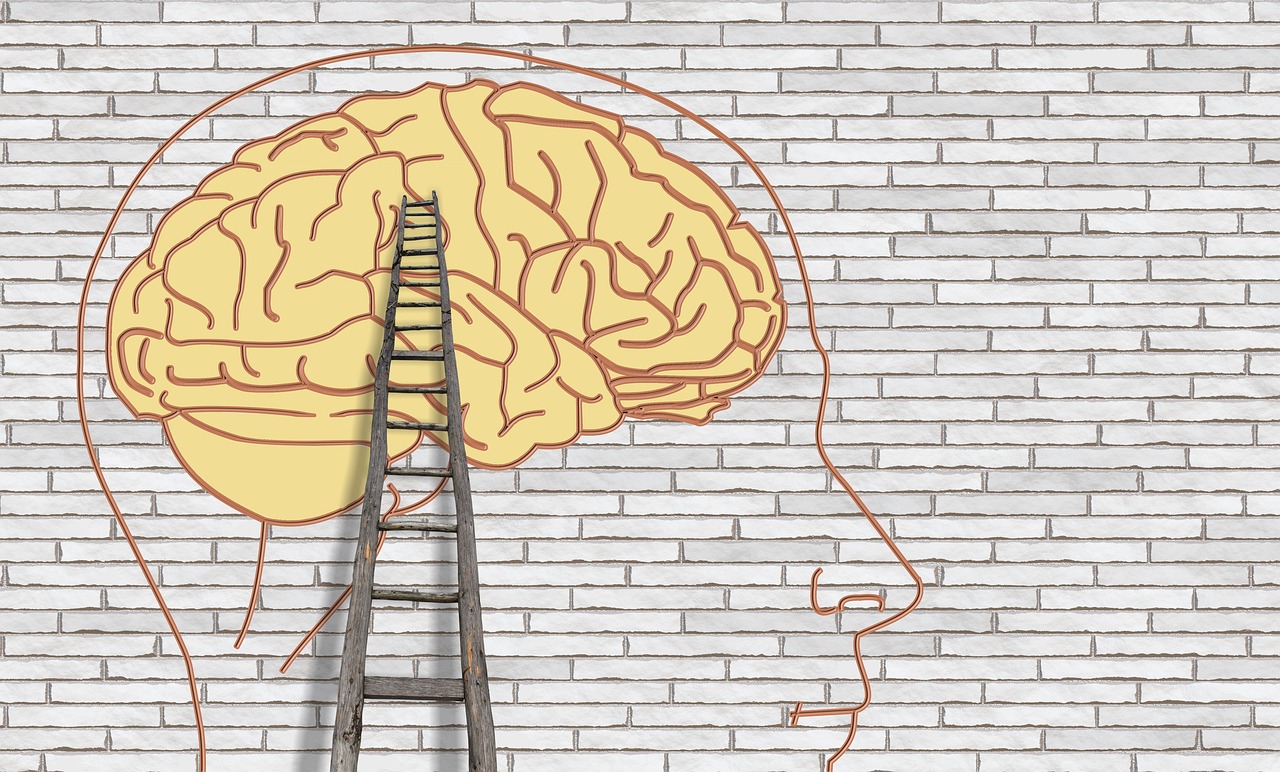 科学半解
科学半解  千言万句
千言万句  千言万句
千言万句  千言万句
千言万句