 方々日誌
方々日誌 Blues Rockの最高峰 – Sonny Landreth – The Road We're On (2003)
Sonny Landreth - The Road We're On (2003) このalbumを聞いたときは、ほんと、衝撃的だった。 演奏はほぼguitar、base、drumsだけという非常にsimpleな構成。 Sonny Land...
 方々日誌
方々日誌 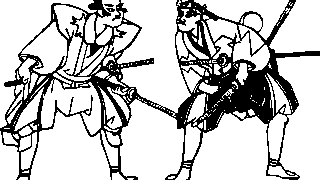 晴筆雨読
晴筆雨読  千言万句
千言万句 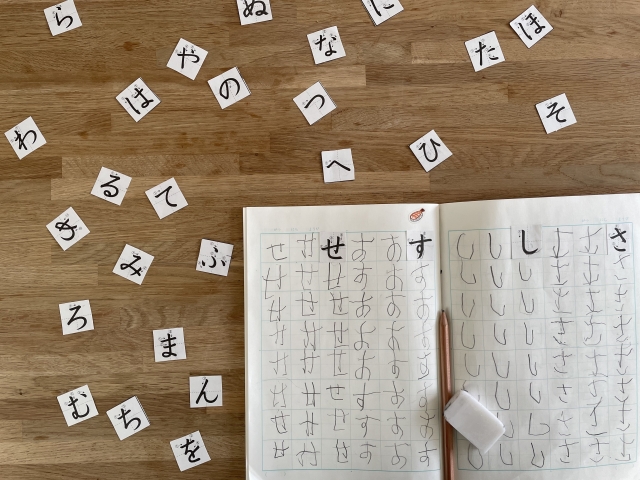 千言万句
千言万句  哲学談戯
哲学談戯 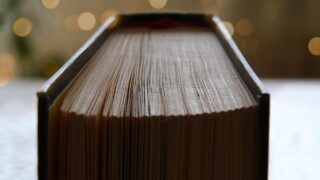 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯