市川浩『精神としての身体』(1975)
身体への問い
1975年初出。講談社文庫版は1992年の出版。
身体論を展開した哲学者、市川浩氏の最初の論考。
西欧の近代哲学は17世紀以来、認識論を中心に展開してきた。しかし、認識の根拠を問う際に、身体の問題は基本的に問われることがなかった。むしろ、身体こそが認識を基礎づける根拠として存在しているのではないか―――
この問いが、著者の身体論の出発点となった。
対象であり、かつ主体であるという二重性を持った「身体」にこそ、原初的な意味での反省の始まりがあり、それがやがて、対象および他者との関わりにおいて自己性の把握を可能にするような「構造」があるのではないか。この身体の特有の構造こそ基点とすべきではないか。著者はそう問う。
近代の認識論は、身体性を捨象したことで、精神と身体が二元論として分離する結果となった。いわゆる精神と身体とは、身体の持つ独特の構造のある一局面だけを抽象化した結果得られたものだろう。近代の心身二元論は、認識論上の便宜から現れたとしか言いようがなく、そこからは、答えることのできない問題群が生じることになった。倫理的、決断的主体としての自己は、自己のどの側面から現れてくるのか。実体的な自己は、関係的な自己から把握されるべきか。あるいは、関係的な自己を実体的なものと呼ぶことができるのか。等々。。。
そして、現在、社会的には、間接的、情報的経験が増え、経験の直接性が失われつつある。現代こそ、身体性への関心は高まっている。
こうした認識の下、市川氏は、身体の持つ構造を解き明かしていく。
現象としての身体
市川氏はまず、われわれの存在は身体を持つのではなく、身体である、という。身体は、コギトを成立させる地平であり、この地平がコギトを世界の中に根付かせ、コギトに認識的視点(perspective)を持った現実的な認識をもたらしている。
だが、この身体は、認識の絶対的基盤となるようなものではない。それは、他者との関係性の中で、その構造を無限に転換させる。それは対象を見ている限り「主観身体」であり、他者の身体を通じて見られることで「対象身体」となり、その見られる自己を意識化することで「対他身体」となる。市川氏は、この「対他身体」の安定的な形成が自己の同一性を支えていると捉える。
確固たる客観的な身体ではなく、間主観的な身体性を想定していると言えるだろう。このような性質として存在する身体の持つ構造が本書の主題となる。以下に著者の身体論の構成を素描してみよう。
構造としての身体
身体の構造を捉えるにあたって、それを二つの次元に区分している。身体が、下意識的(前意識的、あるいは無意識的)な次元で統合されたものを向性的構造と呼び、意識的な次元で統合されたものを志向的構造と呼ぶ。
向性的構造は、前意識の段階で自己及び環境をひそかに分節化し、当てにしうる諸可能性による緩衝地帯を作り上げる。これにより、向性的構造は、志向的構造が生成するための基本的な条件を確保する働きがある。それは、志向的構造の生成の仕方を一義的にではなく、多義的にその可能的な生成の仕方を方向付けるような構造である。
このような向性的構造を前提にして志向的構造が生成する。志向的構造は、状況を支配し、統御するが、それは向性的構造により与えられた諸可能性の中から一つの図式を選択しているにすぎない。志向的構造は、図式の内部の構造を向性的構造の次元による組織化に任せることで環境からの決定論と過剰選択による選択不能な状況に陥ることを防いでいる。このような二重構造が環境の中から生存可能性を確保し、行動可能性の中間地帯を構成する。
行動の構造
生体はその種に固有の生活世界を持っている。行動の構造は、もろもろの生理的基体の構造にもとづけられているが、それらの総和に還元されはしない。世界を分節化するのは、解剖学的な身体の構造ではなく、働きとしての身体の機能構造であり、広い意味での行動の構造である。
自己存在の地平
では、なぜ身体にこのような二重構造が必要なのだろうか。
環境に対して何かを志向するというとき、志向的意識は常に自己の意識を伴っているとは限らない。むしろ自己意識を伴わず、対象に向かっているのが普通である。しかし、われわれは反省によっていつでも対象を志向している自己を意識することができる。したがって、これは意識が対象に志向しているときにも、前意識的かつ、非措定的にわれわれが自己を把握していることを意味している。
この自己把握は意識的志向を構成する不可欠の要因であるが、ここで把握された前意識的な「私」は、志向の背後にある一つの実体ではない。それは志向的構造の自己把握であり、決して全面的に主題化され、意識化されることはない。
知覚する時われわれは「何か」を知覚する。その何かは、意識の焦点にあって明瞭に把握されている「図」であるが、その周りには不分明にしか把握されず、あるいはほとんど意識されない前意識的な「地」が広がっている。それゆえ知覚された存在は、実体としての存在ではない。それは指示作用としての図化であり、「あるもの」としてのXではなく、「目下の主題は、何々である」ということを示す主題化の機能としてのXである。
志向が存在する限り、「私」も「何か」も一挙に与えられている。そして志向の焦点にある「図」とともにその周りに広がる「地」としての世界もまた与えられている。より根本的には反省以前において、すでに「私」は、こうした意識下的な構造に組み込まれており、歴史性を持ったものとしてすでにその志向性を規制されている。対象化された自己の不透明さというものはここに由来しており、自己自身に与えられたコギトの不十全性と未完結性が払拭されることはあり得ない。
このようにして身体の二重的構造は、意識の志向性という次元で生じる表裏の関係ということになる。市川氏の身体論は志向性の一元論ということができる。これが「精神としての身体」ということが意味するところだろう。


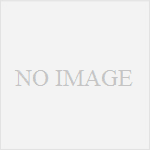
コメント