 科学半解
科学半解 近代医学の転回点:科学的病理学と臨床知の対話
臨床的知識とは何か? 現代の医療現場では、医療従事者に対して性質の異なる二つの知的能力が求められている。一つは、病理学や薬理学といった基礎医学の知識に基づき、病気の原因や症状を科学的に分析・診断する「科学的知性」である。そしてもう一つは、患...
 科学半解
科学半解  科学半解
科学半解  哲学談戯
哲学談戯  科学半解
科学半解 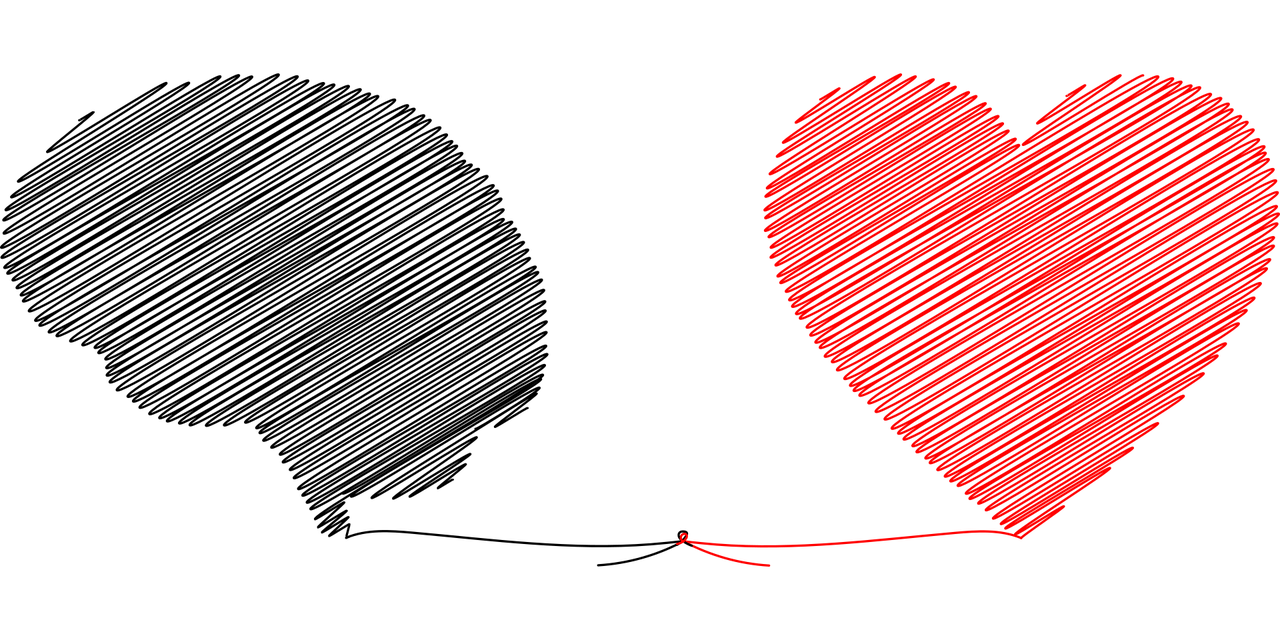 科学半解
科学半解  哲学談戯
哲学談戯 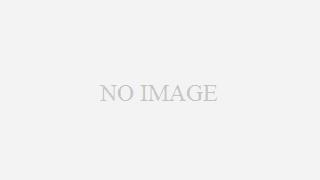 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  晴筆雨読
晴筆雨読  哲学談戯
哲学談戯