プラトン『恋がたき』
哲学を学ぶとはどういうことか?
プラトンの対話篇のひとつに、『恋がたき(あるいは『恋人たち』)』という作品がある。副題は「哲学について」。この作品は、伝統的にプラトンの著作とされてきたが、現代の計量文献学の分析によれば、紀元前4世紀後半に成立したと見られ、文体や語彙の統計的特徴から、むしろクセノフォンの著作との類似性が指摘されている。プラトンの真作ではなく偽作の可能性が高いと考えられている。
プラトンの対話篇の多くは、対話相手の名前がそのまま題名になっているが、本作では名のない若者二人が登場人物であるため、彼らの関係性に基づいて『恋がたき』という題名が付けられている。
物語は、同じ少年に恋する二人の若者とソクラテスとの対話という形で進行する。一人は文芸(ムシケー mousikē)に、もう一人は体育(ギュムナスティケー gymnastikē)に親しんできた青年である。ソクラテスは彼らに対し、「哲学を学ぶとはどういうことか」を問いかける。
文芸を好む若者は、「哲学とは、多くを学ぶこと」であると答える。これに対しソクラテスは、「それは単なる博識(polymathia)にすぎないのではないか」と問い返す。若者はこの異議に応えつつ、次のように哲学者像を描く。
「…専門家によって語られることに、その場にいる者の中でも段違いによくついていくことができ、さらには自らの見解を披歴して寄与することもできるので、その結果、諸々の技術に関して述べられ実践される事柄について、いつでも、その場に居合わせている者の中で最も知的に洗練され賢いように見えるのです」
つまり、哲学者とは、特定の技術に習熟した専門家になることではなく、さまざまな学問に適度に触れ、それらを理解し、自らの知見として統合できる人物であるべきだと彼は主張する。今日の用語で言えば、専門家(スペシャリスト)ではなく、指導者的な教養人(ジェネラリスト)としての哲学者像が描かれている。
このような発想は、実は現代にも当てはまる。現代において「学ぶ」とは、主に二つの方向性に分かれる。ひとつは、専門的な知識を深め、ある特定の分野で貢献できる人材を目指す道。もうひとつは、幅広い知識に基づいて総合的な判断を下せる能力を身につけ、社会や組織を指導する存在になるという道である。特に後者は、政治や経営、教育などの分野で、リーダーに求められる知性とされる。
現代社会においても、私たちは専門家の知見を尊重しつつ、最終的な決定は、複数の分野を横断的に理解し、総合的に判断を下せる人物に委ねようとする。この意味で、文芸好きの若者が示した哲学者像は、現代の「リベラル・アーツ」的な知性の理想像にも重なる。
しかし、ソクラテスはそのような考え方を退ける。彼にとって哲学とは、単に多くを知り、知的に見えることではなく、真理を探究する知の姿勢そのものであった。
ソクラテスの答え──哲学とは何かを問い続ける営み
ソクラテスの答えは、「哲学をするとは何か」を直接的に語るのではなく、それが「何ではないか」という否定のかたちで示される。
- 哲学とは、博学的な知識を得ることではない。
- 哲学とは、特定分野における専門的知識の習得でもない。
- 哲学とは、専門家の知識をなぞる「二番手」に甘んじることでもない。
では、哲学をすることとは一体何なのか?
ソクラテスはその答えを、次のような一言に込めて示唆する。
「してみると、どうやら、デルポイの神殿の内に刻まれた言葉は、そのこと、つまり節度と正義に努めよ、と命じているようだ」
ここで言及されているデルポイ神殿の銘、「汝自身を知れ」は、ソクラテスの哲学の核心を象徴している。哲学をするということは、何よりもまず「己自身を知ること」であり、それは節度(ソフロシュネー)を身につけることに他ならない。
節度を持つ者こそが、自らの限界を知り、欲望に支配されず、真に正義にかなった判断を下せるというのが、ソクラテスの考えである。
この考え方は、前段の若者が語った「哲学=広範な知識の統合による知的優位性」とは根本的に異なる。若者の捉える「知識」は、制度としての学問体系に基づいた理解である。実際、プラトン以降、アカデメイアが設立され、学問は算術、幾何学、天文学など専門分野ごとに整備される。そして、さまざまな分野に精通したのち、指導者としてふさわしい「哲学」、特に形而上的な思弁を学ぶべきだとされた。
このような発想は、学問が制度として定着した世界における知識観である。
そうした点から見れば、『恋がたき』に登場する若者の知識観は、まさに「ポスト・プラトン的」なものであり、この作品がプラトンの偽作とされる最も有力な根拠の一つにもなっている。
一方で、ソクラテスの哲学観は、それ以前の、つまり学問が制度化される前の知のあり方を体現している。彼にとって哲学とは、知識の蓄積ではなく、むしろ宗教的な内省にも似た自己修養の営みであった。「知を愛すること(philosophia)」は、単に知ることを目的とするのではなく、無知を自覚し、自己を問い直す姿勢に支えられている。
「学ぶ」という行為は、本来、自己との対話を通じて自分を見つめ直すことに深く関わっていた。しかし、現代では、知識の量や即効性、実用性が重視されるあまり、学びに内在していた人格的・倫理的側面が見えにくくなっているようにも感じられる。こうした状況の中で、学問や知識が、個人の生き方や在り方とどのように結びついているのかが、改めて問われているのかもしれない。
そうした視点に立てば、たとえ『恋がたき』がプラトンの真作ではなかったとしても、この作品が描き出す哲学的対話には、現代に通じる重要な問いが含まれているといえる。
哲学とは、何を知っているかではなく、どのように生きるかを問い続けることである。
この古い対話篇は、私たちにその原点を思い出させ、哲学本来の意義を今に問いかけているのではないだろうか。
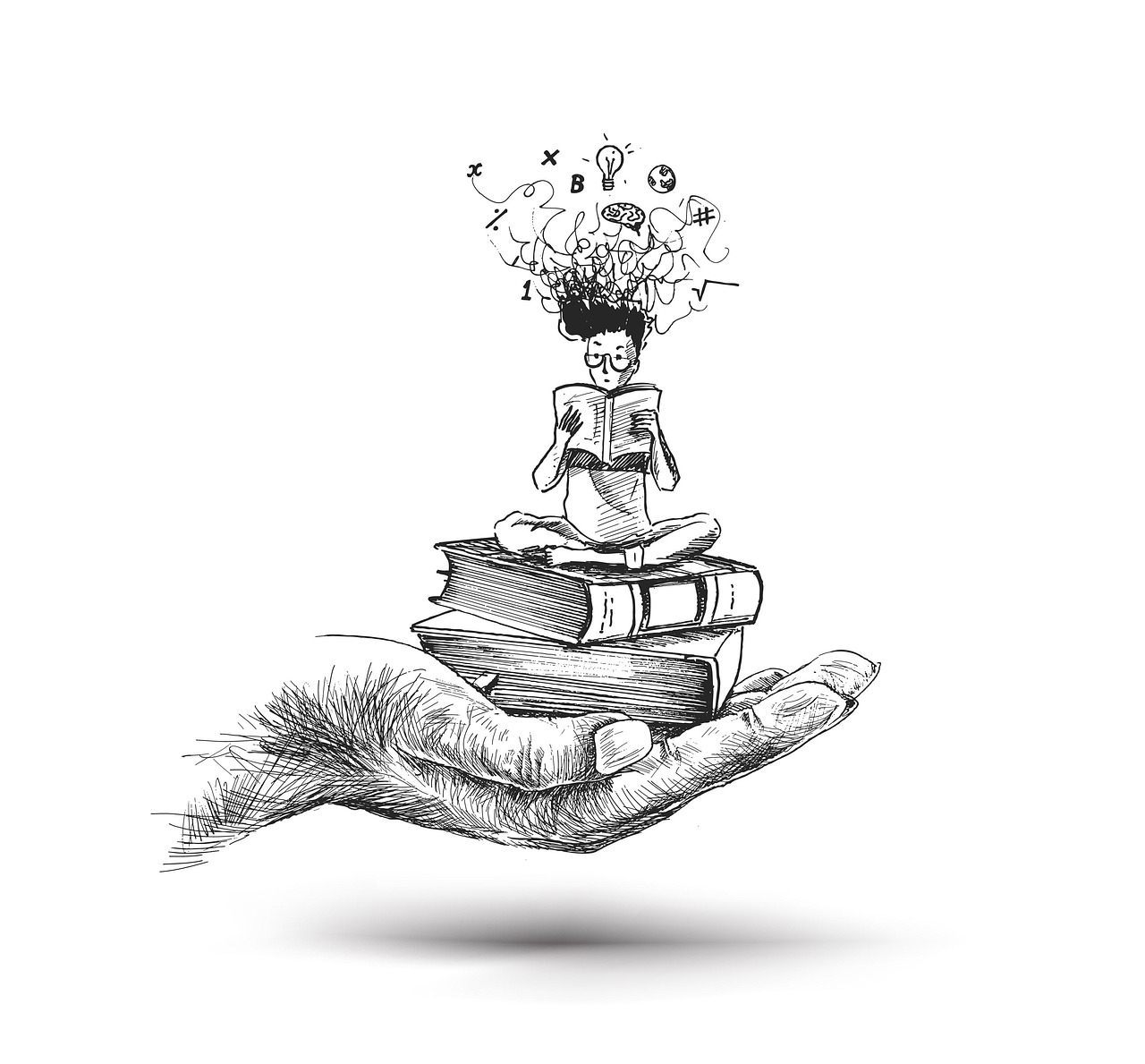


コメント