ニーチェ『ツァラトゥストラ』(1883-5)
道化師としてのツァラトゥストラ
ニーチェの『ツァラトゥストラ』は四部構成で、1883年から1885年にかけて出版された。当初はほとんど注目されず、読者からも理解されなかった。とりわけ第4部に至っては、出版社が見つからず、わずか40部のみの自費出版にとどまっている。
だが、1890年頃から、一部の知識人や読者の間で熱狂的な受け入れられ方をしていく。このニーチェ熱はナチス・ドイツにまで影響を及ぼすこととなった。
本書はこれまで多くの思想家や研究者によって取り上げられ、永遠に続くかのような矛盾と曖昧さに満ちた文体に、さまざまな解釈と評価が加えられてきた。しかし、この「要領の得なさ」こそが、本書の最大の演出であるともいえる。
読者がその文体に翻弄されている姿を、ツァラトゥストラはどこかで面白がって見ているようにも思える。その滑稽さを意図的に演出し、人々を踊らせる──そのような「道化師」としてのツァラトゥストラを創り出したことこそ、ニーチェの真の功績ではないだろうか。
ツァラトゥストラは、預言者や伝道師ではなく、むしろ道化師であった──私はそう考える。
たしかに、「神の死」を宣告し、「超人」の到来を説くツァラトゥストラは、預言者のようにも見える。(実際、『ツァラトゥストラ』は、聖書のパロディとして書かれている。)そのように彼を捉えるならば、彼はニヒリズムの時代に現れた「救済者」として、つまり、自ら価値を創造する生き方を提示することで、世界のあり方を変えるために現れた存在だったといえるだろう。この見方は、ニーチェの同時期の著作『悦ばしき知識』への理解とも一致する、一般的かつ主流の解釈である。
しかし『ツァラトゥストラ』で描かれている人物像は、より諧謔的で戯画的だ。彼は、ニヒリズムの時代そのものを楽しんでいるかのように振る舞い、世間の反応など意に介さない。まるで、世界のことなど気にもしないかのように。そこには深刻さを逆手に取った、自由で軽やかな知性が感じられる。
こうして見ていくと、ツァラトゥストラの本質は「預言者」としてではなく、「道化師」としての姿にあるのではないか──そのような視点こそが、ニーチェの思想を新たに読み解く鍵となるのではないだろうか。
生への意志から、権力への意志へ
ニーチェが他の著作で繰り返し問題にしていることの一つは、ニヒリズムだ。彼にとって、ヨーロッパ近代の理性が直面している最大の危機こそが、ニヒリズムの到来だった。そしてこのニヒリズムは、人間の理性の発展がもたらした帰結でもあった。
歴史学や古典文献学といった近代科学としての厳密な学問は、宗教や道徳にまつわる神話性を容赦なく剥ぎ取っていく。人間の知性は、やがて必ずあらゆる価値の裏にある虚構性を暴き立て、すべての価値を相対化せざるを得ない。それが、近代理性の宿命である。
ヨーロッパの近代的理性は、客観的な真実のみを追究する科学的な態度と精神を人々の間に生み出していた。かつての宗教的信仰は、科学的な態度の下で徐々に解体されていく。そして、すべての物事が信じられなくなったニヒリズムの時代が到来する。理性の時代である近代は、このニヒリズムから決して逃れられないだろう。
そして、ニーチェの理性は、さらにキリスト教の内に潜む欺瞞、すなわちルサンチマン(怨恨)を見抜いた。これは、弱者が自身の惨めな境遇を正当化するために、「弱さ」や「貧しさ」を道徳的に価値あるものと見なす、価値の転倒を指す。ニーチェによれば、キリスト教に限らず、あらゆる宗教や道徳の背後には、このような虚偽や欺瞞が潜んでいる。
科学的知性による真理の相対化と理性による宗教的欺瞞の暴露──これが近代理性のたどり着いた帰結であり、価値不在の時代、すなわちニヒリズムの時代の始まりだった。
このニヒリズムから人々を救済するための存在がツァラトゥストラだ。
『ツァラトゥストラ』は、主人公が洞窟から出て、神の死を町の人々に告げるべく山を降りる場面から始まる。しかし人々は、ニヒリズムの到来すらまだ自覚していない。神はすでに死んでいるというのに、古い価値観にすがりついたままだ。だからこそツァラトゥストラは、神の死を知らせ、新しい時代の生き方を示す必要がある。
それが「超人」の到来の予告である。超人とは、ニヒリズムの荒野を突き抜け、自らの力で新たな価値を創造して生きる存在である。そこには、弱者の怨念でしかない従来の道徳を否定し、「いま・ここ」における生そのものを肯定する意志がある。
だが、この超人による「生への意志」は、容易に「権力への意志」へと置き換わる。この「生への意志」は、やがて「権力への意志」へと転化する──そうニーチェは解釈されてきた。実際、ニーチェの断片的な草稿群は、妹エリーザベトの手によって編集され、『権力への意志』という書物として世に出された。そしてそれが、ニーチェ思想の代表的表現として広く受け止められるようになった。
ニーチェ自身がのちの著作『善悪の彼岸』において、「生への意志」を強さへの訴求──「正しくない」ことが「悪」なのではなく、「弱い」ことが「悪」──として説明している。
しかし、私はツァラトゥストラの姿に、そのような「権力臭さ」を読み取ることがどうしてもできない。
ツァラトゥストラは山上の洞窟と町とを往復し、社会の下層にいる者たちと酒宴を開き、陽気に踊る。その姿からは、支配や権威とは無縁の、どこか浮世離れした自由さが漂っている。むしろ、世俗的な権力や秩序から解き放たれた、ある種の脱世間的なユーモアの体現者としてのツァラトゥストラがそこにいる。
言ってしまえば、彼は「飲んだくれて陽気に踊るだけの、働かないオッサン」のような存在だ。はたして、そんなツァラトゥストラの「生への意志」は、本当に「権力への意志」と同一視できるのだろうか。
飲んだくれの陽気なおっさん
『ツァラトゥストラ』という作品だけを素直に読めば、ツァラトゥストラが酒宴に招いたのは「賎民たち」であり、作中で「高級な人々」と呼ばれているのも、実はそうした社会の底辺に生きる人々である。つまり、ニーチェがここで「高貴」と呼んでいるのは、社会的強者ではなく、むしろ既存の価値から脱落した弱者たちにほかならない。
強者が「生への意志」を貫くことなど当然であり、それ自体に価値転換の必要はない。むしろ、真に超人の思想を必要としているのは、歴史的に抑圧され、従属させられてきた弱者たちではないだろうか。宗教や道徳というものは、歴史上常に権力者によって統治の原理として利用されてきたのだから。超人の思想による価値の転換を本当に必要としているのは、弱者なのだ。
しかし、弱者がルサンチマンとしての宗教や道徳にすがりついている限り、その思想は再び支配の構造に取り込まれてしまう。重要なのは、弱者自身がその怨恨を乗り越え、自らの生を肯定する力を取り戻すことにある。ツァラトゥストラは、そのことを体現しているように見える。
彼は、超人の思想を「教える」伝道師ではない。ニヒリズムの時代に軽やかに踊る「道化師」なのだ。彼には、自らの思想によって世界を変えようとする意図はない。彼の超人としての生き方を見て、それを必要とする人のみが、彼の生き方に従えば良い。それ以上でもそれ以下でもない。
ルサンチマンとは、他者との比較の中から生まれる感情である。だからこそツァラトゥストラは、伝統や社会の価値観といった「他者から与えられる意味づけ」を捨て去り、自らの存在を、自らの意志で肯定せよと語っているように思える。
その意味で、ツァラトゥストラは権力志向の人物ではなく、むしろ脱社会的な存在だ。彼は既存の価値体系の中で勝者になることを目指しているのではない。むしろ、その枠組みを笑い飛ばし、価値そのものを問い直す者である。『ツァラトゥストラ』という作品を単体で読めば、そうした像こそが浮かび上がってくる。
だから私は、この作品は、より単独で、テキストそのものとして読まれるべきだと思う。ツァラトゥストラは、いかめしい思想を説く伝道師でも預言者でもない。ただ、「高貴」な人たちと酒を酌み交わし、陽気に踊るだけの、「飲んだくれのオッサン」なのだ。
Also sprach ich!
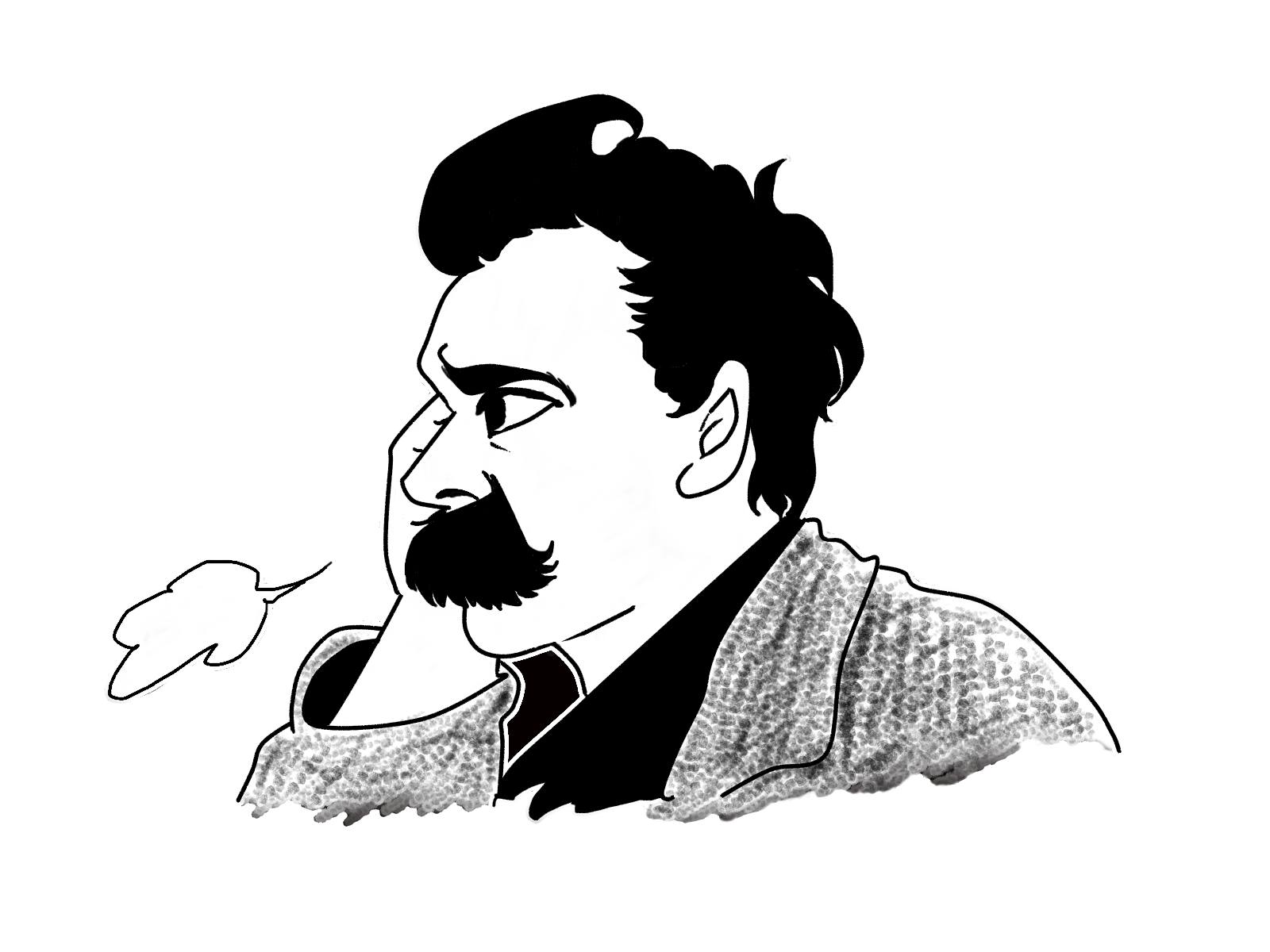



コメント