水村美苗『日本語が亡びるとき』(2008)
消えていく言語
一説によれば、現在世界には約5,000から8,000の言語が存在するとされる。数え方にもよるが、少なくとも3000近くあると見るのが一般的らしい。
世界には多種多様な言語が存在しているが、それと同時に消滅の危機に瀕している言語も数多くある。ユネスコの2009年の調査によれば、その数は約2500にのぼる。世界の言語の約半数が危機に瀕していると考えられている。
ある特定の言語が話者数を急速に伸ばしている一方、多数の言語は消滅の危機にある。情報技術が進展して、この傾向には一層の拍車がかかっている。
言語は決して平等ではない。言語の国際的地位は、その言語の話者集団が持つ文化的優位さ、政治的影響力、経済的な強さを反映している。かつての文明の隆盛を担った言語もあれば、地方の一言語として消滅していったものもある。
現在では、英語が圧倒的に優位な地位にある。英語を学ぶことが学術的、文化的、経済的に優位に立つ上で必須の条件となっていることは間違いない。だとすれば、今後、日本語は一体どういう立ち位置を迫られるのか。
消えてなくなる?
それとも、日本人は日本語だけで十分やっていける?
これは、「英語を話せなければ世界から置いて行かれる」といった類いの英語教育論ではない。
世界の歴史の中で生まれた「日本語」という文化遺産の歴史的意義をどう評価するのかという文明批評に関わる問題である。そして、われわれ日本人のアイデンティティに関する問いである。本書は、そうした観点から、「日本語」の歴史的な意義とその未来について考察している。
といっても、本書はエッセイだ。作家らしい繊細な視点から、日本語の行く末を論じている。
興味深い観点が多いが、ベネディクト・アンダーソンの近代国民国家論を下敷きにした「国語」論が面白かったのでその点を中心に紹介してみたい。
言語の社会的地位 – 「普遍語」「国語」「現地語」
それぞれの言語の歴史的な意義は、その言語が担った社会的な役割によって大きく異なっている。言語が果たした歴史的、文化的な意義に従って、著者は、世界の言語を「普遍語」「国語」「現地語」の三種類に分類している。
「普遍語」とは、かつてのラテン語や漢語であり、文明の中枢を担った言語だ。様々な異なる言語を話していた周辺民族の間においても「書き言葉」として浸透し、中心文化の最先端の知識を伝達する役割を担った。また共通語としても機能していた。
当時の知識階級にとって、この言語を習得することは、中心文化の知識を得るための唯一かつ必須の手段だった。民衆の話す「現地語」に対して、「普遍語」は文化の中枢を担うことのできる特権的な地位にある言語だった。
近代に入り、国民国家の時代になると、「現地語」を「普遍語」の地位にまで引き上げようとする文化的な運動が盛んになる。文化の中枢を担う知的作業は、今まで「普遍語」を通じて行われてきた。それが、知的なものだけでなく、美的、倫理的なものまで含めて、その「普遍語」の役割を担いうる言語として、「現地語」を彫琢していく文化的な努力が進められていった。
こうして、近代国民国家の時代に生まれたものが「国語」という言語だ。各国の「近代文学」と呼ばれるものも、この文化的な運動の中で生まれていったものだ。
しかし、すべての「現地語」がこのような「国語」へと昇華していくことに成功したわけではない。実際は、成功した言語の方が圧倒的に少ない。日本語は、実は、こうした「国語」へと昇華することに成功した稀有な例のひとつなのだ。
現地語が近代的な言語として機能するようになるためには、文法や表現に関してさまざまな実験や改良が必要になる。官民問わず、広く一般的に、このような知的作業が積み重ねられることによってはじめて、「国語」は成立する。
江戸末期から明治大正にかけて、日本語は大きな変遷を遂げている。現在の日本語は、もともとあるものではなく、近代的な「国語」を作り上げようとした文化的営為の中で生まれたものだ。決して自然に生まれたものではない。
今、われわれは、日本語だけで、決して世界に引けを取らない高度な次元で、知的作業を行うことができる。これを多くの日本人は当たり前のように受けとめているが、極めて高度な知的作業に耐えうる近代的な言語というのは、世界全体で見れば実は圧倒的に少ないのだ。
これは、誇ってよい日本の歴史のひとつだろう。だが、今では、日本語が「国語」として「あまりに成功し過ぎた」という事実が、かえって今の日本語の悲劇につながっている。それは、すなわち、日本語に対する「甘え」を生んだということだ。
日本語に対する甘え
日本語は、多くの日本人にとって、あまりにも所与のものとなっている。今の日本語が明治期を中心に多大な知的営為の下で生まれた近代言語だということを忘れている。
日本語が近代において知的な営為の下で作られたものであること、そして、文化というものは防衛意識がなければ、継承されずに消滅していくものであるという認識が全く欠けている。ほとんどの日本人にとって、日本語はあたかも大地のように、かつても、そしてこれからも、自然とそこに存在し続けているかのようだ。
しかし、日本以外の大概の国では、そのような意識はない。陸続きの国境、多民族社会、度重なる侵略の歴史を持った国がほとんどだ。そのような国では、言語や文化というものは所与のものではなく、人々の意識的な努力によって守られるものだ。
日本は比較的、歴史的地理的条件に恵まれたため、かえって言語や文化の防衛に対する意識が低く、蔑ろにしている。
結局、これは、日本語に対する「甘え」である。日本語に依存し、日本語でなくてはろくな表現も思考もできないくせに、日本語を高次の思考、表現に耐えうる言語として磨き上げようとする努力も忘れている。
安易なカタカナ語の氾濫、「交ぜ書き」など漢語の簡略化、破格文の乱立、等々。。。言語の論理性に対して無自覚な結果現れた奇妙な日本語の数々。。。
これを、「日本語が乱れている」といった俗流の国語論として見做してはならない。これは、「現地語」を世界の中心文化に引けを取らない「普遍語」の地位にまで引き上げようとした明治以来の気概が消え失せて、日本語がまた俗物的な「現地語」へと退化していることの現れなのだ。
世界に通用する文化を日本から生み出す必要もない、日本人の間だけで通用し、ウケていればそれでいい。そうした精神的退化の一つの現れだろう。
こうした文化的退化は、言語の分野だけに止まらない。
世界に通用する普遍文化を担おうという気概の消えたところからは、文化の「現地語」化、つまりは、俗物化がより一層進むことになる。
日本人がみな(坂口)安吾のように、いくら文化財など破壊しても「我々は…日本を見失うはずはない」と思っているうちに、日本の都市の風景はどうなっていったか。建築にかんしての法律といえば安全基準以外にないまま、建坪率と容積率の最大化を求める市場の力の前に、古い建物はことごとく壊され、その代わりに、てんでばらばらな高さと色と形をしたビルディングと、安普請のワンルーム・マンションと、不揃いのミニ開発の建売住宅と、曲がりくねったコンクリートの道と、理不尽に交差する高架線と、人が通らない侘しい歩道橋と、蜘蛛の巣のように空を覆う電線だらけの、何とも申し上げようのない醜い空間になってしまった。散歩する度の怒りと悲しみと不快。
法隆寺が残っているのは喜ぶべきことだが、私たちふつうの日本人の生活に関係あるのは、ふつうの町並みである。
今の日本では、むしろ日本語が文化の最後の砦となっていて、その他の日本文化は絶望的なほど退廃している。もちろん、ここで言う日本の文化というのは、一般の人々にとっての日常の文化のことだ。街並み、建築、衣服、文学、映画、食事、年間行事、地域文化。。。そういったあらゆるものが商業主義のなかで安易な消費材と化している。
日本の文化は、今や内側に引きこもり、狭い身内の世界で通用すればそれでよいという卑俗な「現地語」の地位にまで落ちていっている。世界性を見失った、身内ウケすればそれでいいという俗流文化の氾濫。。。
日本のその他の多くの文化は、卑俗な現地語へと堕しているのに、どうして、日本語だけがいつまでも大丈夫だと言い切れるのだろうか。
私には、著者の抱える不安が決して杞憂だとは思えないのだ。。。
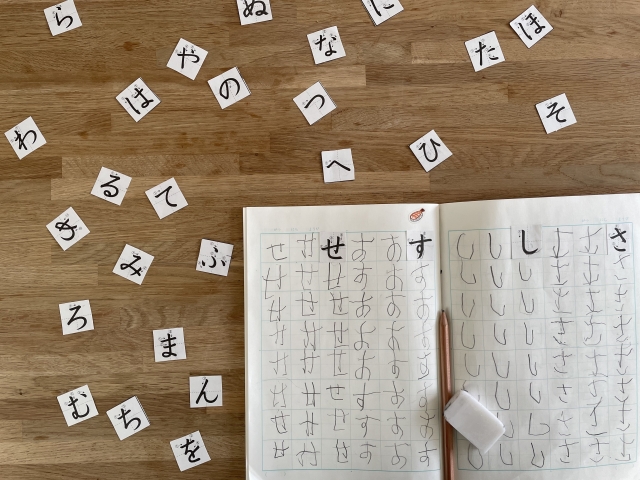



コメント