ソクラテス年表
| 年代(紀元前) | 出来事 | 補足 |
|---|---|---|
| 470年頃 | アテナイに誕生 | 父ソフロニスコス(石工)、母フェナレテ(助産師)の子として生まれる。 |
| 455〜450年頃 | 青年期 | 彫刻家として活動したとされる。教育は主に当時のアテナイの伝統的教養(音楽・体育・詩)による。 |
| 約450〜440年代 | 哲学への関心 | アナクサゴラスやソフィストなどの思想に触れ、自然哲学から倫理的問題へ関心を移す。 |
| 432年 | ペロポネソス戦争開始前後にポティダイア遠征に従軍 | アルキビアデスらとともに出陣、勇敢さで知られる。 |
| 424年 | デリオンの戦いに従軍 | 戦場でアルキビアデスを救出したとの逸話が残る。 |
| 422年 | アンフィポリス遠征に従軍 | 三度の軍務経験を通じ、市民としての義務を果たす。 |
| 420〜410年代 | 市場や公共の場で哲学的対話を行う | 若者や市民に問いかけ、徳・正義・知識の本質を探る。 |
| 406年 | アルギヌサイ海戦後の裁判で参事役(プリュタニス)として投票 | 不法な裁判手続きに反対票を投じ、少数派に留まる。 |
| 404年 | 三十人政権下で不当命令を拒否 | レオンの逮捕命令を拒否し、自宅に戻る(危険を伴う勇気の行動)。 |
| 399年 | 不敬と青年堕落の罪で告発される | メレトス、アニュトス、リュコンらが告発。陪審の多数決で有罪。 |
| 同年 | 毒杯(ドクニコン)を飲んで死去 | 監獄で弟子たちと最後の対話を交わした後、平静に死を迎える。 |
補足
- 生年・青年期の活動は確定的史料が少なく、年代は推定。
- 軍務経験や裁判での行動は、クセノポンやプラトンの記述から再構成される。
ソクラテスの生涯とその歴史的背景
- 黄金期から没落期までを生きた
ソクラテスはペリクレス期の栄華と、ペロポネソス戦争による衰退の両方を体験。 - 民主政と法の関係
彼の行動は、民主政の変質や衆愚化への批判と、法の尊重という二面性をもつ。 - 裁判の背景
戦争敗北後のアテナイは、異端的思想への寛容度が低下。政治的スケープゴートの要素もあった。
プラトン年表
| 年代(紀元前) | 出来事 | 補足 |
|---|---|---|
| 427年頃 | アテナイに誕生 | 名門貴族の家系。父アリストンはコドロス王の末裔、母ペリクティオネはソロンの血筋と伝えられる。 |
| 409〜404年頃 | 青年期 | 詩作や演劇に興味を持つが、やがて哲学に傾倒。ソクラテスの弟子となる。 |
| 404年 | 三十人政権成立 | 親族クリティアスが支配層に加わるが、暴政に失望。政治への直接関与を避ける。 |
| 399年 | 師ソクラテスの死 | 弁明や裁判を目撃し、哲学的使命感を強く抱く。 |
| 399〜387年頃 | 放浪と学び | メガラ、キュレネ、エジプト、南イタリア(ピタゴラス派)などを巡る。 |
| 387年頃 | アカデメイア創設 | アテナイ郊外アカデメイアの聖域に哲学学校を開く。西洋最古の高等教育機関とされる。 |
| 367年 | シラクサ遠征(第1回) | ディオニュシオス2世の教育を依頼されるが、政治的失敗に終わる。 |
| 361年 | シラクサ遠征(第2回) | 再び政治改革に関わるが、失敗。帰国後は執筆と教育に専念。 |
| 360〜350年代 | 主要対話篇の執筆 | 『国家』『ティマイオス』『法律』などを完成。哲学体系を形成。 |
| 347年 | 死去 | アテナイで没。弟子のスペウシポスがアカデメイアを継承。 |
プラトンの生涯とその歴史的背景
- 生年は紀元前428年説もある。
- シラクサ遠征は政治理想を実現しようとした試みだったが、現実政治の壁に阻まれた。
- アカデメイアは約900年間続き、中世ヨーロッパにも思想的影響を与えた。
プラトン著作年表(推定)
| 年代(紀元前) | 区分 | 代表作 | 内容・特徴 |
|---|---|---|---|
| 399〜390年頃 | 初期対話篇 | 『ソクラテスの弁明』 『クリトン』 『ラケス』 『エウテュプロン』 『プロタゴラス』など | 師ソクラテスの人物像・問答法を記録。徳・正義の定義を探るが結論は未確定。ソクラテスの精神的遺産を伝える。 |
| 390〜385年頃 | 『ゴルギアス』 『メノン』 | 修辞術批判や「徳は教えられるか」論争などを扱う。理念論(イデア論)への伏線が見られる。 | |
| 385〜370年頃 | 中期対話篇 | 『饗宴』 『パイドン』 『国家』 『クラティロス』 『パイドロス』 | イデア論を本格的に展開。魂の不死、愛(エロース)の哲学、正義の理想国家論などが展開される。文体的にも成熟。 |
| 370〜360年頃 | 『テアイテトス』 『パルメニデス』 『ソフィスト』 『政治家』 | 認識論・存在論の精緻化。イデア論の批判的再検討。 | |
| 360〜350年頃 | 後期対話篇 | 『ティマイオス』 『クリティアス』 『フィレボス』 『法律』 | 宇宙論、自然哲学、倫理学、法学へ関心が広がる。『法律』では哲人王より現実的な国家制度を構想。 |
| 未完作 | 『ヘルモクラテス』 | 『ティマイオス』『クリティアス』の続編予定だったが、未完成のまま終わる。 |
補足
- 初期対話篇はほぼ全てソクラテスを主人公とし、歴史的ソクラテス像に近いとされる。
- 中期対話篇でプラトン独自の哲学(特にイデア論)が明確化。
- 後期対話篇は対話の構造が複雑になり、ソクラテス以外の語り手や議論形式が増える。
- 成立順は学術的にも完全な一致はなく、語彙分析・文体研究などから推定される。
偽書(真偽不明または部分的に疑われているもの)
アルキビアデスI
アルキビアデスII
ヒッパルコス
恋敵
テアゲス
クレイトポン
ミノス
エピノミス
書簡集(一部:13通のうち第七書簡、第八書簡を除く)
定義集
正しさについて
徳について
デモドコス
シシュポス
エリュクシアス
アクシオコス
アルキュオン
詩
ソクラテス・プラトンの時代背景
| 年代(紀元前) | ソクラテスの出来事 | プラトンの出来事 | アテナイ・ギリシア世界の動向 |
|---|---|---|---|
| 470年頃 | アテナイに誕生 | ― | ペルシア戦争後の繁栄期。デロス同盟を基盤にアテナイ帝国が拡大。 |
| 460〜450年代 | 青年期、石工や彫刻に従事。 | ― | ペリクレスが政界で台頭、民主政治と文化が黄金期に。 |
| 432年 | ポティダイア遠征に従軍。 | ― | スパルタとの緊張激化。戦争直前の外交摩擦。 |
| 431年 | 哲学活動を活発化。 | ― | ペロポネソス戦争開戦(アテナイ vs スパルタ)。 |
| 427年頃 | ― | アテナイに誕生(名門貴族の家系)。 | 戦争序盤。アテナイは海上優勢。 |
| 424年 | デリオンの戦いで勇敢な行動。 | 幼少期。 | 戦局膠着、同盟都市で反乱の動き。 |
| 422年 | アンフィポリス遠征。 | 幼少期〜少年期。 | クレオンとブラシダス戦死、和平機運高まる。 |
| 415年 | 市場で問答活動を続ける。 | 青年期、詩作や演劇に関心。 | シケリア遠征出発、のち大敗。国力低下へ。 |
| 406年 | アルギヌサイ海戦後の裁判で法の遵守を貫く。 | 20歳前後、政治や哲学に関心を持ち始める。 | アルギヌサイ勝利も政治混乱。民主政の不安定化。 |
| 404年 | 三十人政権下で不当命令を拒否。 | 親族(クリティアス)が三十人政権幹部、暴政に失望。政治参加を断念。 | アテナイ敗北。民主政崩壊し寡頭政成立、市民弾圧。 |
| 403年 | 民主政復活後も対話活動を続ける。 | 哲学へ傾倒、ソクラテスの弟子に。 | 民主政再建。内部分裂と不信が残る。 |
| 399年 | 不敬・青年堕落の罪で裁判。有罪、毒杯で死去。 | 師の裁判と死を目撃。哲学的使命感を固める。 | 戦後混乱期、思想的緊張と民主政防衛意識の高まり。 |
| 399〜387年頃 | ― | 放浪と学び。メガラ、キュレネ、エジプト、南イタリアなどを巡る。 | ギリシア諸都市、スパルタ覇権期。のちテーベが台頭。 |
| 387年頃 | ― | アカデメイア創設。 | アテナイ文化復興期、哲学学校が長期的影響を持つ。 |
| 367年 | ― | シラクサ遠征(第1回)失敗。 | ディオニュシオス2世の政権下で政治改革試みるも挫折。 |
| 361年 | ― | シラクサ遠征(第2回)失敗、帰国。 | 西地中海でカルタゴ・シラクサ抗争。 |
| 360〜350年代 | ― | 『国家』『ティマイオス』『法律』など主要著作を完成。 | ギリシア世界はマケドニア台頭期へ。 |
| 347年 | ― | アテナイで死去。アカデメイアは弟子スペウシポスが継承。 | マケドニアのフィリッポス2世が勢力拡大。 |
補足
- 師弟関係の重なり:プラトンがソクラテスと接したのは主に紀元前407〜399年頃の約8〜10年間。
- 政治情勢の影響:両者の人生はアテナイの黄金期 → 戦争 → 敗北と混乱という急激な変化の中にあった。
- 哲学と政治の交錯:ソクラテスの裁判は、プラトンの「哲人王」構想やアカデメイア設立に直結。
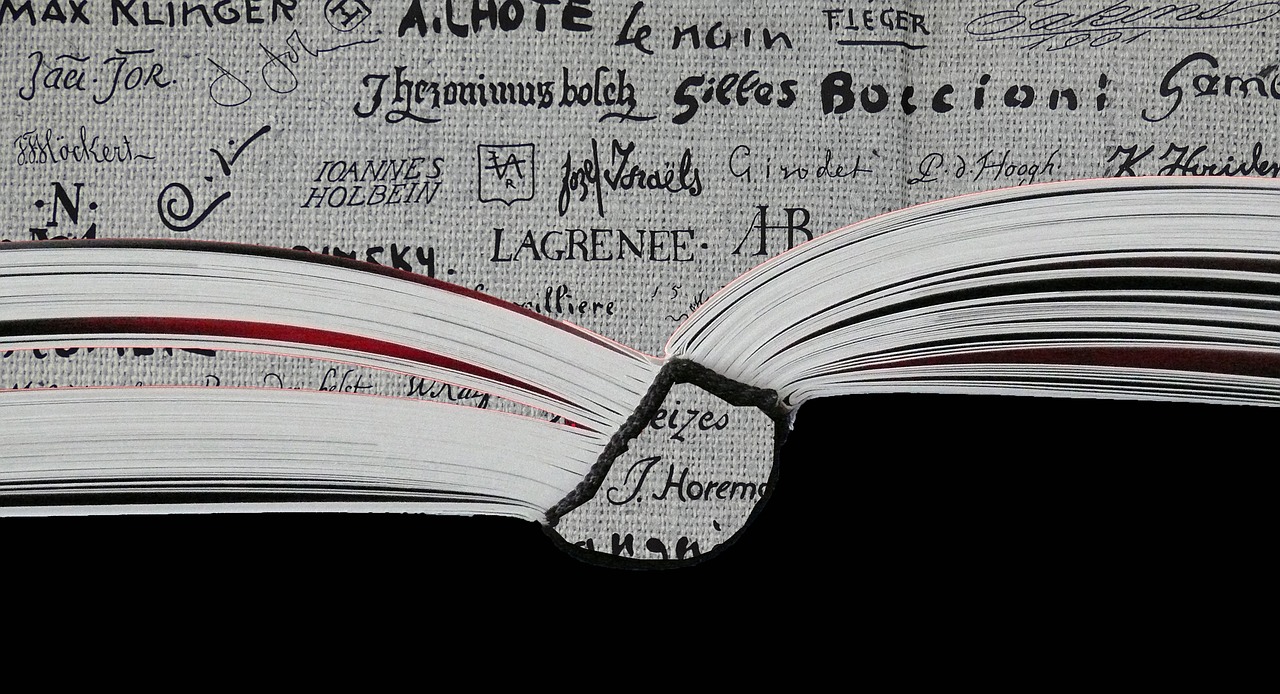


コメント