井伏鱒二『おんなごころ』(1949)
太宰が私に対して旧知の煩わしさを覚えていたことを私も知っていた。敗戦後の太宰は、外見だけのことであるが、まるきり人違いがしているようであった。私だけでなく、以前からの親しい友人たちにも、たいていの旧知の煩わしさを感じているようだった。
太宰治とは旧知の仲であり、師弟関係でもあったにもかかわらず、みすみす太宰を死なせてしまった———
相手の女を太宰から遠ざけることはできなかったのか、そうした後悔とともに当時のことを回想した随想。
しかし、井伏鱒二がその女性と会ったの三度ほどでしかない。太宰がその女の下宿部屋を仕事部屋に使っていた当時に、顔を合わせた程度だ。
「太宰さんは、今朝、わあわあ泣いて、まるで子供みたいなんですの。となり近所にも、あの泣声、きこえたでしょうよ。わあわあ泣くんですの。よっぽど、つらそうでしたわ」
某女は気がいら立っているようであった。
その前日、ある雑誌の編集部にいた青年が、その部屋へ太宰を訪ねてきて、睡眠薬を大量服用して自殺未遂を図ったのだという。
井伏氏は、この自殺未遂事件より、太宰のモルヒネ注射の悪癖が復活したのではないかを心配している。氏は、昭和11年(1936年)の11月に薬物中毒の治療入院を終えた太宰を武蔵野病院へ迎えに行っている。
しかし、この時、太宰とこの女性との仲がそれほど歪んだ悩ましいものとなっていることに気づいていなかった。
それに薄々と気付き始めたのは、太宰が家を出て、「千種」という小料理屋の二階を仕事部屋に使い始めた頃だ。千種のおかみさんの話では、その頃の太宰は、まるで憑きものがしたようになっていたという。
おかみさんの話では、まるで太宰は千種の二階に幽閉されていた。それも朝日新聞に連載する「グッド・バイ」の構想を、太宰がおかみさんたちに話して以来のことである。「グッド・バイ」は未完のまま終わったが、はじめの構想によると、主人公が数人の馴染みの女と別れて行く。これまでの生活にもグッド・バイして、ごく平凡な生活に入って行くところで終りになる。その筋書が女に知れてから、太宰は二階に閉じ込められ、一歩も千種から外に出してもらえなくなった。太宰が「ちょっと、うちに行って来る」と云うと、「あたし、いつでも青酸加里、持ってますよ」と威し文句を浴びせかける。小心な太宰は、たちまちすくんでしまう。
井伏氏は太宰の性質をよく知っていたはずだ。自我と自意識が非常に強いにもかかわらず、小心で繊細であるがゆえに、常に他者の意志に妥協し、果ては従属してしまう。一度でも性質の誤った人との関係を築いてしまったら、誰かの助けがなければ、自らは立ち直れないであろうことを。
よほど以前に太宰は、じゃじゃ馬馴らしの出来るような男こそ、自分の最も軽蔑するものだと云ったことがある。そのとき私は、「そうだろう。君は神経の末端まで、大事にするから」と同感の意を見せた。内心では、案外この太宰という青年は、じゃじゃ馬馴らしの出来る男よりも、斯道の達人として素質があると自負しているのではないかと思った。だが、私の判断はおぼつかない。私の買いかぶりであった。じゃじゃ馬の前で太宰は、ぐうの音も出せなかった。太宰から仕向けた故だと思われる。もともと彼は、人の増長を誘発させる言動に長じていた。そうして相手の増上慢に内心は顰蹙し、それでもまだ表面は我慢して、自虐性があると云ったりする。おもてには快楽をよそおい、内にはピエロの悲しみを覚える、というような意味のことを云っている。いつか私が太宰のその性癖を指摘して「それは煩手を労するというものだ」と云ったところ、「末世の故ですね。すべては社会の罪か」と云って、げらげらと笑った。
人との関りに絶望的なほどの精神的負担と罪悪感を覚えるような人間が、「おもてに友愛をよそおい、内には恨み骨髄」を抱えながら人との「おつきあい」を続けてきた結果が、行きずりの自殺だった。
太宰自身、やりきれない気持ちであったろう。これが仮に物語か小説の筋であるとしたら、もうとっくに太宰は「くだらねえ」と、その本を閉じていたことだろう。
太宰の苦悩を忖度し憐れむ著者。しかし、そこは井伏流。この随想自体を、後悔や懺悔の念でもなく、死別した太宰への哀惜や哀悼といった感傷的なものには全くさせていない。晩年の太宰が芝居に仕立てられ、そこで自分とおぼしき人物が勝手なセリフいうことに呆れ、腹を立てた逸話などを書いている。
太宰が亡くなりしばらくしてから、文藝春秋社に勤めていた石井桃子と偶然にも出会う。この女性は太宰が一時期思いを寄せていた人だという。井伏氏は、太宰が思いを寄せていたことをこの女性にそれとなく聞いてみる。
「いいえ、ちっとも。――でも、あたしだったら、太宰さんを死なせなかったでしょうよ」
女性に依存し、そして、「おんなごころ」に翻弄され、身を滅ぼした太宰。「おんなごころ」も人によって現れ方は、全く異なってくる———
違う女性との関係を築けていたら、全く異なる人生を歩んでいたに違いない。
新潮文庫『かきつばた・無心状』所収


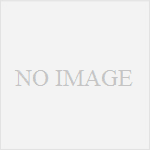
コメント