[adcode]
アリストテレス『詩学』(4c BC)
[adcode]
「詩」の体系的な把握
アリストテレスは、芸術の本質を「再現」(Mimesis)として捉えている。再現することは、自然を学ぶことであって、人間の本性に由来する。そして、再現されたものを鑑賞することに喜びを見出すのも人間の本性である。アリストテレスによれば、芸術の起源とその発展は、この人間の本性に由来する。
そして、さまざまな芸術は、その再現の仕方の違いとして表れる。
詩もまたそのうちのひとつである。
アリストテレスは、芸術をその再現の対象や方法、手段によって分類していく。ここからアリストテレス流の体系的な分類学が始まる。
詩は、韻律を持った言葉によって、人間の行為を再現した芸術だ。
古代文化では、現代のような散文、あるいは小説のような芸術は存在していなかったので、言葉で書き表されたものは、そのほとんどが韻を踏んでいる。その意味で、すべての文章が韻律をもっている。
そのなかでも人間の性質の再現を試みるものが、悲劇と喜劇と呼ばれる。
特に悲劇は、高貴な行為の再現であり、感情の浄化を目指すものだ。そして、歴史家による叙事詩とは異なり、個別の歴史ではなく、普遍的な事実を志向する。
当時は、悲劇も喜劇も「読まれる」ものではなく、「演じられる」ものだった。そのためアリストテレスの議論は、演劇における視覚的効果や、筋立ての技巧、修辞や言葉遣いの効果にまで及ぶ。
[adcode]
『詩学』の著作としての性格
この著作は、詩学というものを一つの芸術として位置付け、個別の作品をどのように評価していくか、ということに主眼がある。詩(演劇)を創作したり、論評したりする際に、どの点に着目すべきかという技巧的な話が、多く語られている。
思想的、哲学的な作品としては、面白みに欠けるが、筋立ての技巧に関する議論などは、詩作や小説の構成などに思いあぐねている人にとっては、今でも価値のあるものだろう。
三大悲劇詩人のひとり、エウリピデースが好んだ手法として有名な「機械仕掛けの神」(テオス・アポ・メーカネス、あるいはラテン語で、デウス・エクス・マーキナー)を愚策として、一刀両断に切り捨てるくだりなどは、読んでいて非常に興味深い。(第15章)
現代でも「夢オチ」のような作品は駄作の典型だろうが、そのような筋立てが古代から非難されていたと思うと面白い。
『詩学』は、もともと一つの著作として書かれたものではなく、講義のためのmemorandomを後世にまとめたものだ。そのため、詩というものの本質を掘り下げようとするようなものではなく、詩を芸術の一分野と位置付けたうえで、その基礎と技術論を教えるような内容になっている。
古代から、このような技巧に関する議論の積み重ねが基礎となって、演劇や小説、さらには現代の映画の発展にまで影響を与えているのだろう。
西欧における芸術創作の伝統的厚みを感じさせる作品。

[adcode]

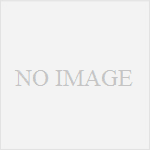
-e1615228993521.jpg)
コメント