ソクラテスの思想とその歴史的背景
『ソクラテスの弁明』において、ソクラテスは魂への配慮を最優先に掲げ、名誉や富といった世俗的価値を退け、神(ダイモーン)の声に従うことを人生の指針とした。そこにあるのは、個人の内面の徳を高めるための徹底した自己探求である。
ところが『クリトン』では一転し、彼は国家の制定した法に従うことの正しさを説き、死刑判決を受け入れる姿勢を示す。前者では個人の魂が、後者では世俗的な法が優先されている。この一見矛盾する二つの態度の意味を理解するためには、ソクラテスが生きたアテナイの歴史的背景──ペリクレス期の栄華と、ペロポネソス戦争による衰退、そして度重なる政変──を読み解く必要がある。
『クリトン』の概説
『クリトン』は、プラトンの初期対話篇の一つであり、『ソクラテスの弁明』の直後を舞台とする。死刑判決を受けたソクラテスが、アテナイの牢獄で刑の執行を待つなか、旧友クリトンが早朝に訪れるところから物語は始まる。クリトンは、処刑が近づいていることを告げ、友人や弟子たちの手配で逃亡が可能であると説得する。彼はまた、逃亡しなければ「仲間を助けずに死なせた」と人々に思われ、子どもたちを孤児にしてしまうと懸念を示す。
これに対してソクラテスは、「正しく生きることが何よりも重要であり、不正をもって不正に報いてはならない」と主張する。彼は、アテナイの法律を擬人化し、自らはこの都市で生まれ育ち、法の保護と恩恵を受けてきたため、暗黙の契約を結んでいると語る。この契約を破って逃亡すれば、法と都市全体を傷つけることになる、と結論づけ、死刑判決を受け入れる決意を固める。
この対話は短いながらも、「生きること」と「正しく生きること」の優先順位、個人と国家法の関係、そして社会契約の萌芽的思想といった重要なテーマを含んでおり、『弁明』との対比を通じてソクラテス思想の多面性を浮き彫りにしている。
変貌するアテナイの政治
1.ペリクレス期の栄華と市民意識の高揚
ソクラテス(紀元前470頃〜399)は、アテナイが古代ギリシア世界の頂点に立った時代に生まれた。ペリクレスの指導下、アテナイは強力な海軍とデロス同盟を背景に経済的繁栄と文化的黄金期を迎え、パルテノン神殿やアゴラの整備といった大規模建築、演劇・哲学・美術の発展が進んだ。
民主政は、成年男性市民全員が直接政治に参加する仕組みを整え、市民たちは都市国家への誇りと共同体意識を強く抱いていた。
若き日のソクラテスは、この成熟した民主政と豊かな公共生活の空気を吸い込み、議論や探究を通して徳を磨くことを当然の価値として体得していったと考えられる。
2.ペロポネソス戦争と民主政の変質
しかし紀元前431年、アテナイはスパルタを中心とするペロポネソス同盟と長期戦に突入する。戦争は27年間続き、都市の財政・人員・士気を徐々に削り取った。
戦中にはペストがアテナイを襲い、ペリクレス自身も命を落とす。後継の指導者たちは、しばしば短期的な民意に迎合し、戦略的失策やポピュリズム的な政策を繰り返した。
こうして民主政は「熟慮する市民の政治」から、「衆愚政治」への変質を遂げ、感情や一時的利益に流される集会政治が目立つようになる。
3.寡頭政の台頭と政変の連続
戦争末期には、民主政に不満を持つ富裕層や知識人を中心に寡頭政の樹立が試みられる。紀元前411年の「四百人政権」、紀元前404年の敗戦後の「三十人僭主政」がそれである。
特に「三十人僭主」はスパルタの支援を受け、民主派の粛清や財産没収を行い、アテナイ市民に深い分断と恐怖をもたらした。
ソクラテス自身もこの時期、僭主政から不正な命令を受けた際に従わず、政治権力の暴走に批判的立場をとったが、同時に暴力的混乱や報復の連鎖が都市を疲弊させる様子も目の当たりにしている。
4.ソクラテスの二面性の形成
こうした激動の中で、ソクラテスの政治的態度は二つの方向を持つようになった。
- 民主政の衆愚化や政治的不正への批判
- 民衆が感情に流され、指導者が迎合的で短絡的な判断をすることへの警戒。
- 無知や未熟な意見が政治を動かす危険性を、日々の対話を通じて鋭く指摘。
- 混乱を抑えるための法の尊重
- 度重なる政変と報復合戦の中で、法秩序が失われることの破壊力を痛感。
- 不正な命令には従わない一方で、基本的な法の枠組みを壊すことは共同体を根底から崩すと考えるようになった。
『クリトン』の歴史的意義
『クリトン』は、ソクラテスの思想における二面性のうち、特に「秩序の維持を重んじる態度」が色濃く表れた作品である。
牢獄からの逃亡が可能であったにもかかわらず、ソクラテスは「法との暗黙の契約を破ることは都市の基盤を壊すことになる」としてこれを拒否する。
この決断の背景には、民主政の混乱や寡頭政の暴政といった歴史的経験から、「法が崩れれば、残るのは力と報復だけになる」という切実な認識があったと考えられる。
こうした点から、ソクラテスは、プラトンの理想主義とは異なり、実践的かつ現実主義的な思想的立場を持っていたことが窺われる。
具体的には、ソクラテスの思想は、個人の良心や魂の探究を追求する革新的な側面と、社会秩序の維持を重んじる保守的な側面という、二つの相反する側面を共存させていた。
「個人の内面の良心」と「国家の法」が対立した場合でも、それを単なる矛盾として否定するのではなく、「魂への配慮」を基準にして何が正しいのかを問い続ける実践的な態度こそが、ソクラテスの思想的意義であると言えるだろう。
『クリトン』は単なる倫理的対話にとどまらず、ペロポネソス戦争後のアテナイが抱えていた政治的不安定と道徳的動揺を背景に読み解くべき作品である。
ソクラテスの法遵守の姿勢は、魂への配慮による市民的不服従の理念と対立しつつも、秩序の重要性を説く点では、戦乱と政変を経験した都市国家の切実な現実を反映している。
つまり、『クリトン』は歴史的背景を理解しなければ、その核心的な重みが見えにくくなる作品でもあるのだ。
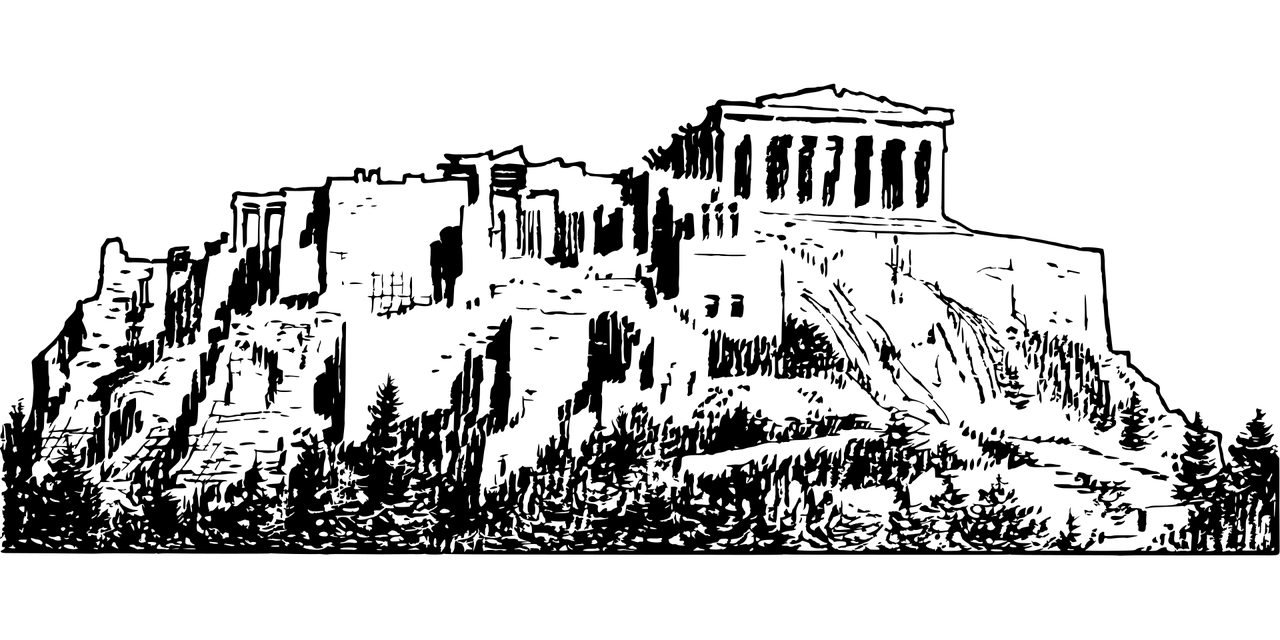


コメント