【概略】進化論の進化史(全3回)第1回
19世紀の歴史哲学と進化論の誕生
歴史をめぐる問いの深化:19世紀思想の出発点
19世紀のヨーロッパでは、「歴史」とは何か、歴史の変化に理由はあるのか、といった根源的な問いが、思想家や哲学者たちの主要な関心事となっていた。ここでの「歴史」とは、単なる過去の出来事の記録ではなく、社会や人間精神がどのように発展・変化してきたかを探求する哲学的問題として捉えられていた。
この時代には、歴史を偶発的な出来事の集積ではなく、一定の法則や発展の方向性をもつ過程として理解しようとする潮流が生まれた。こうした歴史観は、「歴史に普遍的な法則は存在するのか」「人間社会に進歩はあるのか」といった問いを中心に据えた思索へとつながっていく。
歴史における法則の探究:四つの思想的アプローチ
この知的潮流の中で、以下のような代表的思想家たちが、それぞれ異なる観点から「歴史に内在する法則性」を提示した。
- オーギュスト・コント(フランス)
人間の知性と社会の発展を、「神学的段階 → 形而上学的段階 → 実証的段階」という三段階の法則で説明した。歴史を科学的に理解しようとする実証主義の立場から、社会進歩の必然性を主張した。 - ハーバート・スペンサー(イギリス)
社会や文化が単純な状態から複雑な状態へと発展するという社会進化論を提唱。生物学における進化の概念を社会理論に応用し、社会変化を自然的過程と見なした。 - G.W.F.ヘーゲル(ドイツ)
歴史を理性(ロゴス)の自己展開ととらえ、矛盾と対立の運動である弁証法により、世界史全体を解釈した。歴史の背後にある「理念」の発展を重視する観念論的立場である。 - カール・マルクス
ヘーゲルの弁証法を唯物論的に転倒させ、歴史を生産様式の変化とそれに伴う階級闘争の連続と見る史的唯物論を展開。歴史における物質的基盤の決定的役割を強調した。
これらの思想は、「歴史には内的な必然性があるのか」「社会の進歩に必然性はあるのか」といった問いに答えるべく形成されたものであり、「歴史哲学(Philosophy of History)」という学問分野の確立に決定的な影響を与えた。
歴史としての自然:進化論という新たな視点
このような「歴史を法則的に理解しようとする思考」は、生物学の分野にも波及した。すなわち、生物そのものを静的・不変の存在とみなすのではなく、時間の中で変化しうる歴史的存在ととらえる視点が生まれたのである。
この視点から登場したのが進化論である。進化論は、生物を神が創造した不変の「種」とする創造論に代わって、生物が環境や時間とともに変化・分化していく存在であるという新たな自然観を提示した。
前史としての創造論とその揺らぎ
18世紀まで、西欧では「生物は神により創造され、各種は不変である」とする創造論的世界観が支配的であった。しかし、19世紀に入ると、化石の発見や地質学的研究の進展により、地球上にはかつて存在したが現在はいない生物種があることが明らかになり、生物にも「歴史」があるという考え方が徐々に受け入れられるようになった。
19世紀のヨーロッパ思想は、「歴史とは単なる過去の記録ではなく、法則的に進展する現象である」という観点から、人間社会と自然界の両方を歴史的に捉える視点を確立した。この視点が、歴史哲学と進化論という二つの領域で、「変化には必然があるのか」という問いを追究する知的営為へと結実していったのである。
初期進化論の試み:ラマルクの用不用説
進化という考え方を体系的に初めて提示した思想家が、ジャン=バティスト・ラマルク(フランス)である。彼は1809年の著書『動物哲学』において、以下のような理論を打ち立てた。
- 生物は環境や行動に応じて器官を多用または使用しなくなる
- その結果、器官は発達または退化し、後天的な形質が形成される(用不用説)
- これらの獲得形質は子孫に遺伝する(獲得形質の遺伝)
ラマルクはこの理論にもとづき、生物は自然発生し、単純な形態から複雑なものへと目的をもって進化すると主張した。彼の進化観は創造論を否定するものであったが、進化に方向性や目的を仮定する点では、なお前近代的要素を残していた。それでも、彼が進化という観念を明確に理論化したことは、後世の生物学にとって画期的な意義をもつ。
進化論の科学化:ダーウィンの自然選択説
ラマルクの理論は大胆ではあったが、実証的根拠に乏しかった。その後、チャールズ・ダーウィンが1859年に『種の起源』を発表し、自然選択(自然淘汰)というメカニズムを提示することで、進化論に科学的基盤を与えることに成功した。
ダーウィン以降、進化は証拠に基づく科学的探究の対象となり、生物の変化に関する法則性や原因を明らかにする研究が飛躍的に発展していく。こうして生物学もまた、「歴史を法則的に理解する」という19世紀的思考に貫かれた学問分野となっていったのである。
チャールズ・ダーウィンと自然選択説(1859)
『種の起源』(1859年)においてチャールズ・ダーウィンが提唱した「自然選択説(Natural Selection)」は、現代進化論の中核をなす理論である。
この理論の要点は以下の通りである。
- 資源の有限性と生存競争
生物が生き延び、繁殖するために必要な資源(食料、空間など)は有限であり、すべての個体が生存・繁殖できるほど十分ではない。したがって、自然界では常に生存をめぐる競争(闘争)が生じる。 - 個体差と適応
同種の個体間にもわずかな違い(形質の変異)が存在する。その中には、環境において有利に働く変異も含まれており、こうした形質を持つ個体はより多くの子孫を残す可能性が高い。 - 自然選択(自然淘汰)のメカニズム
有利な形質が次世代に伝わりやすくなることで、世代を経てその形質が集団内に広がっていく。この過程が自然選択(Natural Selection)であり、種全体が時間とともに変化(進化)していく原動力となる。
ダーウィンは、生物の進化を方向性や目的を持つ過程ではなく、偶然的変異と環境適応の結果が積み重なったものとみなし、目的論的解釈(生物が進化の最終目的に向かっているという考え方)を否定した。
遺伝学の誕生と進化論の補完
ダーウィンの自然選択説は、生物の変化を説明する説得力を持っていたが、形質がどのように子孫に伝えられるのかという「遺伝の仕組み」が不明であった。これを補完したのが、遺伝学の発展である。
グレゴール・ヨハン・メンデルと遺伝の法則(1865)
メンデルはエンドウマメを用いた実験により、形質が一定の規則に従って子に伝わること(遺伝)を示した。
メンデルの提唱した法則:
- 分離の法則:親の持つ対立形質は、生殖細胞形成時に分離され、子に独立して伝わる。
- 独立の法則:異なる形質の遺伝は互いに独立して行われる。
メンデルは遺伝形質を制御する「因子(現在でいう遺伝子)」の存在を仮定し、後天的に獲得された形質(ラマルク説)が遺伝するという考えを否定した。
メンデルの業績は当初ほとんど注目されなかったが、20世紀初頭に再発見され、ダーウィンの理論と結びついて現代進化論の基盤となった(新ダーウィニズム/現代進化論的総合(統合説))。
ウォルター・サットンと染色体説(1902)
サットンは、メンデルの「遺伝因子」が染色体上に存在するという仮説を提示。
減数分裂を観察し、遺伝情報が親から子に伝えられる仕組みが染色体の挙動と一致することを指摘した。
これにより、遺伝子=染色体上の単位という理解が確立され、遺伝学は急速に進展することとなる。
進化論の確立と現代生物学への道
チャールズ・ダーウィンの自然選択説は、生物が環境との相互作用によって変化するという動的な自然観を提示したが、遺伝のメカニズムが不明であったために説明には限界があった。その後、メンデルの遺伝法則やサットンの染色体説によって、進化における「変化の材料(遺伝的変異)」と「継承の仕組み」が科学的に説明可能となり、進化論は確固たる自然科学理論として成立するに至った。
これらの理論的補完を通じて、20世紀半ばには分子生物学を取り込んだ現代進化論(総合説/統合説)が形成され、生物の進化は遺伝子レベルで理解される時代に入った。
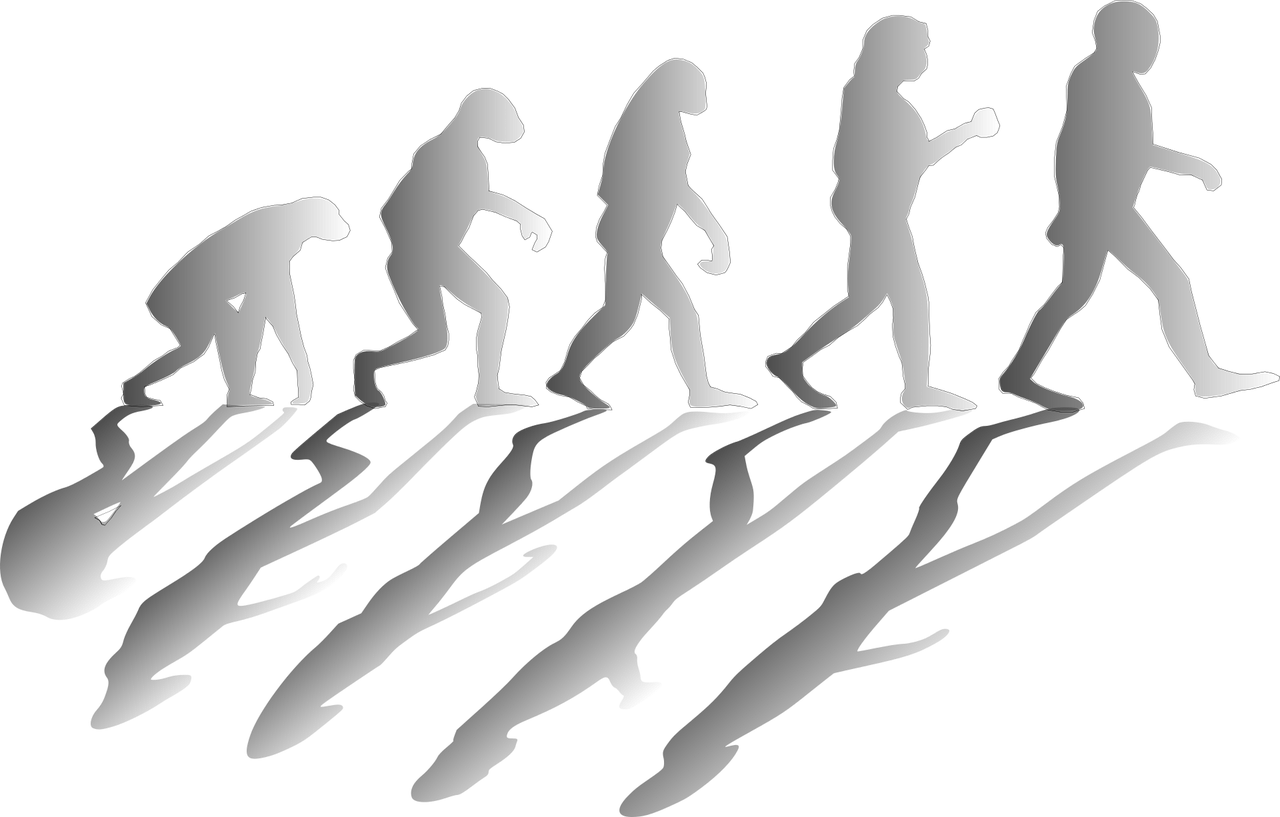



コメント