プラトン『メノン』(385 BC?)
対話から想起へ
『メノン』は、プラトン初期対話篇の作品の中で、最も遅く書かれたものの一つと見られている。初期作と中期作の両方の特徴を持ち、中期への橋渡し的な位置付けにある。
本対話篇の主題は、「徳(アレテー)は教えることができるのか」という問いであり、これは初期対話篇『プロタゴラス』と同じ問題をめぐって議論が展開される。
『プロタゴラス』では、若きソクラテスが老練なソフィスト・プロタゴラスと激しく論争を交わすが、『メノン』ではその構図が逆転する。晩年のソクラテスが、若く美しい青年メノンの問いに応じるかたちで、対話が進行するのである。
対話の舞台は、紀元前402年頃のアテネ。ソクラテスは当時60代後半で、死刑判決を受ける約3年前にあたる。この『メノン』におけるソクラテスは、もはや論争者ではなく、若者を導く教師的存在として描かれている。
では、なぜプラトンは、『プロタゴラス』と同じ主題を、あえて再び、しかも晩年のソクラテスを通して描いたのだろうか。
おそらくそれは、プラトン自身が自らの哲学的思想を展開するにあたり、「導く者」としてのソクラテス像を必要としたからではないか。この時期のプラトンは、ソクラテス的対話法から脱却し、独自の哲学体系を構築しつつあったと考えられる。彼は、教師としてのソクラテスの姿に仮託することで、自身の新たな思想を語らせようとしたのである。
『メノン』の執筆は、プラトンが紀元前388年にシケリアから帰国した後と推測される。シケリア滞在中、彼はピュタゴラス派の影響を強く受けたとされるが、そこからプラトンは観念論的な存在理解を学び取った。そして、それに基づいて展開されるのが、「学ぶこととは思い出すことである」という「想起説(アナムネーシス)」である。
プラトンは、『プロタゴラス』でソクラテスが提示した徳(アレテー)を巡る問いに対して、この想起説によって答えることができると確信しつつあったはずだ。そして、その説を説く役割として、若者を導く晩年のソクラテスの口を借りたのだろう。
こうして『メノン』では、ソクラテスによる対話的探究と、プラトンによる観念論的思索が併存する。極めて短い対話でありながら、二つの観点から議論が展開している。
その結果、異なる論理が相互に展開し、議論の結論が最初の問いへと帰っていくという複雑な構造を取っていて、読者には読みづらい印象を与えている。
『メノン』を読み解く鍵は、ソクラテスの対話的手法が目指すものと、プラトンの想起説が証明しようとしているものとを明確に分けて考えていくことにあるだろう。
ソクラテスの対話的方法論──「無知の知」に基づく哲学的探究
ソクラテスの哲学的方法は、一般に「無知の知」として知られている。この言葉が示すように、彼の立場は、言葉の定義や用法が曖昧なまま議論を進めることを厳しく戒め、まず自分が何も知らないことを自覚するところから思索を始めようとする態度にある。
『メノン』第2章の冒頭で、若きメノンはソクラテスに対して次のように語っている。
ソクラテス、わたしはあなたにお会いする以前から、あなたは自分で難問に悩み、他人をも難問に悩ますことしか、しない人だという話を聞いていました。現にいまも、あくまでわたし個人の印象ですが、あなたはわたしに、魔法をかけ魔術で欺いて、文字通り呪文をかけてしまいました。それでわたしは、こんなにもたくさんの難問に取り囲まれて、途方にくれています。
この発言からも明らかなように、ソクラテスの対話法は、相手の意見の矛盾を明らかにすることで、彼ら自身が言葉の意味や概念の本質について曖昧な理解しか持っていないことに気づかせるものである。その目的は、相手に「自分は知らないのだ」という無知の自覚を促し、そこから本当の思索を始めさせることにあった。
このように、ソクラテスは単なる批判者でも詭弁家でもなく、問いを通じて相手を導く哲学的案内人(メイエウティクス=助産術)として振る舞っている。彼の真骨頂は、教えを与えるのではなく、相手が自ら思索を深めていくよう促すその姿勢にある。
『メノン』においても、ソクラテスは「徳(アレテー)は教えることができるのか?」という問いにすぐには答えず、まず「そもそも徳とは何か」という問いを根本から繰り返し問い直す。定義が不明瞭なままでは、どのような議論も成立しないという彼の哲学的立場が、ここにも一貫して貫かれている。
プラトンの想起説──「知の探究」への転換
一方で、プラトンの思想には、ソクラテスのいう「無知の知」が入り込む余地はほとんどない。プラトンにとって人間の魂は、生まれる以前からすでに真理を知っている存在であり、学ぶという行為は、忘れていた知識を思い出す「想起(アナムネーシス)」にすぎないとされる。
つまり、人が何かを「知らない」と感じているのは、魂がそれを一時的に忘れているだけであり、適切な導きがあれば、正しい知識に再び到達することができる──これがプラトンの確信である。論理的に正しい順序をたどれば、人は他者の力を借りることなく、自らの力で真理に到達できるという前提に立っている。
その思想を象徴的に示しているのが、『メノン』に登場する、ソクラテスとメノンの従者の少年との対話である。
ソクラテスは、少年に一つの正方形を示し、その2倍の面積になる正方形を求めるように問う。少年は、ソクラテスの説明に従って、元の正方形の対角線を一辺とする正方形から2倍の面積の正方形が求められることを「知る」。
少年は、この時、自らが今まで知らなかったことを知ったのである。自らの「無知」を自覚したのではなく、自らの「知」を自覚したのだ。プラトンにとってこの場面は、人間の魂があらかじめ真理を内に宿していることの実証であった。
この幾何学の例えは、人間の知性の本質をきわめて鮮やかに描き出している。これは「生得的な論理的思考能力」の証明と見ることもできるだろう。プラトンはこの考えを「想起説」として理論化し、ソクラテスの対話的探究を超えて、人間の知の本質とその獲得の仕方に新たな地平を開こうとした。
この想起説を前提として、プラトンはソクラテスの口を借り、さらに次のような思想を語らせている。すなわち、人は「知らない」と考えていることについても探究すべきであること、そしてそのためには「仮説(ヒュポテシス)」を立て、それに基づいて論を進めることが有効であるという点である。
これは、推論によって仮説を導き出し、その検証を通じて真理に近づこうとする、きわめて合理的な発想である。
結論としてのアポリア
さて、そもそもの問いであった「徳(アレテー)は教えることができるのか」という問題に対して、最終的に二人の対話はどのような結論に至ったのだろうか。
ここで議論されている「徳(ἀρετή アレテー)」とは、古代ギリシアにおいて、重要な概念で、「社会的に称賛される個人の優れた資質」という意味である。以下のWikipediaの解説は非常にわかりやすい。
Arete is a concept in ancient Greek thought that refers to “excellence” of any kind—especially a person or thing’s “full realization of potential or inherent function.”The term may also refer to excellence in “moral virtue.”
Arete – Wikipedia
つまり、徳として現れる個人の優れた「資質」や「才能」を教えることができるのかが、ここでは問われているのだ。
この問いに対して、ソクラテスは、まず仮説を立てて考察することの重要性を、幾何学者が図形に補助線を引いて問題を解く作業にたとえて説明する。
彼は最初に、「徳は有益なものであるべきだ」という仮説から出発し、徳が有益であるためには知性(フロネーシス)を伴っていなければならない、ゆえに徳とは知性であり、したがって教えることが可能である──という推論を展開する。
だが、ここでソクラテスは、アニュトスとの議論から、優れたアレテーを持つものが、アレテーを教えることに成功することがないという反証を提示する。
こうして問題は、再び解決不能な状態──すなわちアポリア(難問)へと帰着する。ソクラテスは、仮説と反証の循環を通じて、問いを再び出発点に戻し、言葉の厳密な意味から問い直すことの必要性を説く。
「徳(アレテー)は教えることができるのか」という当初の問いは、結論に至らないまま、問いだけが循環して、対話の終焉を迎えることになった。こうして『メノン』は、初期対話篇の形式を踏襲して、問いを読者に投げかかたまま終わる。
この対話篇には、ソクラテスの対話的方法とプラトンの理論的思考──すなわち、「言葉の意味と定義を徹底して問い直す方法」と「想起と仮説による演繹的な探究」という、二つの思考様式が併存している。
この時点でのプラトンは、まだ想起説のみによってすべての知識を説明しようとしているわけではない。むしろ模索の途上にある。『メノン』は、プラトンがソクラテスの遺産を引き継ぎながら、自らの思想体系を形成していく出発点として位置付けられる。
『メノン』は、プラトンの思想形成を追う上でも、初期と中期の思想を結び付ける上でも極めて需要な作品だ。そして同時にこの対話篇は、「教育は可能か」「知はいかにして獲得されるのか」といった、人間の本質を巡る問いを私たちに投げかける。『メノン』は、知性と学びの本質を問い続ける哲学の原点であり、プラトン哲学の転換点を刻む一冊なのである。
引用
プラトン『メノン』(光文社古典新訳文庫)より
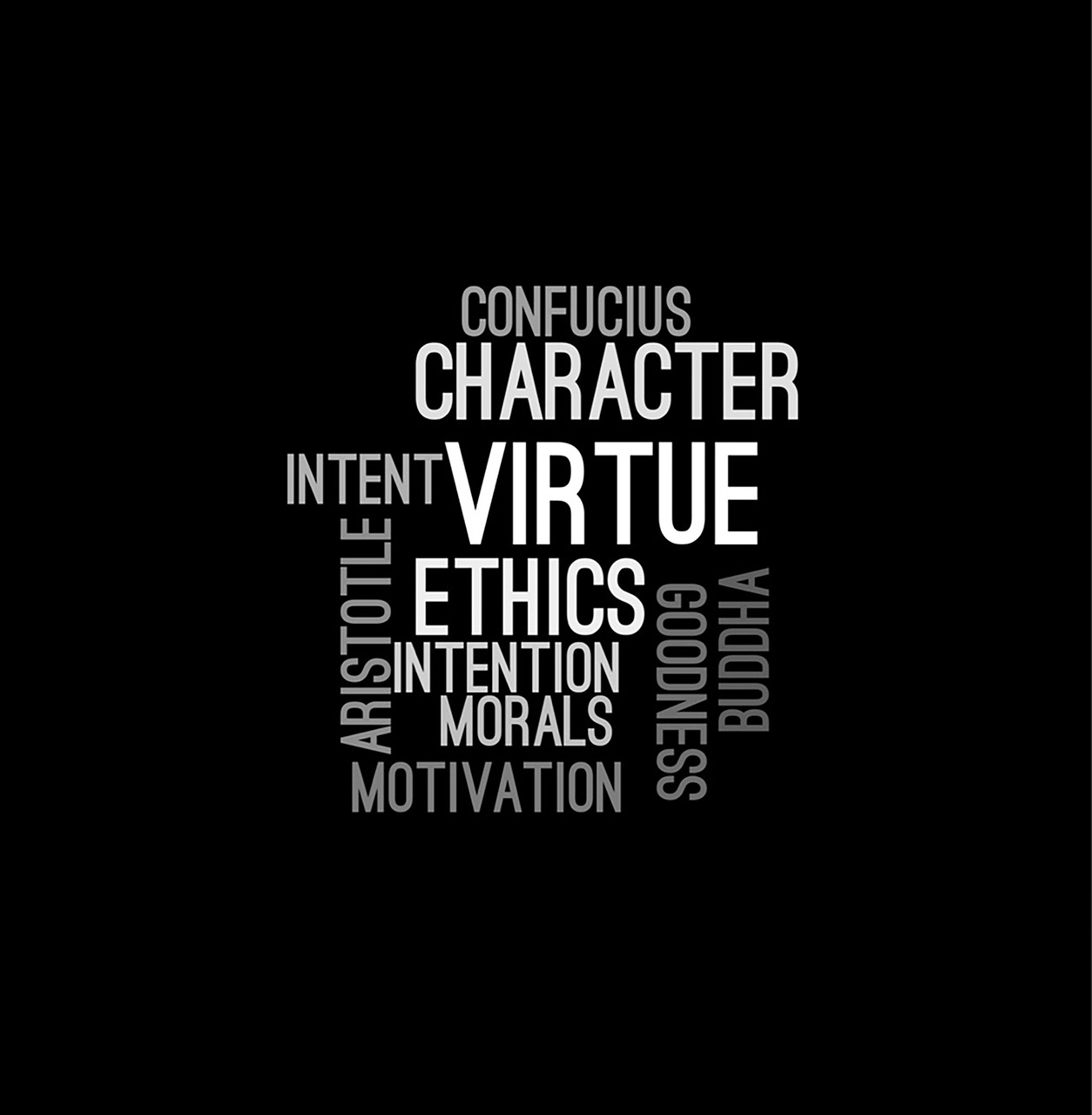




コメント