プラトン『クレイトポン』
『クレイトポン』の真偽問題
古代ローマ帝国の第2代皇帝ティベリウスの廷臣であったトラシュロスは、プラトン全集を編纂し、これが後世のプラトン著作編集の基礎となった。すでに帝政ローマ期には、プラトン名義の真偽不明な著作が多数流布しており、トラシュロスはその中から、真作と見なされる36篇を選定・整理した。このなかに『クレイトポン』も含まれている。
しかし19世紀、ドイツの神学者・文献学者シュライアマハーが『クレイトポン』の真贋に疑義を呈し、それ以降、本作を偽作と見なす見解が有力となった。
実際、本書の構成は他のプラトン作品とは異なり、ソクラテスがクレイトポンから論難されたまま反論することなく終わっており、不自然な印象を与える。一方で、作品の大部分が失われ、現在伝わるのはその一部にすぎない可能性も否定できない。ただし、それを裏付ける証拠は存在せず、この著作の真偽問題は、今後も決定的に解明されることはないだろう。
何が「徳」と呼べるのか?
真偽の問題は、プラトンの思想を明らかにするうえで重要ではあるが、以下ではテキストそれ自体が持つ哲学的価値により重点を置いて考察していきたい。
本作『クレイトポン』の副題は「徳の勧め」であり、徳を他者に促すことの意義が語られている。しかし、この対話編での本質的な問いは、「徳はどのように習得され、いかに実践されうるのか」という点にある。
クレイトポンはこの問いを明確に提示し、ソクラテスの主張に対して根本的な疑問を投げかける。それは単なる個別の論点にとどまらず、ソクラテス哲学全体に対する本質的な批判となっている。
全生涯にわたる我々の仕事というのは、まだ徳を目指すように促されていないものたちを促すことであり、その者たちはその者たちでまた別の者たちを促すことなのか、それもと我々は、人は徳へと促すこと自体は行うべきであることに同意した上で、その後になすべきことについて、『で、それから?』と、ソクラテスに対しても、お互い同士の間でも問わなければならないのでしょうか。我々は正義に関して、どようにその習得に着手すべきだと主張するのでしょうか。
このクレイトポンの発言に表れているのは、「徳を勧める」ことと、「徳を教え、実践する」ことのあいだにある深い溝への問いである。
クレイトポンは、ソクラテスの議論を否定しているわけではない。彼は次のようなソクラテスの教えを肯定している──「誰も自ら進んで悪をなす者はいない」「不正を犯すのは、魂への配慮を欠いているからである」「アレテー(徳・特質)は教えることができる」「ゆえに、自らの魂への配慮を他者にも促さねばならない」。これらは、当時もっとも広く知られ、一般にソクラテスの思想として受け入れられていた教えである。
クレイトポンはこれらの点には賛同するが、それでもなお疑問を呈する。「では、実際に徳とはどのようにして身につくのか?そしてそれは、どのような具体的行為として表れるのか?」──この問いに対して、ソクラテスからは明確な答えが返ってこない。
ソクラテスとの議論の中で対話者は、正義の具体的な定義を問われ、最終的には自分が何も知らないことを自覚させられる。それは、ソクラテス自身にとってさえも同じなのだ。「無知の知」を自覚することで、新たな問いへと自らを駆り立てる契機となる。
この思考法は、対話を通じて思索を深化させるという点で哲学的には意義深い。しかし一方で、明確な結論を避けるソクラテスの態度は、無思慮な人々には単なる「はぐらかし」として映る。実際、クレイトポンは、ソクラテスは正義について知らないのか、それとも知っていて教えようとしないのかのどちらかであると非難する。
このような批判的視点は、ソクラテスの議論手法を「空とぼけ」として捉えるアテナイ市民の間でも広く共有されていた。
クレイトポンの批判の核心は次の通りである。ソクラテスは人々に徳や知を求めるよう促すことはできても、それが何であるかを具体的に教えることはできないのではないか──これはソクラテスの哲学に対する根源的な問題提起である。
そしてこの批判は、ソクラテスが裁判にかけられた際、民衆から向けられた非難とも本質的に通じるものであった。
ソクラテスの実際の姿?
この作品で描かれているソクラテスの姿というのは、ソクラテスの実態に非常に近いものだったのではないだろうか。
ソクラテスは、「無知の知」を自覚させることをその哲学の出発点とした人物である。彼は、相手の思い込みを対話によって解体し、真の知識への問いを促したが、具体的な答えを提示することはなかった。
それに対し、弟子であるプラトンは、「では、どうすれば正しい知に到達できるのか」という問いを自らの課題とし、これに対する答えとして「想起説」や「イデア論」を構築していった。しかし、ソクラテスがそれと同じ考えをどれほど抱いていたかは不確かだ。プラトンの哲学とソクラテスの思想は厳密には区別されなければならない。
おそらく、プラトンも、ソクラテスとの対話を聞いてクレイトポンと同様の疑問を抱いたのだろう。すなわち、「私たちは無知であることは分かった。だが、それではどうすれば徳を身につけ、正しい知識を得ることができるのか?」という問いである。
この問い、すなわち「で、それから?」という不満や戸惑いは、当時のアテナイ市民の多くにも共有されていたに違いない。そして、こうした理解されにくいソクラテスの議論法は、市民の不信と反発を招くことになった。
こうした市民からの悪評は、のちにソクラテスを裁判にまで追い込んでゆく。
『クレイトポン』の作者が誰であるのか、いつの時代に書かれたものであるのか、それは分からない。プラトンの著作ではないと見るのが現在では有力なようだ。しかし、この作品は、ソクラテスの主張とそのアテナイでの当時の評価をありのままに描いているように思える。
ソクラテスの思想の歴史的意義は、それまで自然を主な対象としていた哲学の関心を、人間の魂とその表現である「言葉」へと転換させた点にある。彼の問いは、現代風に言えば、言語の使い方の厳密さを問うものであり、その意味で哲学史における大きな転換点となった。
とはいえ、ソクラテスは決して体系的な哲学の創始者ではなかった。彼は鋭い対話者であり、優れた教育者・弁論家ではあったが、思想を明確な体系として提示することはなかった。その作業を担い、ソクラテスの思想を理論化していったのは、弟子プラトンである。
『クレイトポン』においてクレイトポンは、そうした体系なき哲学を批判している。つまり、『クレイトポン』は、偽書であるからこそ、プラトンの解釈や理論を排した、より生身のソクラテス像を描くことができた作品なのではないか──このように捉えることも可能だろう。
引用
プラトン『アルキビアデス クレイトポン』(講談社学術文庫)より。
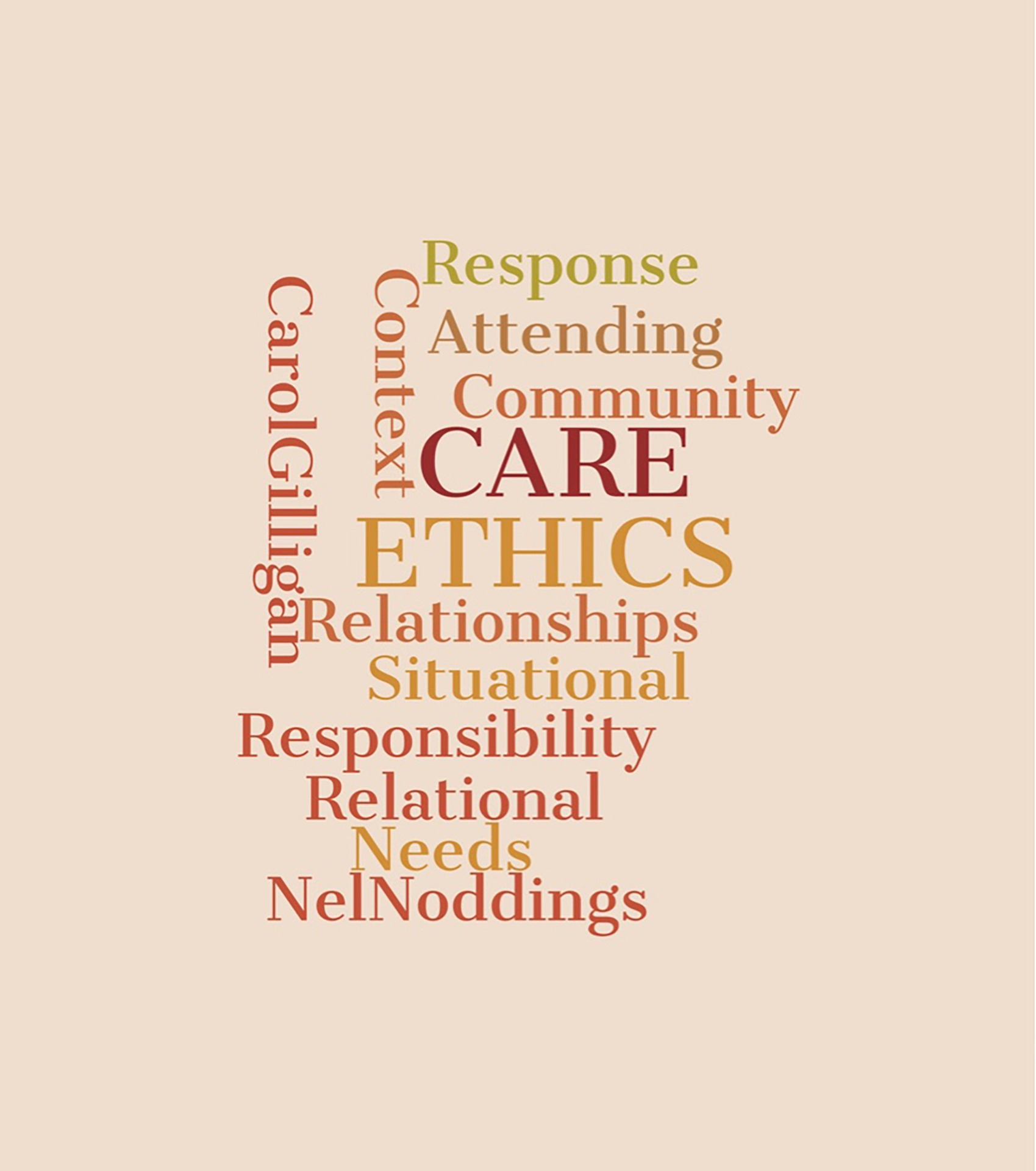


コメント