理性による信仰の意義の証明
17世紀フランスの思想家ブレーズ・パスカルの遺稿集『パンセ』は、人間の現実を鋭く観察した人文主義(モラリスム)文学の傑作として知られている。しかし、この書物は彼の死後、未整理の断片を編者が寄せ集めて編纂したものであり、著者自身が構想した全体像や意図は必ずしも明確ではない。そのため、『パンセ』は単なる断章集として読まれることも多く、作品全体の統一的な主題を把握することは長らく困難であった。
しかし、20世紀後半から進展した文献学的研究によって、『パンセ』の本来の構想が徐々に浮かび上がってきた。それによれば、この著作は単なる道徳的随想ではなく、17世紀フランスの宗教的論争、とりわけポール=ロワイヤル修道院を拠点に広がったジャンセニスムを擁護するための護教論的著作であった。ジャンセニスムは、人間の堕落と神の恩寵の不可欠性を強調するカトリック改革運動であり、パスカルはこの立場から信仰の合理的基盤を提示しようとしたのである。
『パンセ』全体を貫く大きな主題は「理性と信仰の相剋」である。近代的合理精神が台頭する時代にあって、信仰を否定するのではなく、むしろ理性の力によって信仰の必然性を明らかにする──これがパスカルの基本的な狙いであった。すなわち、理性を最大限に尊重しつつも、それだけでは人間の根源的問いに応えられないことを示し、その隙間にこそ信仰の意義があると主張したのである。
その試みの中でも最も有名なのが「パスカルの賭け」と呼ばれる議論である。これは、人間が信仰を選択する際に、理性によって完全な証明は不可能であるにもかかわらず、信じることの方が「得」であると論じる思考実験であり、信仰の合理性を示す代表的な一節として今日まで広く知られている。
パスカルの賭けとは
パスカルは、神の存在を理性だけで証明することは不可能であると認めたうえで、「信仰するか否かは合理的な賭けの問題である」と論じた。
彼の主張は次のように要約できる。
神が存在するかは分からないが、信じる方が損得の計算上は有利である。
つまり、信仰を「賭け」として捉え、勝敗とその利益を計算する発想である。
パスカルの議論は、神が存在するか否かという二分法に基づいている。もし神が存在し、信じた者が救済を得られるとすれば、その報酬は「無限の幸福」である。一方、神が存在しない場合、信じても失うものはごくわずかである(禁欲や宗教生活による小さな犠牲程度にすぎない)。逆に、神が存在するのに信じなかった場合、人間は「無限の損失」、すなわち永遠の救いを失うことになる。神が存在しない場合に不信仰を選んでも得られる利益は有限でしかない。
このように選択を「賭け」に見立てれば、無限の幸福を得られる可能性のある「信仰」の側に賭ける方が、合理的に考えて圧倒的に有利である、とパスカルは論じた。つまり、神の存在を理性で証明することは不可能だが、理性そのものを用いて信仰の選択を正当化できる、という逆説的な仕方で彼は信仰を擁護したのである。
ゲーム理論的枠組み
パスカルの賭けは、合理的な損得の計算によって成り立っている。そのため、ゲーム理論の期待効用最大化の概念で説明することができる。
ゲーム理論では、意思決定は「戦略」と「利得(ペイオフ)」で表される。
ここでの「プレイヤー」は自分自身、そして「自然(偶然)」である。自然は「神が存在する」か「存在しない」かを決定する。
意思決定者は「信じる」か「信じない」かを選ぶ。
この状況は2×2の戦略マトリクスで表せる。
利得表(期待効用の観点)
| 神が存在する(確率 p) | 神が存在しない(確率 1-p) | |
|---|---|---|
| 信じる | +∞(永遠の幸福) | -C(信仰のコスト:時間、自由、習慣の制約など) |
| 信じない | -∞(永遠の苦しみ) | 0(コストも報酬もなし) |
- +∞ や -∞ は天国や地獄の永遠の価値を表すため、有限の利益や損失より絶対的に大きい値である。
- C は現世における信仰生活の負担(有限値)である。
期待効用による説明
期待効用は次の式で計算できる。
- 信じる場合
EU(信じる) = p × (+∞) + (1-p) × (-C) → 常に +∞ - 信じない場合
EU(信じない) = p × (-∞) + (1-p) × 0 → 常に -∞
結果として、p が 0 より大きい限り、信じる方が期待効用が無限大になるため合理的選択となる。
このモデルでは「信じる」が支配戦略(dominant strategy)となる。
なぜなら、相手(自然)の状態に関わらず、「信じる」が「信じない」よりも高い利得を与えるからである。
理性の限界
もっとも、この「賭け」の議論が果たして成功したといえるかどうかについては、古くから議論がある。というのも、信仰を「損得の計算」として提示すること自体が、信仰の本質を歪めてしまうのではないか、という批判があるからである。真の信仰とは、打算による選択ではなく、心からの決断としてなされるべきものであり、合理的な見積りだけで人が神を信じることはできない、というわけである。
実際、パスカル自身の生涯を振り返れば、彼が信仰に至った決定的契機は「計算」ではなかった。彼は1654年11月23日の深夜、いわゆる「火の体験」と呼ばれる劇的な宗教的回心を経験する。彼はその体験を震える筆致で「炎、炎、炎。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。哲学者や学者の神ではない」と書き記し、その紙片を生涯肌身離さず衣服に縫い込んでいたという。この体験は、神の現存を圧倒的に感じ取る出来事であり、理性による推論をはるかに超えた信仰の根源的体験であった。
こうした事実は、パスカルの思想全体を理解する上で重要である。すなわち、彼にとって理性は決して軽視すべきものではなく、むしろ最大限に尊重される。しかし、理性はあくまでも有限であり、人間存在の根源的な問い──死や永遠、救いといった問題──に最終的な答えを与えることはできない。そこで理性が行き詰まる地点において、信仰が開かれる。『パンセ』の議論も、また「パスカルの賭け」も、この限界を照らし出すための試みであったと言えるだろう。
すなわち、パスカルの思想において「理性と信仰の相剋」は決して理性の否定を意味するのではなく、理性の果敢な探究の果てに露わになる「理性の限界」の自覚を意味している。そして、この限界を深く見据えたとき、人間ははじめて信仰へと身を開くことができる──それが、パスカル自身の生涯と著作が証している根本的なメッセージなのである。
理性時代の幕開け
しかし、パスカルが生きた時代そのものは、すでに理性中心の方向へと大きく舵を切っていた。17世紀は「科学革命の時代」と呼ばれ、ガリレオやケプラー、ニュートンといった科学者たちの業績によって、自然現象が数学的法則に基づいて説明されうることが次々と証明されていった。近代科学は急速に権威を確立し、宗教や信仰の影響力は徐々に後景へと退いていく。
こうした潮流の中で、『パンセ』の背後にあったジャンセニスム的な護教論としての意図は忘れ去られ、むしろ人間の心理や存在の矛盾を鋭く描き出した人文主義の著作として読まれていくようになった。この変化は、同時代のデカルトの著作に起きた現象とも並行している。すなわち、デカルトは『省察』などで神の存在証明を試みたにもかかわらず、その神学的意図はしばしば無視され、後世には合理主義哲学の幕開けを告げる近代的思索の典型とみなされるようになったのである。
このようにして、17世紀に芽生えた理性の自立は18世紀の啓蒙の時代へとつながり、本格的な「理性の時代」が始まる。信仰と理性の相剋をめぐるパスカルの思索は、時代の潮流においてはむしろ逆風を受けるものであったが、その理性の限界を見据えた姿勢こそ、合理主義が進展する近代にあって独自の光を放ち続けるのである。
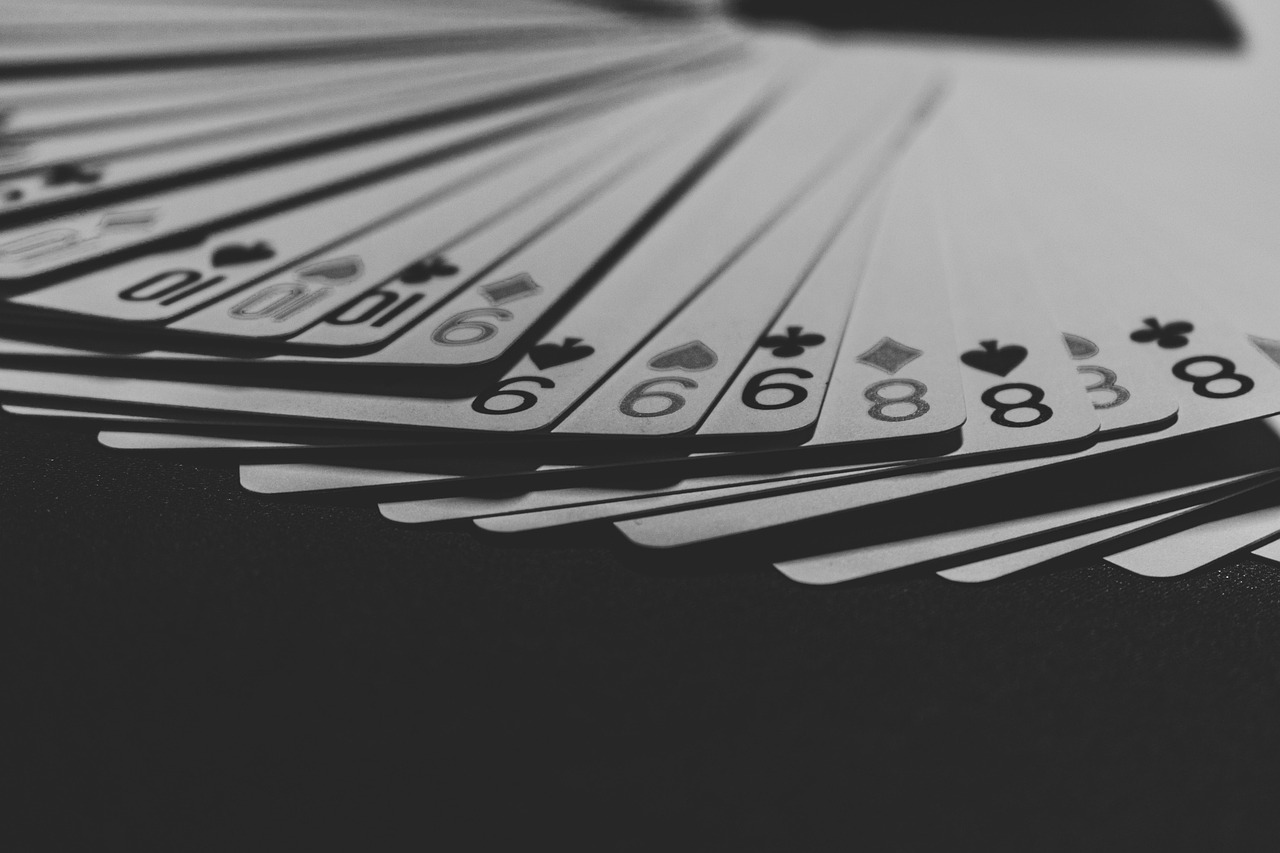
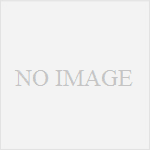
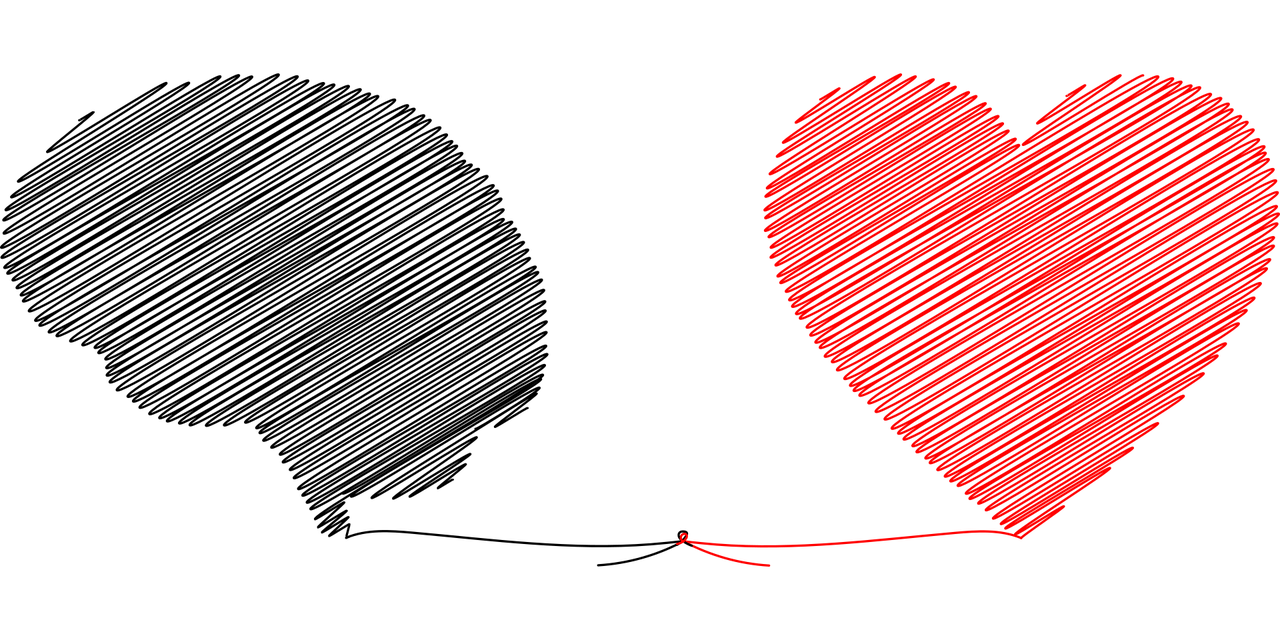
コメント