[adcode]
モノが動くという謎
物が動くというのはどういうことか―――
モノは力を加えれば動くし、斜面に置けば転がる。高いところから落とせば落下する。こんな当たり前のことに疑問を抱き、その説明を試みようとしたのが古代ギリシャ人たちだ。
運動の問題に関して、最初に体系的な理論を構築したのはアリストテレスである。アリストテレスの議論は、エンペドクレス以来の四元素論を継承し、その理論を精緻に組み立てて、観察される事実とその説明をぴたりと一致させた。観察と説明が一貫した枠組みの中で理解可能なもとなり、思想の一大体系を形成した。アリストテレスの運動に関する説明体系は、中世のスコラ思想を支配し、17世紀のガリレオの時代まで、主要な理論として君臨することになる。
アリストテレスにとって自然は、目的論的に解釈される。すべての物質には目的が存在し、その目的因に従って自然の秩序が形成されていると見做される。
彼の理論によれば、地上のすべての物体は、火、空気、水、土の4つの元素からなり、その混合の割合によって多様な物質が作られる。この4元素は、それぞれが本来あるべき自然の場所へ帰ろうとする「目的」を持つ。火、空気、水、土 の順に重くなり、最も軽い火は天へ上ろうとし、最も重い土は地へ帰ろうとする。土の元素を多く含む物体、すなわち重量の重い物質程、本来あるべき地面へと早く動こうとする。そのため重量の重いものほど落下速度は速くなるとされた。
このように地上の物質はほとんどのものが、古代の世界における宇宙の中心、つまり地球の中心へと向かう自然的性質を持っている。これは物質が持つ自然の運動法則として捉えられた。他の方向へ向かう運動はすべて不自然なものであり、何者かがそれに力を加えて生じさせた結果起こるものであった。
アリストテレスの運動原理は、「静止」を基本とする。物質が本来あるべき場所へと帰れば自然と静止する。そのため、説明が必要とされたのは、静止ではなく、運動の方であった。たとえば、物体の移動速度の違いは次のように説明された。ある物体の速さは、起動者がその物体に加える力に比例するとされ、運動に抵抗が存在する場合は、物体の運動の速度はその抵抗に反比例して変化するとされた。
アリストテレスは、このように運動に関して原理となる法則を打ち立て、そして、その理論を核として、その他の現象を説明した。
アリストテレスの運動の理論は、常識的に得られる観察によく一致するものだった。だが、すべての説明が可能だったわけではなく、この理論体系に収めるためにさらに説明の必要な変則的事実も存在した。
アリストテレスの理論によれば、静止が基本であり、下へ落下していくことが物質の自然法則だとすれば、物体が移動を続けるには常に起動者が必要ということになってしまう。
たとえば、矢は弓の弦を放れた瞬間に、物体の持つ自然の法則に従い、地面に落ちていなくてはならない。最初の起動者との直接接触が断たれた後も、矢が落ちずにいるために、矢に持続的な運動を与え続けているものは何か?しかし、それはアリストテレスの理論からは出てこなかった。
また、物体が落下する際、速度を次第に速めながら落ちるという事実も新たな説明を必要とした。これらの問題に対し、アリストテレス派の人々は、投射体がそのまま運動を続けたり、速度が変化するのは、空気の力のためと考えた。彼らは、起動者によって、物体だけでなく、最初の動きが空気中にも引き起こされ、その空気による力が、隣から隣へと伝達され、そが継続的に物体に働く結果、運動の持続と加速が生じると説明したのだ。
アリストテレスの理論体系が強固であったのは、このような例外的事例を説明する際に、その体系内に下位の法則を立てた上で、その法則に適合させて説明したからである。したがって、この思考体系の枠内でいくら観察をしても、理論は観察された事実を説明するための新たな説明を加えるため、理論自体は変更されない。次々に観察される変則的事実を例外としてではなく、理論として説明するためには、思考の枠組みそのものを根本的に変更する必要があった。新たの思考の転換が必要とされたのである。
[adcode]
慣性の発見
14世紀にアリストテレスの運動理論に挑戦し、それに代わるものとして「いきおい(impetus)」という考え方を提示した人々がいた。代表的な理論家としては、ジャン・ビュリダン、アルベルト・フォン・ザクセン、ニコル・オレームなどの名前があげられる。この一派はオックスフォードに端を発し、パリで一学派として受け継がれて発展し、16世紀の初めまで影響力を保った。彼らの理論は、近代的な「慣性」の概念を準備することになる。
彼らはまず、物体の運動は、外部から力が継続的に加えられる場合にのみ持続するという伝統的なアリストテレス以来の考え方を否定した。
彼らが発展させた理論によると、物体はそれ自体が有する量と運動の初めに与えられた量によって運動を続ける。すなわち、投射体はそれがすでに得ている勢いと、単に運動しているというというそのことのよってのみ加速を得て運動している。このことから物体に働く力は、一様な運動を起こしているのではなく、一様な割合の加速を起こしているのである。
さらに、物体の持つ「いきおい」は、物体が運動し始めた時の速さと物体の質量と正の相関関係を持つと考えた。そして、運動している物体が減速するのは、重力と空気の抵抗力によるとした。
こうして物体が動く理由として、「空気」による継続的加力という余計な説明要因を追加する必要がなくなった。説明体系はアリストテレスの理論よりさらに整合的で簡明なものになった。
近代的な慣性の原理は、17世紀の自然哲学者デカルトとガリレオによってほぼ同時期に提唱され、以降、急速に受け入れられていく。
1638年、ガリレオ・ガリレイが落体の法則を発表した。この説により、アリストテレス以来の常識であった物質の落下速度がその質量に比例するという考え方が否定された。ガリレオにとって、物体の運動は「静止」を基本とするものではすでになくなっていた。物体の運動あるいは静止は、外部からの力が加えられない限り継続する、と彼は考えた。近代の運動理論の原型はすでにこの時成立していたと言っていい。
重力はあらゆる物体の間に働く普遍的な力であるという見方もすでに現れていた。アリストテレスは地上のすべての物体が地球の中心へ向かう運動を自然の法則として捉えたが、天体観測が進展した17世紀には、天井の物体にも同じ不変的法則があるのではないかと考えられ始めていた。
1665年、アルフォンソ・ボレリは、太陽にも引力の作用があり、接線方向に飛び去ろうとする諸惑星の遠心力と釣り合うことで楕円の軌道を描くという考え方を提唱する。ここから万有引力という考え方が出てくるまでは、ほんの一歩である。
[adcode]
万有引力の登場
ニュートンが万有引力の法則を発表するのは1687年だが、1665年までには、ニュートンの引力の理論の材料はほとんど出揃っていた。しかし、それは個々の科学者の著作の中に散在している状態で、それらを結びつけて考える者はいなかった。
慣性、引力、遠心力といった考え方は、惑星の運動の問題を解決するために、それ以前に取り組んで理解しておかなくてはならないものであったが、それらはすべて、地上の物質に属する事柄で、地上にのみ適応される法則とされていた。アリストテレスの伝統的な理論では、地上と天上は全く異なる法則に従うとされていたからだ。だが、17世紀以降の急速な天体観察の成果によって、地上の物質と天上の天体の運動法則を統一的に捉えようとする思想家が各地で同時多発的に現れてくる。ニュートンも同時期に天体の動きを慣性と遠心力から説明しようと試みていた。
ニュートンは1665年には遠心力に必要な公式を独自に発見していたものとみられている。重力が距離の二乗に反比例する力で惑星を引きつけるとすれば、惑星はその軌道をそらさないために、相対応する力、すなわち遠心力を持つということを発見した。遠心力と重力の作用を数学的に表現することに成功したのである。
ニュートンはこの時点で重力と遠心力の基本的な総合に到達していた。ところがその証明に不完全な点があり、以降多年にわたってこの仕事を顧みず、放置することになった。
だが、1672年、転機が訪れる。天体観測上の重大な発見がもたらされるのである。ジャン・ピカール指揮下のフランス遠征隊が、カイエンヌとパリとで火星の高度を同時に測定した。この観測の結果、地球から太陽までの平均距離が以前より正確に求められた。またそれだけでなく、太陽系の大きさがより一層明確になった。ニュートンはこの資料を用いて、彼の最終的な計算を行い、自らの体系の正しさを確信する。
そして、1687年、『プリンキピア』を発表した。ニュートンが彼の体系を発表する以前は、デカルトの渦動論が有力な理論として受け入れられていた。デカルトの理論は、真空を否定する理論であり、空間にはエーテルという物質が充満しており、それが物質の運動に関わるとされていた。ニュートンの万有引力は、その理論が不可能であることを示すことになった。デカルトの物質が充満して渦巻く宇宙に対して、ニュートンの空虚な宇宙が取って代わることになった。
ニュートンの最終的な勝利は、近代科学の方法論を決定づけることにもなった。デカルト的な精緻な演繹的体系によって自然を説明するのではなく、幾何学と実験的方法との連合によって自然の正しい姿を証明していく―――これがのちの近代自然科学の基本的な方法論となっていくのである。
参考図書
ハーバート・バターフィールド『近代科学の誕生(上)』講談社学術文庫
ハーバート・バターフィールド『近代科学の誕生(下)』講談社学術文庫

[adcode]

-e1615228993521.jpg)
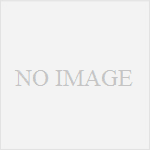
コメント