[adcode]
井伏鱒二『多甚古村』(1939)
[adcode]
多甚古村―――
読み方は「たじんこむら」。裏手に山を控え、岸辺近くの南方のどこかの農村、ということまでしか分からない。
「国家危急の際」という言葉が作中、何度か出てくる。だが、人々の暮らしにそれほど逼迫した様子は見られない。おそらく時代は、盧溝橋事件後すぐの日中戦争時。当時は支那事変と呼ばれて、政府は戦争として認めていなかったため、一般には戦争という意識はそれほど強くなかっただろう。しかし、若者が次々に徴兵されていく様子は描かれている。
この農村の駐在所に新しく赴任してきた、年のころ30前後の甲田巡査の目を通して、田舎の人々の暮らしが描かれている。
長閑で牧歌的な生活―――と思いきや、そうでもない。
駐在所には、喧嘩や泥棒の知らせ、もめ事の仲裁依頼など、次々と人々が駆け込んでくる。甲田巡査はその度にせわしなく駆け回っている。
土方の人夫が酒に酔って仕事仲間の朝鮮人と喧嘩騒ぎ。
正月賭博の一斉捕り物。
隣町の逃走犯の張り込み。
タクシーの無賃乗車。
等々、意外と騒がしい事件が続く。だが、どれもあっけらかんと片付いてしまう。取り押さえれれば素直に罪を詫び、仲裁に入られれば、おとなしく意見に従う。出来事は騒がしいが、人々は純朴だ。
非常に面白いのが、甲田巡査が、事件以外にも村のさまざまな揉め事に巻き込まれているところだ。
夫婦喧嘩やら親子喧嘩、村の水路利権の争いから、犬に噛まれて慰謝料払え払わんの揉め事まで、あらゆる争いに仲裁に出ている。
裁判沙汰などほとんどないような田舎の農村だ。裁判になるほどでもない揉め事は、話が大きくなる前に巡査がとりなして解決していたんだろうなと思う。作中には「人事係」という言葉が出てくるが、当時は地方の駐在所は、行政事務の一部も兼ねていたのかもしれない。
作品中に、面白い事例が出てくる。
私が自転車から降りて「こんばんは奥さん、何やね」とたずねると、奥さんは可なり悄気込んで「こんばんは、旦那はん。ちょっとお願いがあってまいりましたのや」と云った。山田さんの家は小地主で当主は元教員である。暮らしも安泰で外に出るにも奥さんはいつも派手な風をしているが、今日は地味な着物に前垂をして、手拭を前垂の横に垂らしていた。「どうしたんです」ときくと「へえ、困っとりますのや。長男がこのごろ休暇で帰っていますのや。それが町の妙な女と、一しょになる云うてきけへんし、うちではあの通り頑固だし、長男は家を出るちゅう。うちでは勘当やと云う。わたしは、どないもならぬけに、旦那はんに仲にはいって貰おうと思うて来たんやけど」と云う。「さよか、しかしなあ」と私は、じっくり考えてみた。
いったい駐在巡査というものは、人事主任も司法主任も行政主任も特高主任も何でも一人で兼ね小使も兼ねている。
都会の学生のまねをして喫茶店に出入りする不良学生。そこの女給と恋仲になったものの、その女給にはやくざの情夫がいて―――事情はそんなところだ。
甲田巡査は、山田の奥さんの息子を説得し、やくざと喫茶店の女給には話を付けてやると約束する。
大正昭和の文学には、カフェというのがよく出てくるが、当時のカフェ(喫茶店)というのが、いかがわしいところと言われていた雰囲気がこの作品から良く伝わってくる。スタバのようなオシャレにノマドワークするようなところではないようだ。昭和初期の風俗が垣間見れて面白い。
海辺近くに村長が所有している貸別荘がある。そこにはアメリカ人の老人が孫娘二人を連れて一時期、滞在していた。その後は、都会から気の強い自由奔放な令嬢が移住してきた。彼らは、村人から謂れのない言いがかりや難癖をつけられたりしている。
しかし、異国人や都会的な彼らの存在は、片田舎の農村の物語に現代的で異国情緒の彩りを与えている。単純に農村の風俗もので終わらせないところに、作者の妙味を感じる。
村人たちは、漱石の『坊ちゃん』のように渾名で登場する。
交換君、温帯さん、眼界さん。。。
起こる出来事は騒々しく醜いものばかりだが、それを取り巻く人々の素朴さがこの作品に暖かいぬくもりを与えているのだろう。
作者の筆致は淡々として軽妙で、嫌みなところが全くない。村で起きる事件や醜聞、差別や偏見までをありのままに描いて、それを田舎の長閑な風情として見せてしまう。
田舎に暮らす人々のゴタゴタとした揉め事や争いまでを「牧歌的」に描いてしまうところにこの作品の魅力があるのだろう。
[adcode]


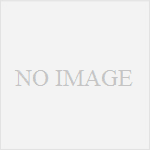
コメント