[adcode]
ニーチェ『道徳の系譜学』(1887)
[adcode]
『善悪の彼岸』を補う書
ニーチェは、本書の前付けにて、この書を前著『善悪の彼岸』を補足、説明するものと述べている。
『善悪の彼岸』自体が『ツァラトゥストラ』の超人思想を説明するべきものだったはずだ。しかし、『善悪の彼岸』は、ヨーロッパ近代の時代診断へと主題を大きく変えていくことになった。超人よりも、それを抑圧する病理の方へと批判の目が向けられていった。
ニーチェは、この時代診断によって、「家畜の群れによる道徳」をヨーロッパの病理として暴き出した。しかし、今度は、この家畜の群れがどうして、主人の座に取って代わることができたのか、という問いが生じてくる。
そこでニーチェは、この道徳が発生した歴史を解き明かしていくことが必要となった。『道徳の系譜学』は、この問いに答えようとした書だ。
ニーチェが、ここで重視したものこそが「ルサンチマン」という人間の心理機制である。
[adcode]
ルサンチマンとは何か
ニーチェは前著『善悪の彼岸』で、人間本来の在り方を自己保存の本能に従うものではなく、自己の生の限界を試す存在として捉えていた。「力への意志」を体現するものこそ正しい人間の在り方だった。
この「力への意志」を発揮する健全な精神の持ち主は、能動的であること、創造的であることを最善の価値としている。
しかし、「力への意志」を欠き、本来支配されるべきものたちが、この価値の転倒を企てた。「弱いもの」こそ正しい、と見做したのだ。
この価値の転換によって、人間の「生」に対する攻撃が始まる。そして、それはさらに自己自身に内面化され、禁欲の倫理として発展した。
自分の力の弱さを認めず、価値の転換を図ることで、自己を正当化しようとする精神態度―――
これが、ニーチェの言う「ルサンチマン」だ。
この価値の転倒において、重要な役割を果たしたのが、僧侶(司牧者)であり、キリスト教だ。
利害関係から生じる「負い目」、経済関係から生じる「負債」―――
キリスト教は、人間の精神に生じるこれらの心理的な負い目を罪として、人間の原罪にまで仕立てていった。ニーチェのキリスト教に対する批判の目は極めて厳しい。
ここからニーチェの徹底した宗教批判と現代批判が展開されていくことになる。
[adcode]
ニーチェの見落としたもの
近代ヨーロッパの精神病理を鋭く抉ったニーチェだったが、彼の議論には大きな飛躍があることもまた確かだ。
『善悪の彼岸』においてもそうだったが、ルサンチマンによる価値の転倒が企てられて以来、2000年に及んで対立をしてきた「弱者」と「強者」は、なぜ、近代ヨーロッパにおいて弱者の勝利をもたらしたのか、という問いに何の答えも与えられていないのだ。
『ツァラトゥストラ』において、ニーチェは、「超人」を志向する孤高の存在としてのツァラトゥストラを描いた。だが、その解説を試みようとした『善悪の彼岸』と『道徳の系譜学』においては、「力への意志」を歪める「家畜の群れ」への徹底的な批判へと主題を変えていった。
そのため、ここに人間の二類型が生じることになる。
「獅子」と「家畜の群れ」、「高貴なるもの」と「卑しいもの」、「支配するもの」と「支配されるもの」―――
このようなニーチェの議論からは、いわば、精神の階級闘争史観と呼ぶべき様なものが生じてしまう。『ツァラトゥストラ』に見られた孤高の人間の生き方を問う視点は、すでにニーチェからは失われていた。
ニーチェは、本書の執筆以降、予定していた理論的大著の計画に挫折し、さまざまな批判に応えるための論争の書を矢継ぎ早に執筆していくことになる。
あたかも、ニーチェ自身がこの精神の階級闘争に巻き込まれていったかのようだった。そして、この階級闘争は、精神錯乱というかたちで、ニーチェの敗北として終わっていった。
ニーチェがイタリアのトリノで昏倒したのは、本書の出版後、わずか1年半後のことであった。

[adcode]

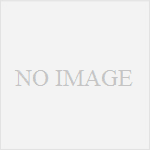
コメント