無身という思想
江戸時代に入ると、武術における「身体」の存在感は徐々に薄れ、「心」が重視されるようになる。いわば唯心論的な思想が主流になっていくのである。たとえば、戦国時代の武士は「腹が減っては戦はできぬ」と語ったが、江戸時代になると「武士は食わねど高楊枝」といったように、身体的な欲求よりも精神的な制御が理想とされるようになった。
この傾向は剣術に顕著である。無住心剣のように、精神的な修養を極端に追求することで、具体的な技術的裏付けを失い、やがて消えていった流派もある。武術の中には、肉体を徹底的に意識しながらも、それを心の中に吸収し、消し去ろうとする思想が存在したのは確かだ。実戦においては命のやり取りが前提であり、体調や調子といった個別の身体的要素は問題にならない。だからこそ、精神が身体を超越する必要が生じる。技はしだいに唯心論的に解釈されるようになっていくのである。
柳生新陰流の伝書『兵法家伝書』の頃から、武術において「気」という概念が独立して前面に出てくる。著者である柳生但馬守宗矩は、禅僧・沢庵の影響を受けていた。禅の中でも一休は江戸以前の人物で、身体の有用性を認めており、『一休骸骨』には死後の身体に対する執着さえ見られる。しかし江戸時代以降、そのような身体への意識は次第に消えていく。「気」が盛んに論じられるようになったのは、武士たちが中国古典、とくに道教や儒教の文献を読むようになってからである。
ここでいう「気」は、現代で言えば「意識」に近い。心を構造ではなく機能から捉えようとする機能主義的な発想である。日本文化には、「年ごとに咲くや吉野の山桜 木を割りて見よ 花のありかは」という和歌に象徴されるように、形(具体)を通して初めて心(抽象)が現れるという考え方がある。心は目に見えないが、確かに人を生かしている「神気」として存在しており、それは誰もが観念的には理解できる。このような捉え方が、武術における要諦や極意として受け継がれていく。
江戸時代の剣術は、身体性を失い、次第に教養や思想としての側面が強まっていく。これは、禅の思想の影響が大きい。禅に傾倒した剣術は、技の数を減らし、より単純化されたものに収斂していく。一方で、神道に由来する流派では、技術が減るどころか、細胞分裂のように技が次々と増えていった。つまり、禅的な影響は技の「抽象化」を促し、神道的な伝統は「具体化」や「拡張」を促したのである。
このような時代背景の中で、武術家たちが禅に惹かれるのは、ある意味で自然な流れだった。予測不能で理屈では説明できない動きを会得するためには、矛盾を矛盾のまま受け入れ、自己さえも説明できない動きを追求する必要がある。そうした動きを制御するために、なんとか技という具体の中でそれを掴もうとしたのが「術」の世界である。結果として、禅と似た方向に向かい、「余計な知恵を使うな」「頭で考えるな」といった態度が求められるようになる。
本来、論理では解決できない問題に対して、それでもなお答えを見出そうとする執念がある。論理的には矛盾している事柄を、身体で実感し、解消しようとする姿勢。禅の影響を精神論ではなく、技術論として捉えることで、より実践的な理解が可能となるだろう。
ある意味で、禅は非常に体制的であり、現代の科学的思考にも抵触しない。それは禅が徹底したニヒリズムを内包しており、絶対的な信仰を持たず、論理の限界を逆手にとって「悟り」として飛躍する思想だからである。禅がしばしば誇大妄想的、唯我独尊的と見なされるのは、たとえ論理的に破綻していようと、悟りを得た自己は完全に肯定され、他人の評価を超越するからである。
日本人は外面的には協調的に見えても、内面では非常に個人主義的で、自意識の強い一面を持っている。その性質が、武術の精神性や禅的思考と深く結びついていたことは否定できない。
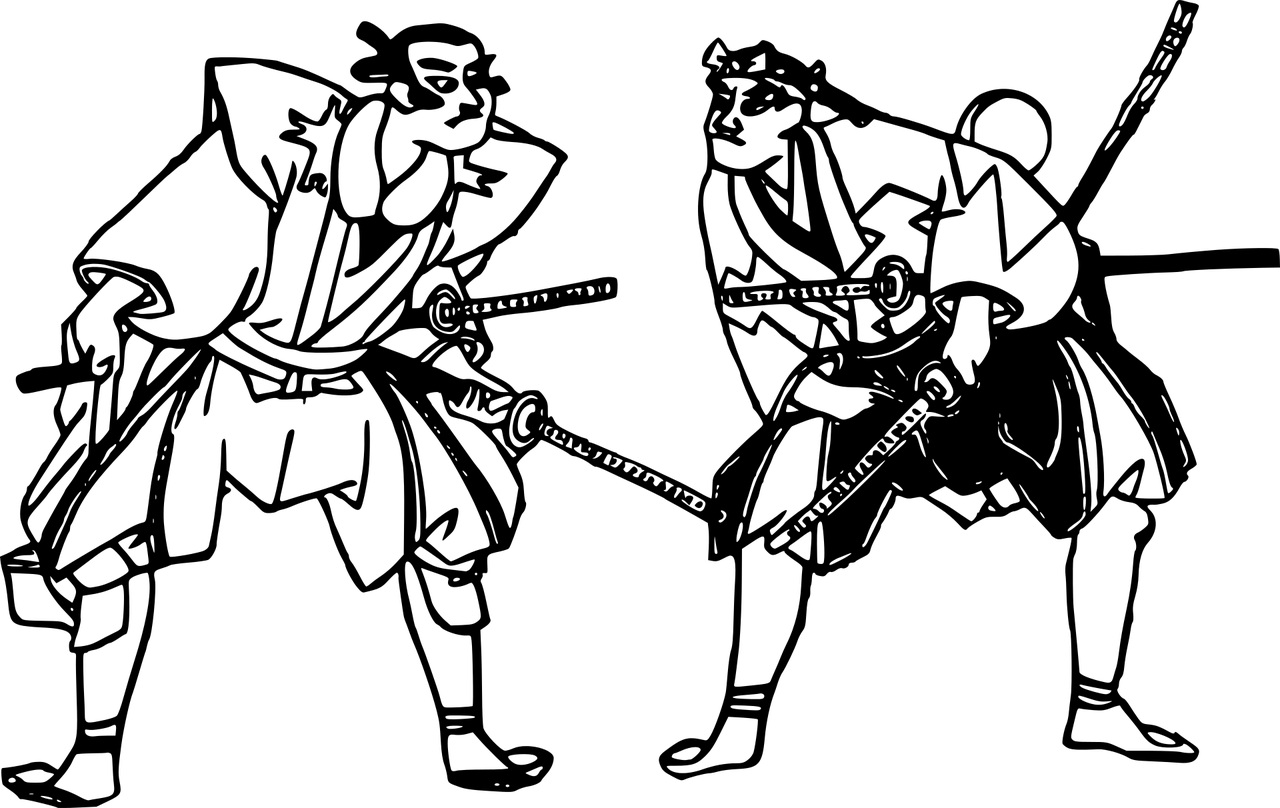


コメント