絶版本の世界へようこそ。
あえて絶版本を読み、それを紹介するという誰得?な企画です。
養老孟司・甲野善紀『古武術の発見』光文社 (1993)
失われた身体感覚を取り戻す
一度失われた技術を再び取り戻す———
甲野善紀氏は古武術の研究家であり、日本における失われた身体感覚の復興に取り組んでいる。
甲野氏は、身体感覚の質的な転換、すなわち日常的な身体操作からの脱却によって生まれる、武術特有の動きに着目している。彼によれば、武術における身体の運用とは、単なる日常動作の延長ではなく、感覚の再編を伴う「質的転換」であるという。
この考え方は、古伝における型稽古が、単なる模倣や反復訓練ではなく、知覚と身体操作の解体・再構成を目的としていたという洞察に基づいている。稽古を形式的な練習としてではなく、「感性の再構成」や「動きの脱構築」として捉える視点は、非常に先鋭的である。
また、精神は身体技法と切り離せないものであり、身体性から自然と立ち現れてくるものだという。近代以降に分断されがちであった「身体=実践/精神=理念」という二元論に対する、批判的な視点が示されている。
失われた日本の身体感覚は、どのようにして取り戻すことができるのか?
本書は、対談形式。話の聞き手は、脳科学者の養老孟司氏。博学な二人の議論から、かつて日本人が持っていた身体感覚の再構築が試みられている。それは、現代の私たちの感覚からすると、かなりかけ離れたものだ。昔の日本人が今とは全く異なる感覚で生きていたと思うと、不思議な感じがする。
二人の話は多岐にわたっていて、非常に興味深い。
武道の変遷
現代の武道というのは、江戸期の武術とはまったく異なるものになっている。明治維新を境に近代化が始まり、その中で武道の質的な変化が進んだ。まず、明治維新直後には、武術は文明開化にそぐわないものとして一時的に社会から排斥された。また当時は政治的にも混乱しており、武術の稽古をしているだけで警察から睨まれることもあった。
しかし、西南戦争での抜刀隊の活躍などを経て、武術の軍事的な役割が再認識されることになる。結果として、武道はその後の富国強兵、そして軍国主義へと向かう流れの中に取り込まれ、発展していった。実技面でも精神面でも、軍の強化に利用されていったのである。
その一方で、講道館の影響もあり、武道はスポーツ化していく。加納治五郎は初歩的な力学を用いて柔術を理論化し、講道館柔道は大きく発展したが、その過程で柔術が持っていた術理の伝統が失われることにもなった。柔術家たちは、野蛮視されていた柔術が講道館のおかげで日の目を見るようになったことから、あえて講道館に異を唱えることはしなかった。
戦後、アメリカ軍によって武道は一時禁止されたが、徐々に解禁される過程で、スポーツ化の傾向はいっそう加速した。しかし、完全にスポーツ化したわけではなく、精神修養という側面が強調されるようになった。軍隊式の訓練方法が根強く残り、単純な反復稽古が「根性」としてノルマ化され、押し付けられる。それが他のスポーツにも影響を与えている。
古伝における武術と「型」の意義
身体の意識の仕方について、過去のやり方や伝統は一挙に失われてしまった。いかにして身体をもう一度取り戻すかという点において、現在もなお暗中模索の状態が続いている。かつての天才的な武術家たちが何代にもわたってようやく確立した体系を、現代武道は素人の浅薄な合理主義によってあっさりと捨ててしまった。
昔の文献は、技に関する部分でも非常に抽象的に書かれており、現代人が読むと観念的、精神主義的に見えるが、実はそれらの多くは具体的な技術論である。体格や体力に頼らない術、つまりいわゆる精神論的な武道ではなく、「術」にこだわった武術の体系が、かつては存在していた。
その術とは、日常的な体の動きの延長線上にあるのではなく、質的に転換した動きであり、身体感覚を組み替えることによって得られるものである。型稽古も本来はこの目的のために行われていた。古伝における型稽古は、日常の中で固定化された身体感覚を分解し、個々の基本的な動きを取り出すための動作であった。つまり型とは、日常的な動作の癒着を剥がすための基本動作なのである。
すべての動きを単純な因果関係として捉えないこと。個々の動きをバラバラに還元し、それらを新たに組み合わせていくことで、初めて予測しがたい「術」としての動きが生まれてくる。型の追求には、それを受け取る側の感性が重要であり、したがって武術の修行とは非常に個人的なものである。大勢に対して「反復練習としての型」を一律に押し付けるやり方は、本来の武術の要請にはまったく適しておらず、そこから質的に転換した動きが生まれることはない。
型と実践、精神論を別々に理解してしまった結果、そのつながりが見えなくなっているのではないか。意識の分散化や予測できない動きというのは、型を一つ一つ体感していくうちに自然と身についてくるものである。型に精神論を詰め込むのではなく、型の中に身体の使い方や心の運び方が内包されているということである。
武術における「精神」とは、身体運用の方法を追求していくうちに不可分の関係として自然と身についてくるものであり、「精神」から身体に入っていこうとするのは、順序が逆である。
現代においては、「自分」という言葉を使うときに身体を含めて考える人は非常に少なく、たいていは「自分=心」と考えてしまっている。一方で、現代のスポーツや武道では、日本文化が持っていた「身体を消す」という美学の裏返しとして、極端な形で身体を意識させることが前提となっており、それが軍隊式訓練や体育会系のしごきにつながっている。
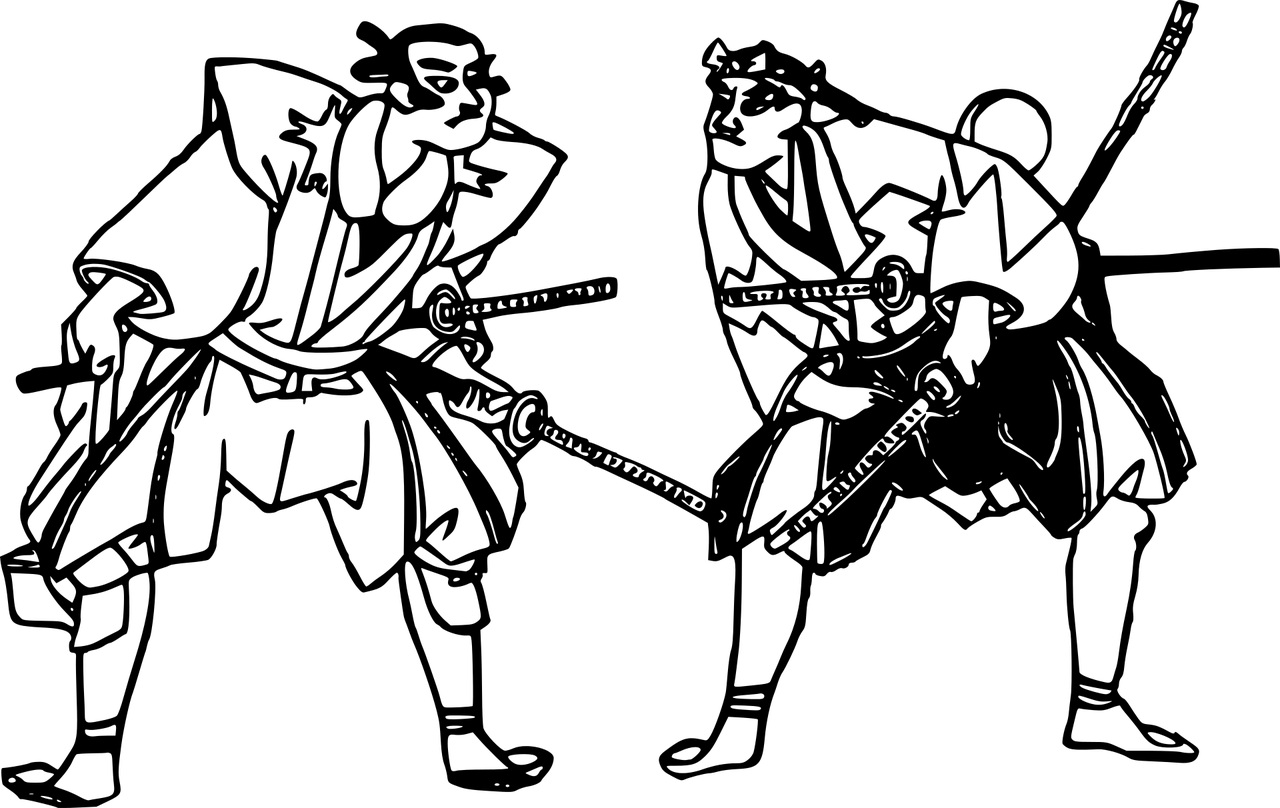


コメント