はじめに:意識の起源を問う
「意識」とは何か。この問いに明快な答えを出すことは、現代の脳科学や哲学においてもなお困難を極める。意識とは単に自己が世界を感じる感覚なのか、それとも記憶や言語と不可分の高度な情報処理の現れなのか。いずれにせよ、意識は単独の脳部位に閉じた内部現象ではなく、他者や環境との相互関係のなかで立ち現れてくる動的な構造だという理解が近年強まりつつある。この記事では、情動の神経基盤である「扁桃体(扁桃核)」の働きを起点に、情動と社会的共鳴、そして言語と意識の発生との関係を考察してみたい。
扁桃体と情動:個体内の反応から集団的現象へ
霊長類、特にサルや人間では、側頭部に位置する「扁桃体(amygdala)」が情動反応や社会的行動に深く関与していることが知られている。扁桃体は恐怖や怒りといった情動の発火点として機能するだけでなく、他者の表情や行動に対する意味づけ、危険の予測といった、社会的状況に対する評価判断にも重要な役割を果たす。
この扁桃体の機能を調べるため、サルを対象にした実験が行われた。実験では、あるサルの扁桃体を切除し、その行動の変化を観察した。すると興味深いことに、切除されたサル自身よりも、むしろ周囲のサルの行動に顕著な変化が見られた。切除されたサルは表情や行動による情動の表現が乏しくなり、それが他のサルにとっては「異常」として知覚され、周囲のサルが不安や混乱、警戒といった過剰な反応を示すようになったのである。
この現象は、情動というものが単に個体内で完結するものではなく、他者との間における「共鳴」として成り立っていることを示唆している。つまり、情動とは常に「誰かに向けられたもの」であり、「誰かに受け取られるもの」でもある。
情動から意識へ:共鳴と鏡映の神経基盤
このような社会的共鳴の現象に関わる神経基盤の一つとして注目されているのが、「ミラーニューロン(鏡映神経)」である。ミラーニューロンは、他者の動作や表情を見るだけで、自分がそれを実行しているかのように活動する神経細胞で、他者の意図や感情を理解する基盤となっていると考えられている。情動もまた、こうした神経系を通じて、個体間で「感情の模倣」や「共感」の形で伝播する。
さらに、こうした共鳴現象は、単なる感情の伝達にとどまらず、自己と他者の区別、すなわち「主観の境界」を生み出す契機ともなっている。自分が感じているのか、他人の感情を感じ取っているのか。その判別のために脳は高次の統合処理を必要とし、ここに「意識」という現象が立ち現れてくる。
言い換えれば、意識とは単に自己の内部を照らす光ではなく、他者との相互行為のなかで生じる「反射的構造」なのである。自己とは、他者に映された情動の鏡像を通して初めて輪郭をもつ。これは哲学的に言えば、フッサールの「間主観性」やメルロ=ポンティの「他者のまなざし」とも通底する考えである。
社会的動物における意識の連鎖構造
情動の伝達は個体間の「感情的つながり」を作り出す。特に社会性の高い動物では、知覚系と運動系が他個体と連動し、全体として連鎖的な行動構造を形成する。たとえば、群れの中で一匹のサルが危険を察知し緊張すると、それが一瞬で群れ全体に広がるのはこのためである。
このような連鎖の中で個体が「自分と他者の違い」を学び、「自分の行動が他者にどう影響するか」を予測・制御する能力が発達してくる。この予測可能性の枠組みの中で、時間的持続性をもった「自己モデル」が形成され、そこに「意識的な自我」が生まれる土壌が整っていく。
意識とは「共鳴のなかの自己」
意識は、生物の内部に閉じた、孤立した情報処理装置の産物ではない。それはむしろ、情動の共鳴や模倣、社会的な相互作用のなかで編み上げられる、動的かつ関係的なプロセスである。扁桃体やミラーニューロンが示すように、脳の働きは常に他者に向かって開かれており、意識もまたその開かれの中で生じる。
言い換えれば、私たちは他者と出会い、他者のまなざしを受け、それに応答するプロセスのなかで、「意識を持った自己」になっていく。情動という根源的な共鳴装置が、やがて自己と他者を分かつ鏡となり、そこに「私」が映し出されるのだ。
意識の発生──言語と他者を通じて「私」は生まれる
自己の意識は、他者の存在を媒介として初めて成立する。意識は孤立した個体の内面から自律的に生じるものではない。これは「言葉の成立」を手がかりに考えると、より理解しやすい。
言語の意味と自己意識の成立には、構造的な類似がある。たとえば、ある言葉の意味を、単なる「直示(直接的な指し示し)」によって他者に伝えることはできない。仮に、道端の花を指さして「これが花だ」と説明したとしても、聞き手にとっては、その言葉が何を意味しているのかは判然としない。指されているのは色か、形か、香りか、花の一部か全体か、それとも発話の状況全体か──直示だけでは意味は決定されないのである。
この問題に対してルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインは、「言語ゲーム」という概念を提唱した。彼によれば、言葉の意味とは、単なる記号と対象の一対一の対応ではなく、「その言葉がどのような文脈で、どのように使われ、どのような反応を引き起こすか」という社会的・実践的な用法の中で理解されるものである。つまり、言葉の意味を学ぶとは、ある言葉を使ったときに、他者がどのように反応するかという相互作用の一連のパターン──すなわち「ゲームのルール」を学習することに他ならない。
この言語ゲームの考え方は、言葉の意味の理解が、個人の内省や自己の経験から生じるのではなく、むしろ他者の行動や反応を観察することから始まるという、経験の順序の逆転を前提としている。たとえば「痛み」という極めて個人的と思われる体験すら、まずは他者が痛がっている様子(うめき声や身振りなど)を観察し、それが「痛み」と名づけられていることを知ることによって、自己の内部体験にもその枠組みが適用されるようになる。つまり、他者の身体の表現から逆照射されて、自己の感覚が輪郭づけられるのである。
このように見てくると、意識の起源には明らかに、他者の身体と外部環境が深く関わっていることがわかる。人は、自分自身を一人の他者として外部から観察され、名指されることを通して初めて、「自分がどのような存在であるか」を記述する語り方を獲得する。言い換えれば、人は他者によって「意識される」ことを通して、「自己を意識する」ことができるようになるのである。
ここで重要なのは、他者の心や感情が実在するから学ばれるのではなく、「あるものとして」学ぶことによって、結果的に実在するかのように経験されるという点である。そしてこれは、自分自身の心についても同様である。自己の内面もまた、「あるものとして他者から学ぶ」プロセスの中で意識化される。
したがって、意識とは自己の内的心理や精神から自然に湧き上がるものではない。さらに、脳の生理的な働きによって単独で生じるものでもない。それは、他者の脳に備わった認知機能を前提とし、自己と他者の相互作用、すなわち共鳴のネットワークの中で初めて成立する現象だと考えるべきである。
参考
下條信輔『意識とはなんだろうか』(1999)

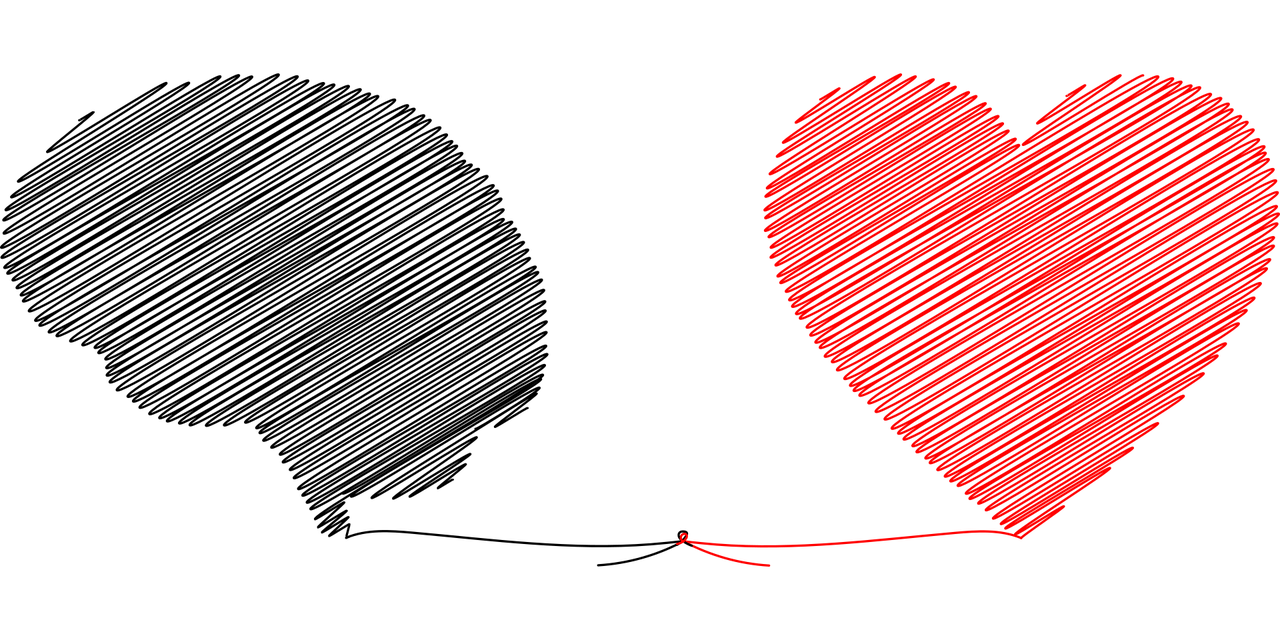

コメント