哲学をすることの意味とは?
日常誰でもが出会う事柄に対して半病的なこだわりをもち、それに対して全身でぶつかってゆき答えを求めようとする無謀でいくぶん滑稽な(まさにトン・キホーテ的な)営みこそ哲学なのです。
哲学は、役に立たない——しかし、だからこそ意味があるのかもしれない。
哲学が、日常生活や仕事の場で直接的な実用性を持たないことは、専門的な知識がなくても多くの人が理解できるだろう。しかしそれでも、「思考力を鍛える」あるいは「精神的な成熟に寄与する」と期待する人は少なくない。
だが、哲学が必ずしもそうした期待に応えるとは限らない。思考力や精神の成長に寄与するかどうかも、実際には疑問が残る。ではせめて、哲学に没頭することで精神的な充足感や喜びが得られるのかと言えば、それもまた難しい。むしろ、考えれば考えるほど苦悩が深まり、迷いが増すことさえある。哲学は、娯楽としても高尚な趣味としても、簡単に楽しめるものではない。
では、なぜ人は哲学をするのだろうか?
それは、おそらく「哲学するしかないから」なのだろう。
著者自身は、そのように哲学を捉えている。
理由や目的があるわけではない。ただ、問わずにはいられないから問う。登山家が「そこに山があるから登る」と言うように、哲学者は「問うべき問いがそこにあるから考える」のだ。
哲学に惹かれてしまった人は、それに理由があるというより、むしろ「惹かれてしまった」という状態そのものが出発点なのだ。哲学という営みから明確な成果が生まれるわけではない。社会的にも、個人的にも、「役に立たない」ことばかりだと感じることもある。
それでも、問いを抱えてしまった人は、それを考えずにはいられない。ただ、それだけのことなのだ。
意味がないからこそ問う
哲学への入り口は人それぞれだろう。著者の場合、「死」という不条理な問いが出発点だったという。しかしそれは、あくまで著者にとっての個人的な問題であって、哲学全体の普遍的な出発点とは言いがたい。「死」や「実存」といったテーマは、数ある哲学的な問いの一つにすぎない。たまたま著者がその問題に強く引き寄せられた——それだけのことかもしれない。
また、著者が大学に職を得た時点で「哲学的彷徨は終わった」と語るくだりには、ある種の矛盾も感じられる。もし哲学が本当に何の意味も持たない営みであるなら、それを職業にすること自体、ある種の目的性を持ちうるということになりはしないだろうか。
哲学すること自体には、たしかに実益は乏しい(大学教授を除けば)。それでも、どの時代にも、どの国にも、問わずにはいられない人が一定数存在する。そして、その問いはしばしば、その人自身の存在に根差したものである。だからこそ、他人にとっては取るに足らないことであっても、自分自身では考え続けずにはいられない。
哲学関連の本を読み続けていると、ふとしたときに虚しさがよぎることがある。
「こんなことに、いったいどれだけの時間を費やしているのか?」
「もっと別のことをすべきではないか?」
そうした考えがふと浮かぶのは、どこかで哲学が“何かの役に立つ”ことを、まだ少し期待しているからかもしれない。
しかし、哲学は役に立たない。いや、むしろ「役に立たないもの」として、哲学は存在している。
それでも、ある問いに取り憑かれた者が、考え続けること。
それが哲学なのだと思う。
そう再確認できただけでも、この本を読んだ意味は、きっとあったのだろう。……たぶん。
中島義道『哲学の道場』(1998)
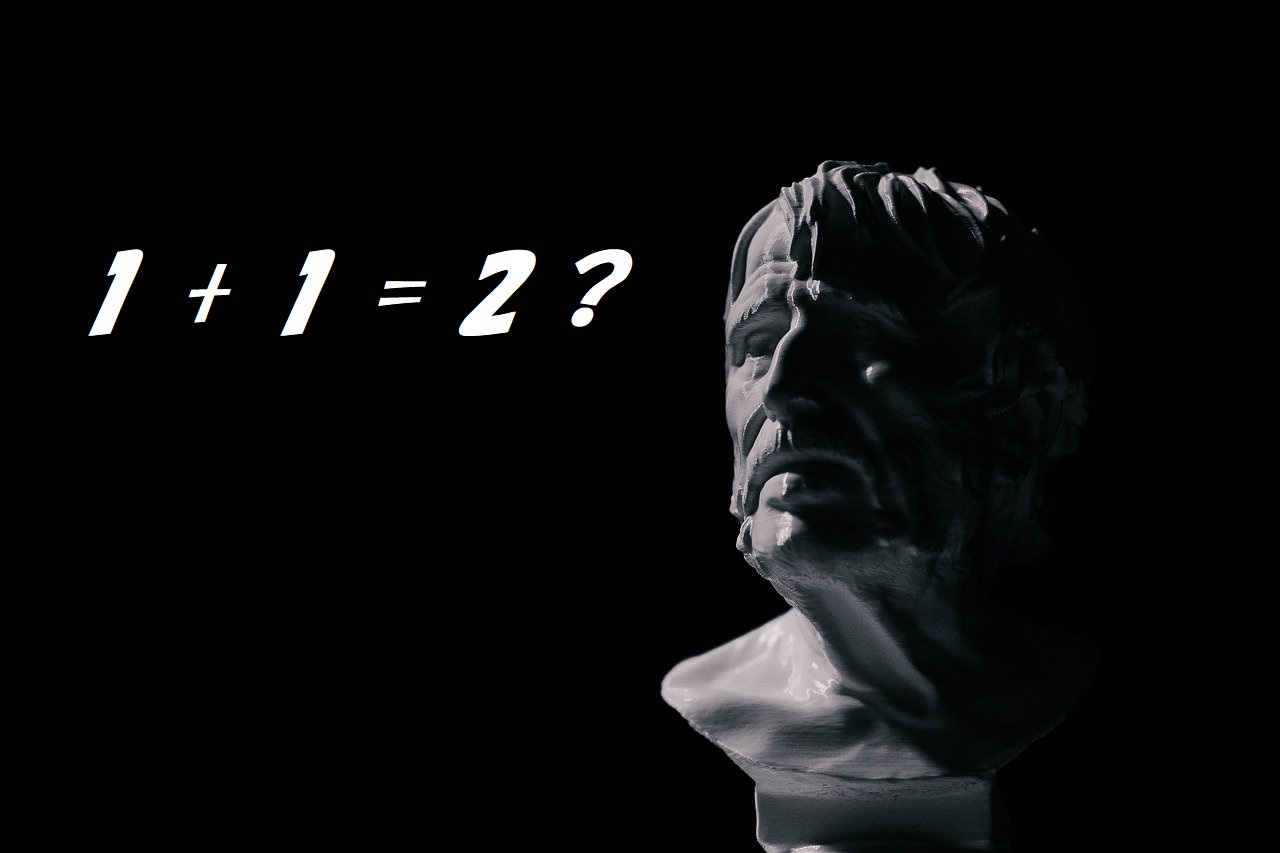


コメント