[adcode]

入不二基義『相対主義の極北』(2001)
[adcode]
相対主義の自己適用化
2001年の著作。
相対主義は相対性そのものを真理として主張する。そのため自己論駁に陥る。本書はこの自己論駁を内在的に極限まで問い詰めた先にどのような思考が立ち現れてくるかを思索したもの。
まず第1章で、相対主義の考え方を六つの局面へと展開するものとして説明している。
1.内在化(超越的な視点の拒否)
2.複数化
3.(相互の)断絶性
4.再帰性(自己適用)
5.相対性と絶対性の反転
6.非-知の次元
相対主義は、以上の六つの局面を経て、最終的に最後の6の段階で懐疑論へと行き着いてしまう。著者は、この懐疑論で相対主義の議論を終わらせるのではなく、相対主義の可能性を相対主義の自己適用を徹底化することで見極めようとする。
相対主義の自己適用から生じる結論は、端的に言って次のようになる。何が真理であるかは認識の枠組みに依存するという相対主義の主張そのものと、その認識の枠組み自体が、永遠に無限後退していくということだ。
ここで相対主義の強度を上げると不可知論へと至り、それはさらに絶対的なものへと反転する。しかし、その絶対性はその極限で相対性へとさらに反転する。こうして相対主義を構成するものとは、「絶対性と相対性の力動的な反転関係」ということになる。
[adcode]
実在論との接続は必要か?
ここまでの議論は(まぁなんとか私でも)ついて行ける。しかし、著者の議論はここから実在論へと移っていく。
実在論には二つの考え方がある。「立ち現われ(現象)」を実在とみなす弱い実在論と現れの背後に認知不可能な実在があると考える強い実在論である。ここで著者は、この強い実在論の極限化と相対主義の自己徹底化が究極的に一致するという。それはどういうことか。
まず、個人主義的な相対主義は、自己の「思い(現われ)」がそのまま真理と重なってしまう。しかし、認識の枠組みによって共同主観的に秩序付けられた「現われ」は安定性を持っている。その意味で相対主義にとっての真理とは、枠組みによって高度に組織化されて安定している「現われ」のことであり、また枠組みによって異なる形をとる相対的なものだ。
ここで「現われ」と「真理/実在」との間の距離という点に関して、相対主義と実在論は同じ構成をとるという。相対主義にとっての真理と実在論にとっての実在は、その距離の取り方という点で同じ問題構成を孕んでいるのだ。
つまり、立ち現われ以前の、実在論における「何もないということさえない」という状況と、相対主義における「想定不可能であるということさえ想定不可能」であるという状態は、人間の認識の到達可能な極限として、一致する。よって相対主義の極北と実在論の極限は一致する。
と、まぁ。。。これが私なりに理解した本書の結論だ。(これは我流の解釈だし、著者の用いていない用語を使って内容を補っていたりするので、あまり正確さについては当てにしないでください。)議論は終始、極端に抽象的であるし、極めてacrobatな展開をするので読み通すのに骨が折れる。
このような議論が当を得ているのかどうかは、私には良く分からない。しかし、実在論と組み合わせて議論する必要性が、どうしても最後までわからなかった。唐突に実在論の議論が登場し、実在論の極限が相対主義と同一であることを証明することに何の意味があったのだろう。う~ん、私は途中から著者の意図を見失ってしまった。。。
だが、相対主義を極限まで問い詰めるという考え自体は、非常に刺激的で面白い。西洋哲学の紹介ばかりやっている日本の「哲学学者」(哲学者ではない)が多い中で、極めて意欲的な作品であることは確かだ。哲学に興味があったら一度はこうした「単なる哲学解説本」ではない独創的な思索を読んでみるのも価値があると思う。

[adcode]


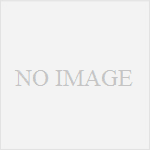
コメント