オギュスタン・ベルク『風土の日本』(1986)
分裂する日本の自然観
晩春のある日曜日の午後、妻と私は戸山町のあたりをぶらついていた。まるで田園にでもいる思いだった。うねうねと曲がる小道、ときおり現われ出る緑、小さな丘、藪で覆われた窪地、切れ切れの空き地……けれどもそこは都市、大都市であった――ひとつの世界である。
p.16
著者のオギュスタン・ベルク氏は1969年に初めて来日し、通算で12年間日本に滞在している。来日当初は新宿高田馬場に暮らした。冒頭に引用した文中の戸山町も新宿区にある。
70年代の新宿はまだ一部の地域に自然を残していたとはいえ、すでに大都市として発展していた。「まるで田園のよう」と表現されている場所も、緑豊かな田舎の風景を指すのではなく、都市という人工的な空間の中にあって、開発されずに「自然な」姿のまま残された地域を意味している。
日本の都市にはしばしば「都市計画の不在」が指摘される。これは西欧諸都市と比較すると、特に顕著である。西欧の都市は、明確な理念と計画に基づいて建設されており、都市空間とは本質的に「人為的な」ものである。そこでは「自然」——すなわち人の手が加えられていないあるがままの姿——は都市から排除された対象となっている。
一方で、日本の都市、特に東京は、都市計画に基づく体系的な発展ではなく、人々の活動に応じて自然発生的に発展してきた。人が集まり、商業が生まれ、それに合わせて交通やインフラが後追い的に整備されていく。こうした過程で形成された東京は、都市でありながらも至るところに「人為性の欠如した空間」が現れる。つまり、計画されず、なすがままに放置されたような場所が存在するのである。
ベルク氏が新宿を歩いて感じた「不思議な感覚」とは、このような都市空間における「自然」の存在だった。大都市の只中に、突如として「人為」が排除されたような空間が現れる。それは決して緑に囲まれた自然ではなく、「なされるがまま」「あるがまま」に放置された、計画性のない空間である。
フランス人であるベルク氏にとって、この違和感は、日本人にとっての「人為」と「自然」の関係を再考する契機となった。
ベルク氏の著書の原題は『野生と人為——自然を前にした日本人』である。本書の主題は日本人の自然観であり、それは人工的・人為的な介入と、非介入的・放任的な姿勢との対比の中で論じられている。
ここで注意すべきは、「自然」という言葉が二つの意味を持っていることである。一つは「緑豊かな自然」という意味であり、もう一つは「なされるがままに任せる」という意味である。
日本人の自然観は、この自然という言葉が持つ二つの意味そのままに、分裂している。
日本の社会が自然を前にして、対照的な対応の仕方を見せるということである。ひとつの観点からすれば、日本の社会は自然を顧みようとしない。つまりあるがままに放置するか、あるいは荒廃させるかの二つに一つである。しかし別の観点から見ると、同じ社会が自然を最高の価値とし、その文化の到達点にしてしまうところまで尊重している。一方には野生の自然、そして他方には人工の極地ともいえる構築された自然。これら両極端とも見える二つのものが、同じひとつの風土(milieu)の内部で、どのように結びついているのだろうか。
p.3
ベルク氏は本書の中で、この奇妙に分裂した日本人の自然観を丹念に読み解いていく。
量産される日本人論の問題点
日本文化には、自然を敬う宗教的・芸術的な側面が色濃く存在する。たとえば、日本では山を御神体とし、海を魂の帰る場所とするなど、宗教観に自然崇拝の要素が見られる。また、日本庭園や盆栽といった芸術分野でも、自然を模倣・再現することに高い価値が置かれている。
しかし、その一方で、自然保護に対しては極めて無関心であると言わざるを得ない。たとえば、1970年代に提唱された列島改造論に象徴されるように、日本は際限ない大型公共事業によって各地で自然を乱開発してきた。そこには、自然崇拝とは矛盾する姿勢が如実に表れている。
とりわけ1970〜80年代は、自然破壊が著しかった時期である。しかし、きわめて皮肉なことに、この同じ時期に「日本の自然観」を称賛するいわゆる「日本人論」が多数登場し、ブームともいえる現象が起きた。
1967年に和辻哲郎の『風土』が岩波文庫で再刊されたのを皮切りに、唐木順三、中根千枝、河合隼雄など、社会学・人類学・哲学・心理学といった幅広い分野の知識人たちが日本文化や社会のあり方を論じ始めた。これらの「日本人論」は、個々には多様な観点を持っていたものの、次のような共通する認識に基づいていた。
すなわち、西欧と日本を二項対立で捉え、西欧社会を「個人主義」、日本社会を「集団主義」と規定する。そして、西欧の自然観は「自然の征服」あるいは「自然との対峙」とされるのに対し、日本の自然観は「自然との調和」とされる。このような図式は論者によって多少の違いはあれど、当時広く共有されていた。そして、この前提の上に、西欧近代がもたらした現代の矛盾や危機を、日本的価値観によって乗り越えようとする、いわゆる「近代の超克」論が展開されることも少なくなかった。
こうした日本人論の中には、示唆に富んだものも存在する。しかし、ベルク氏の視点を踏まえるならば、それらの多くは以下のような根本的な問題点を抱えていたと言える。
- 西欧を一括りにした単純な二項対立による文化理解の粗雑さ
- 印象批評的な軽い筆致による論の展開
- 因果関係の軽率な拡大適用
- 十分な論証を欠いた類比の多用(論理の横滑り)
これらの特徴から、当時量産された日本人論の多くは、厳密な学術的手続きを踏んでいない「印象批評」の域を出るものではなかった。
ベルク氏は、このような印象論的な日本人論に対して批判的立場を取る。彼は、感覚的で曖昧な記述ではなく、操作可能な概念を用いて、体系的な理解を目指した。その中心に据えられているのが「風土」という概念である。
風土とは何か?
ベルク氏の方法論は、構造主義的記号論を彷彿とさせるもので、レヴィ=ストロースの構造人類学に多くの影響を受けていると考えられる。その特徴は、まず説明の枠組みとして明確な概念体系を設定する点にある。
本書においては、「野生(自然)」と「人為(文化)」という対立軸を基盤とし、その中間に位置するものとして「通態(trajet)」という概念を導入する。そして、この「通態」の働きを担い、日本人の自然観を構成する中心的な観念として登場するのが「風土(milieu)」である。
ベルク氏は、「風土」という概念を、分裂した自然観、すなわち野生と人為の二項対立をつなぎ、あるいは統合する媒介として位置づけている。
しかし、日本語の「風土」という言葉は、長い歴史を持ち、多様な意味を内包している。また言外の意味や含蓄(connotation)も多く含んでいて、印象が定まらない。風土の意味を厳密に捉えようとすると、非常に困難な作業とならざるを得ない。
実際にベルク氏は、本書の中で多くの日本文化論を渉猟しながら「風土」という観念の輪郭を描こうとしているが、その全体像は掴みづらく、読者にとって明確に伝わってくるとは言い難い。
フランス語の milieu は、本来「中間」「間」「環境」などの意味を持つ語であり、日本語の「風土」という意味は含んでいない。通態(trajet)に対応する概念として用いられたもので、分裂した自然観の「間(milieu)」を象徴的に結びつけるためのものだろう。
したがって、ベルク氏には、「風土」それ自体の全体像を描こうという意図はないのかもしれない。
それにもかかわらず、なぜ訳語として「風土」が選ばれたのかは重要な疑問である。訳者によれば、この訳語の選定はベルク氏本人の意向によるものとされる。本書は話題が多岐にわたり、フランス現代思想の影響を受けた抽象的で難解な文体が、議論の把握をさらに困難にしている。
とはいえ、ベルク氏が日本人の自然観を、単に分裂したものとしてではなく、ひとつの統一的な観念として捉え直そうとしている意図は、全体を通して伝わってくる。彼は「通態(trajet)」という概念を発展させ、象徴的存在としての「風土」を描くことで、日本文化の深層にある自然との関係性を体系的に理解しようと試みたのだろう。
かつて大量に出版され、次々に消費されていった多くの「日本人論」は、実際には日本の自然観を無批判に称揚する欺瞞的な言説に過ぎなかった。彼らが語った「自然との調和」は、現実には存在しない観念上の理想にすぎず、実際の日本社会は自然破壊に対してほとんど無関心で、「なすがまま」に荒れるに任せていた。
そして、都市の発展は、人為(計画的な開発)は排除され、個々人の好きなように自然(なすがまま)に任された。
日本の都市の無計画性/無秩序性

日本人にとっての自然:都市の中に現れる非人為性
都市計画(人為)が排除されて、地権者がそれぞれ好き勝手に個々の感性だけで街を作り上げていく。なすがまま(自然)に出鱈目に拡大していく都市。

本書は、印象批評的な日本人論とは明確に一線を画す試みである。論述は極めて難解で、理解には相応の読解力と忍耐を要するが、それでも異文化からの視点によって浮かび上がる数々の指摘は非常に示唆に富んでいる。一読する価値は十分にある書である。
オギュスタン・ベルク『風土の日本』(1986)


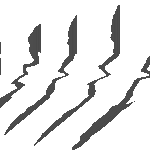
コメント