 哲学談戯
哲学談戯 信仰に裏打ちされた合理性──デカルト哲学の出発点をめぐって – デカルト『方法序説』を読む
デカルト『方法序説』(1637)デカルトと中世──近代哲学の起点は本当に「断絶」だったのか「認識する主体(精神)の発見」「機械論的身体観」「数量化された自然像」── これらは、近代的世界観の根幹をなす概念である。そして、こうした考え方を最初...
 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯 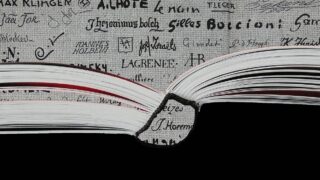 晴筆雨読
晴筆雨読  方々日誌
方々日誌 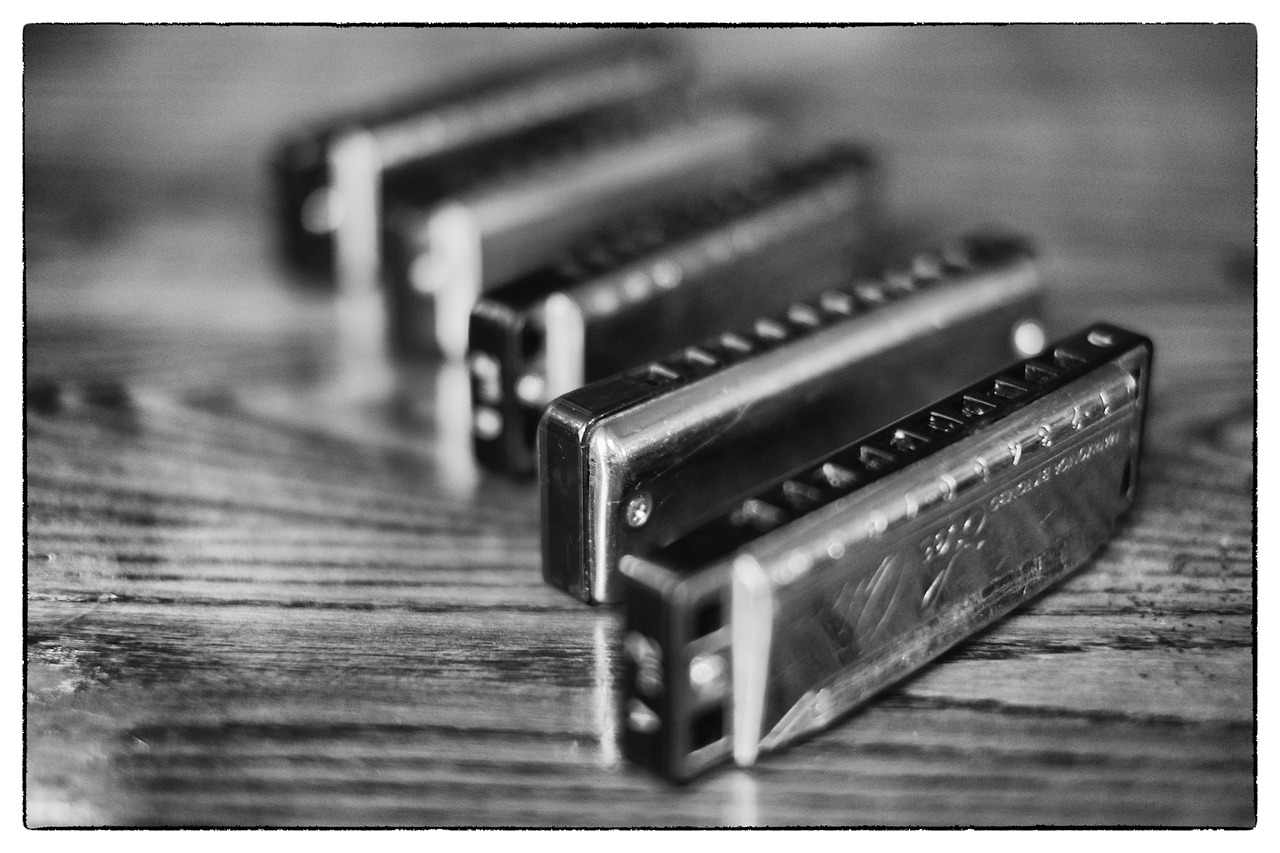 方々日誌
方々日誌 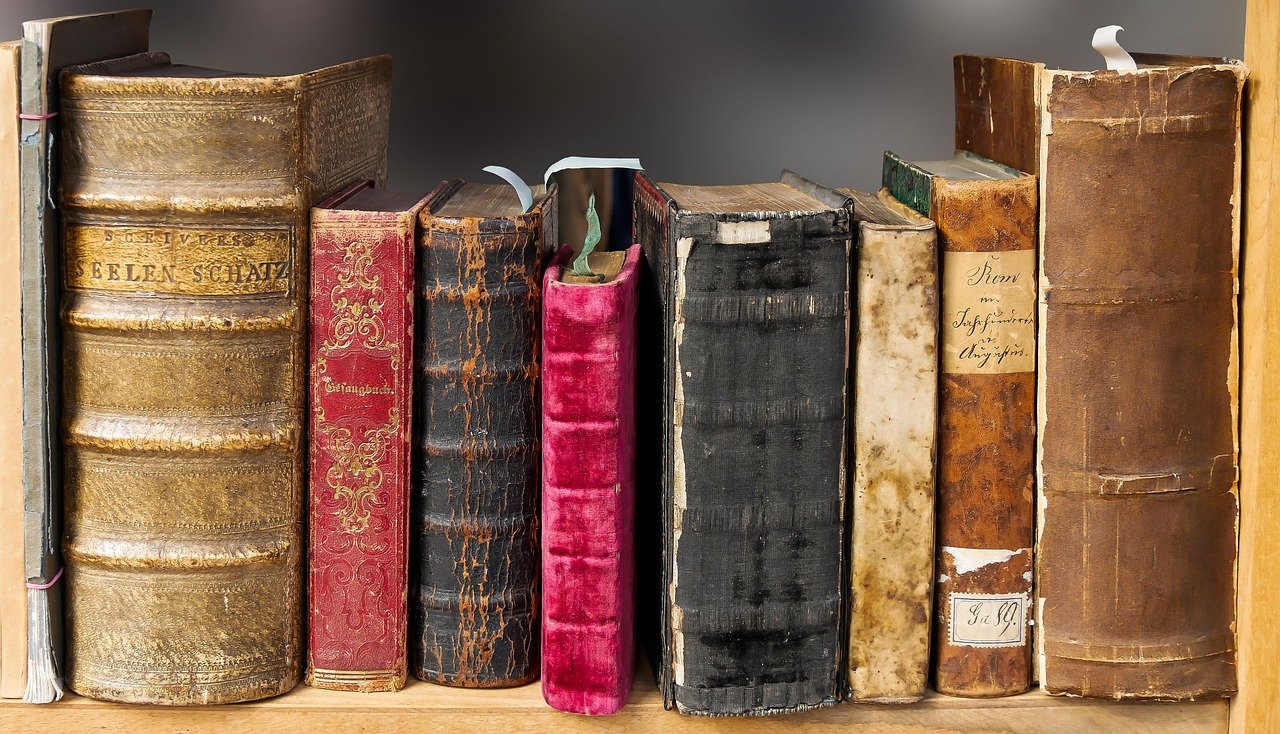 千言万句
千言万句