 晴筆雨読
晴筆雨読 インド思想の源流──〈自己〉を問い直す思想:仏教の誕生と展開
仏教──「自己」を問う思想の転換点 ヴェーダ的宗教思想とその後のブラフマニズムが宇宙と人間の根源的結合、すなわちアートマン(自己)とブラフマン(梵)の一体性を説いてきたのに対し、仏教はその前提そのものを根本から問い直した思想運動である。紀元...
 晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  科学半解
科学半解  科学半解
科学半解  哲学談戯
哲学談戯  科学半解
科学半解 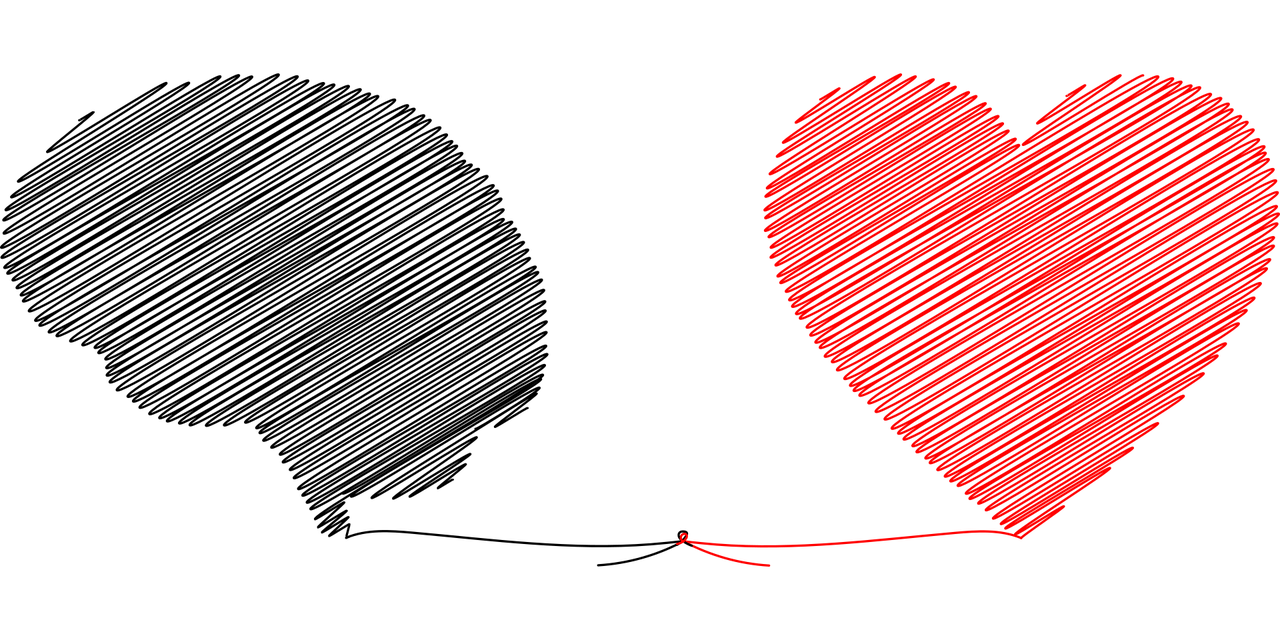 科学半解
科学半解  哲学談戯
哲学談戯