 科学半解
科学半解 近代知への反論 – 中村雄二郎『臨床の知とは何か』
中村雄二郎『臨床の知とは何か』(1992)臨床の知の発見 近代科学は、普遍性・客観性・論理性を中心原理として、現実を対象化してきた。だが、その一方で、こうした枠組みから排除されてしまった「異なる現実」が存在するのではないだろうか。 それを中...
 科学半解
科学半解  科学半解
科学半解 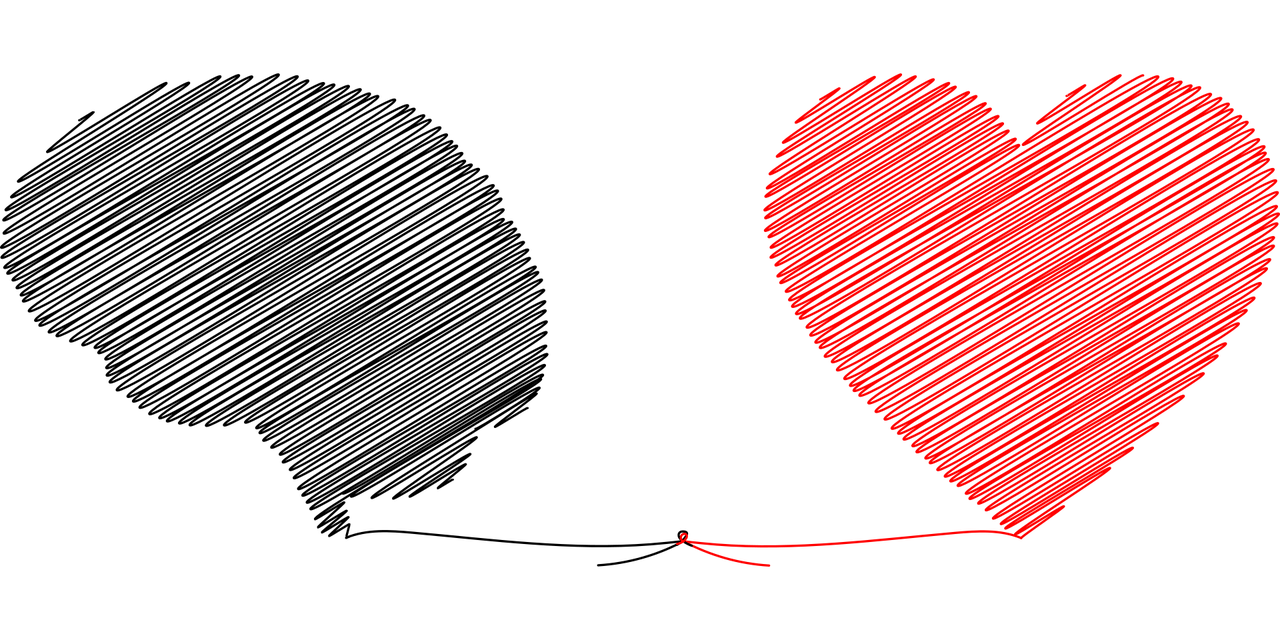 科学半解
科学半解  科学半解
科学半解 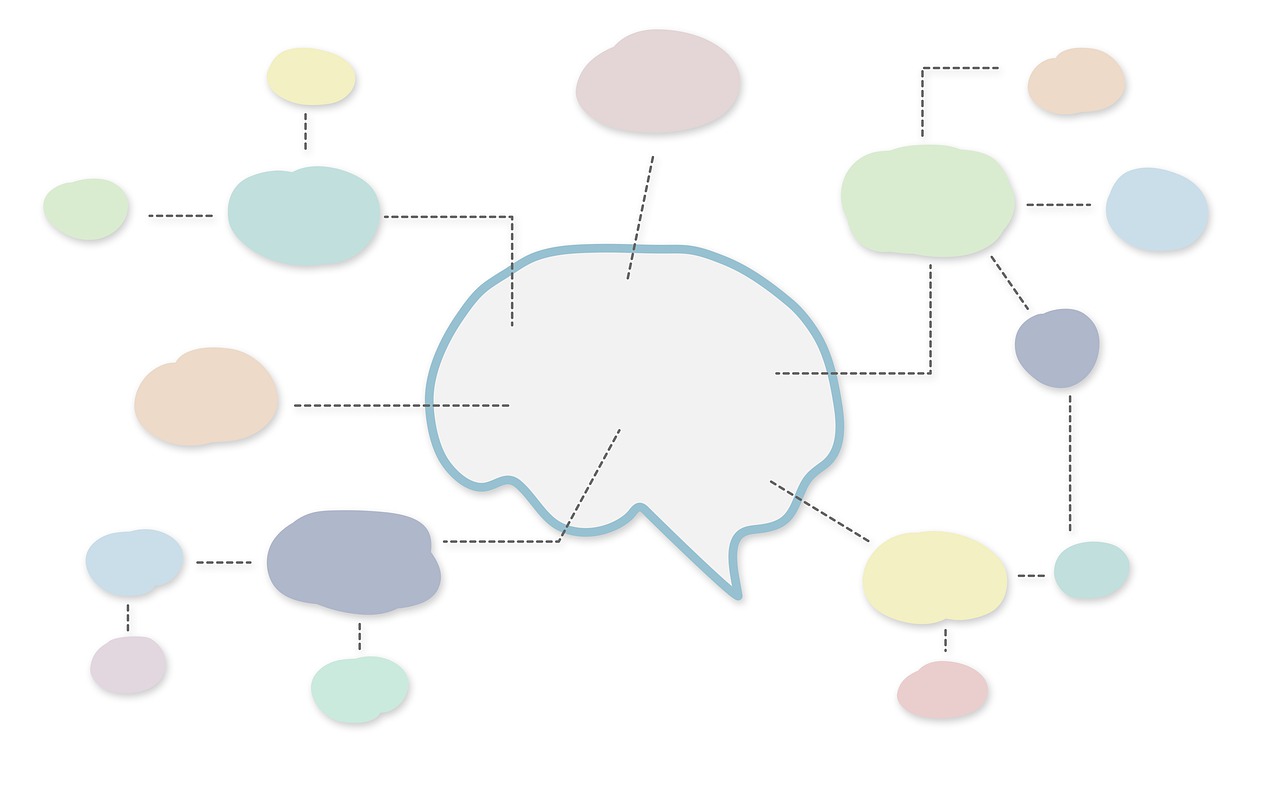 科学半解
科学半解 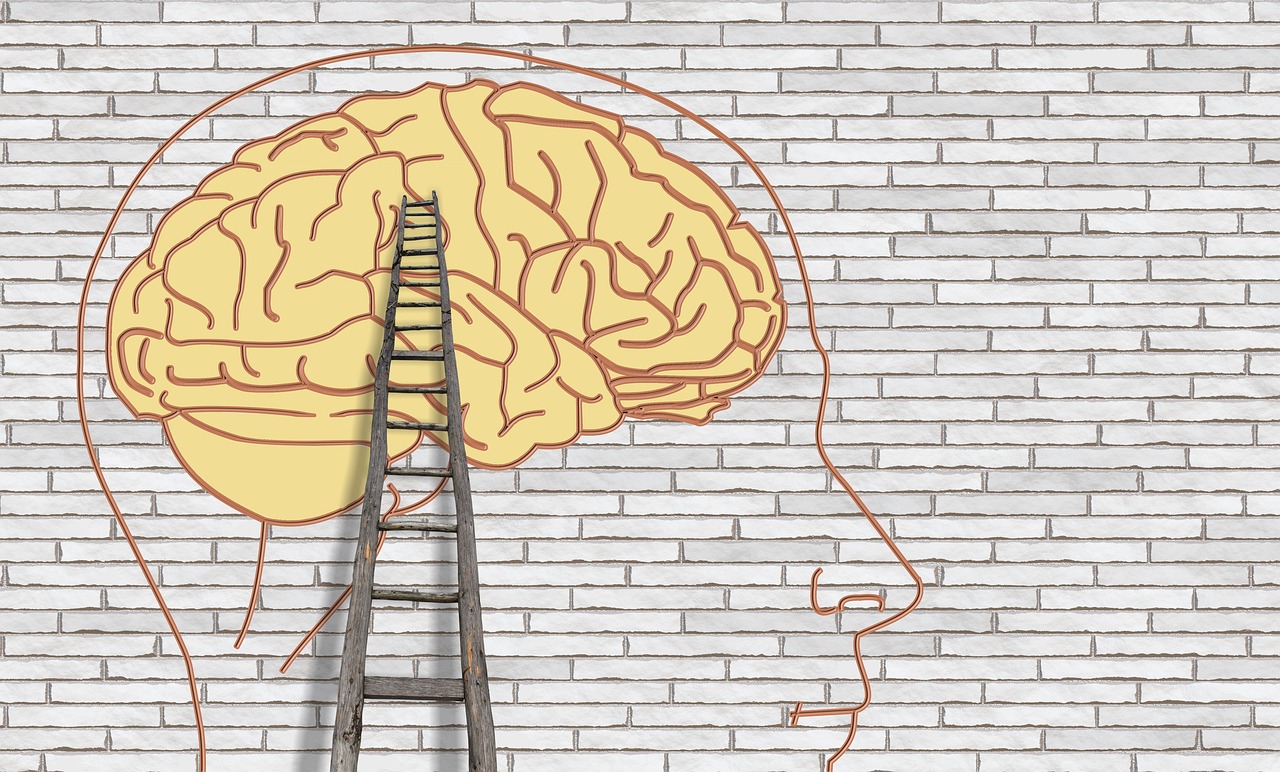 科学半解
科学半解