 哲学談戯
哲学談戯 パスカルとジャンセニスム──『パンセ』に込められた信仰と理性の対話
ジャンセニスムの源流とヤンセニウス ジャンセニスム(Jansenisme)は、17世紀のカトリック教会内部で起こった改革的信仰運動である。その思想的源流は、オランダの神学者コルネリウス・ヤンセン(ラテン語名:ヤンセニウス、1585–1638...
 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯 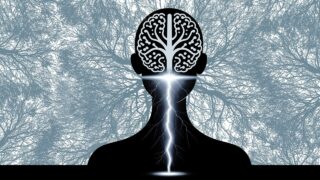 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯