【概略】進化論の進化史(全3回)第2回
ネオダーウィニズムの登場:遺伝学と自然選択の統合
19世紀にダーウィンが提唱した自然選択説は、生物の多様性や適応の過程を説明する強力な理論であったが、当初は遺伝の仕組みに関する知見が不足していた。この理論的空白を埋める形で20世紀初頭から進展したのが、ネオダーウィニズム(新ダーウィン主義)である。
ロナルド・フィッシャーと総合説(1930)
ロナルド・フィッシャーは、1930年の著書『自然選択の遺伝学的理論』において、ダーウィンの自然選択説とメンデル遺伝学を統合し、「進化の総合説」(modern synthesis)の理論的基盤を築いた。
フィッシャーは、生物の形質の変異が遺伝子の突然変異によって生じ、それが環境への適応度(生存や繁殖の期待値)に差をもたらすことを明確に示した。
これにより、自然選択による進化が遺伝学的メカニズムに裏打ちされた過程であることが証明され、ダーウィン以来の理論が再評価されることになった。
集団遺伝学の確立
フィッシャーと並び、J.B.S. ホールデンやセウォール・ライトらが集団遺伝学の基礎を築き、進化を集団内の遺伝子頻度の変化として定式化。
この分野では、確率論・統計学・数理モデルを用いて、自然選択・突然変異・遺伝的浮動・遺伝子流動・隔離など複数の進化要因の相互作用を分析した。
進化は単なる観察的記述から、予測可能で実証可能な自然科学的プロセスとして理解されるようになった。
現代進化論の深化と分子生物学の接続
1940年代以降、進化論は遺伝学・生態学・行動学・分子生物学など、さまざまな分野の成果を取り込みつつ発展し、現代進化論(modern evolutionary synthesis)としての学際的枠組みが確立されていく。
オズワルド・アベリーとDNAの発見(1944)
オズワルド・アベリーらの実験により、遺伝子の本体がDNAであることが初めて示された(形質転換実験)。
これは「遺伝情報がタンパク質ではなくDNAに担われている」という決定的証拠となり、分子生物学の出発点とされている。
この発見は、後のDNA複製・転写・翻訳のメカニズム解明や分子進化学の成立へとつながり、進化の理解は分子レベルにまで深化する。
淘汰の単位をめぐる議論とその意義
進化において「何が選択されるのか(淘汰の単位)」という問いは、自然選択の精緻な理解に不可欠である。1960年代以降、この問いに新たな視点を提示したのが、郡選択説(group selection theory)であった。
V.C. ウィン=エドワーズと郡選択説(1962)
V.C. ウィン=エドワーズは、著書『Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour』(1962)において、アリやハチなどの社会性昆虫が、個体の犠牲をいとわず集団を守る行動を示す点に注目。
彼は、自然選択は個体ではなく集団(群れや種)のあいだで作用すると主張し、「利他的行動」が集団の存続率を高めるという立場をとった。
批判と影響
- 郡選択説は、その後の研究により理論的・実証的な弱点が指摘され、現在では進化の主因とはみなされていない。
- しかし、この議論は、自然選択が働く「単位」が遺伝子、個体、集団、種のいずれなのかという問いを明確化し、進化における利他性・利己性の定義と分析枠組みに大きな影響を与えた。
- 特にリチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』(1976)などに代表されるように、進化の淘汰単位を遺伝子レベルでとらえるアプローチ(遺伝子選択説)が登場し、行動生態学や進化心理学などの新たな領域を切り拓いた。
結語:自然選択の再定義と進化論の展望
ウィン=エドワーズの郡選択説は否定されたものの、その試みは、自然選択の作用対象(淘汰の単位)を厳密に定義する必要性を浮き彫りにした。進化は単に「適応したものが生き残る」のではなく、「何に対して、何が、どのレベルで選択されるのか」という問いが問われるようになったのである。
このようにして進化論は、生物の変化を「なぜ起こるのか」だけでなく、「どの単位で、どのように進化が進むのか」を問う理論へと深化していった。
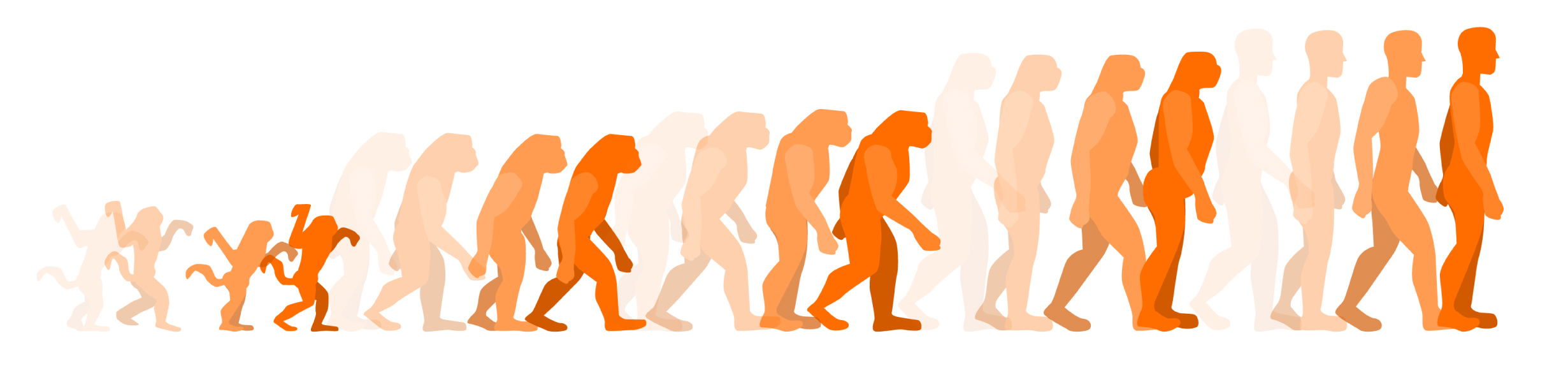

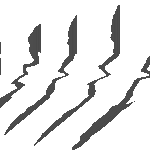

コメント