プラトン『ソクラテスの弁明』(390 BC?)
ソクラテス──「無知の知」と対話の哲学
私は神によってポリスにくっ付けられた存在なのです。大きくて血統はよいが、その大きさゆえにちょっとノロマで、アブのような存在に目を覚まさせてもらう必要がある馬、そんなこのポリスに、神は私をくっ付けられたのだと思うのです。その私とは、あなた方一人ひとりを目覚めさせ、説得し、非難しながら、一日中どこでもつきまとうのをやめない存在なのです。
ソクラテスは、自らの思想を伝えるための学園や教壇を設けることはなかった。彼の舞台はアゴラや競技場などの公共空間であり、通りすがりの人々との自発的な議論こそが、彼の哲学の実践の場であった。他のソフィストたちのように、有力者の子弟を対象に高額な報酬を受け取ることもせず、誰に対しても分け隔てなく、対話を通じて問いを投げかけていった。
彼の対話の特徴は、後に「無知の知」として知られるようになる独特の方法論にあった。ソクラテスは、相手の前提や論理の矛盾を鋭く突き、相手が「知っている」と信じていることが、実は無自覚に受け入れられた曖昧なものであることを露呈させた。それは言葉の定義や使い方への無自覚さを相手に問い直させ、その本来的な意味をあらためて探究させる手法である。
このような思考と対話の実践は、ソクラテスをアテナイ市民の間で一躍有名にし、「知者」としての評価を受けるきっかけとなった。彼の問いかけによって、自分の知の限界を自覚させられた人々は、言葉の意味をあらためて問うという知的営みに驚きと関心を抱くようになったのである。
ソクラテス自身も、こうした対話が人々にとって意味あるものであると確信していた。『ソクラテスの弁明』の中で、彼はこう語っている。
では一体なぜ、人々は私と共に喜んで長い時を過ごすのでしょう。あなた方はすでに聞いています、アテナイの皆さん。真実のすべてを私はあなた方に語ったのです。つまり、知恵があると思っているが実際はそうでない人々が吟味されるのを、彼らは喜んでいるのです。実際、それは不快な経験ではありません。
知的好奇心に満ちた者にとって、ソクラテスとの対話は極めて刺激的な経験であったに違いない。だが、すべての人がそのような知的動機で議論に加わったわけではない。ソクラテスの対話は誰にでも開かれており、いわば「公開討論」のような形をとっていた。そのため、論難された側が名誉や体面を損なわれたと感じ、反感を抱くこともしばしばあった。
このような背景から、ソクラテスは「知者」として称賛される一方で、「皮肉屋」あるいは「とぼけた男(知っているのに知らぬふりをする)」といった批判も受けるようになる。劇作家アリストファネスは、喜劇『雲』の中で、人々を煙に巻く詭弁家としてのソクラテス像を戯画化し、当時の一般的な風評を風刺的に描いている。
こうしてソクラテスに対する評価は、アテナイ市民の間で賛否に大きく分かれた。しかし、ソクラテス自身は、自分の使命は人々に「無知の自覚」を促すことにあると確信していた。それは、デルフォイの神託──「ソクラテス以上の知者はいない」というアポロン神の言葉──に裏打ちされた信念でもあった。
彼は自らを「アブ(虻)」になぞらえた。つまり、ソクラテスにとって自分の存在とは、巨大で鈍重な馬──すなわちアテナイというポリス──に対して、不断に目覚めを促し、刺激を与える役割を果たすものであった。
だが、この信念と行動の徹底こそが、やがて彼自身を危機に陥れることとなる。自己批判、自己検証を相手に促すソクラテスの哲学は、その知的挑発性ゆえに、社会的にも政治的にも大きな緊張を生むものだったのである。
ソクラテス裁判の背景
前399年、ソクラテスは、保守派の政治家アニュトスによって、不敬神の罪で告発された。この時、ソクラテスは、70歳を迎えていた。
告訴状は、次のような内容だったと言われている。
「ソクラテスは、ポリスの信ずる神々を信ぜず、別の新奇な神霊(ダイモーン)のようなものを導入することのゆえに、不正を犯している。また、若者を堕落させることのゆえに、不正を犯している」
この告訴状の内容に意味はないだろう。ソクラテスが告発された理由は複合的なもので、政治的な背景と文化的な文脈、そして、ソクラテスの個人的資質、といった三つの要因があったと思われる。
まず、政治的な背景として、ペロポネソス戦争敗戦後のアテナイの政治的混乱がある。前404年に親スパルタの三十人政権が成立したが、この政権はわずか1年で民主派によって打倒された。民主派による政権奪取以降、三十人政権に関わった者たちへの弾圧、迫害が続いた。
三十人政権の首謀者であるクリティアスは、ソクラテスの下で一時期学んでいる。アテナイ市民からは、ソクラテスの弟子と見做されていた。そのため、ソクラテスへの告発もこの三十人政権関係者への弾圧の一環だったといえる。
また、文化的な要因としては、ソフィストという新たに登場してきた知的職業に対する保守派からの反発があった。ソフィストとは、討論や説得の技術を教えることを生業とした職業知識人たちであった。民主制が成熟したアテナイには、ギリシア各地からソフィストたちが訪れ、自らの弁論術を売り込んでいった。
彼らの弁論術を学ぶために、多くの有力者の子弟が大金を支払ったという歴史的事実からは、アテナイの民主制がいかに成熟し、議論による説得を重視していたかが分かる。これは、自らの弁論の力、つまり、実力によって政治を変えることができたということを示している。意欲のある若者は、この弁論術に熱狂した。
当然、こうした実力主義は、保守派層、既得権益層に危機感を抱かせた。プラトンは、のちの著作である『メノン』の中に、ソクラテスの告訴を行ったアニュトスを登場させ、ソフィストと呼ばれる連中は、どのようなものであれ、国家に対する害悪だと語らせている。ソフィストの弁論術とソクラテスの思想は全く異なるものだったが、彼らのような自らの知恵と知識によって社会に影響力を持つ存在は、保守派層、既得権益層に一様に危険視されていた。ソクラテスに対する告訴状の中の「若者を堕落させる」という言葉には、保守派層のソフィストへの反感と恐れが読み取れる。
そして、最も重要な要因は、ソクラテス個人の資質だろう。ソクラテスは、アテナイの一般市民からはソフィストの一人と見做されていたが、ソクラテスの活動は、明らかに他のソフィストたちとは異なっていた。
知識を売るということをせず、弁論の技術を教えることを生業にしていないこと。純粋に対話のための対話を公共という開かれた場で行い、相手の無知を気付かせ、社会を啓蒙することを信条としていること。
このようなソクラテスの特異な信条と思想は、哲学的な探究心に富んだものたちへ非常な感銘を与え、多くの弟子を生んだ。
実際、ソクラテスが刑死したのち、ソクラテスを擁護し、その思想を伝えるための多数の著作が現れる。クセノフォン、アイスキネス、パイドン、アンティステネス、アリスティッポス、エウクレイデスなどの支持者たちが、ソクラテスを主人公とした対話形式の作品群を残した。 ソクラテスの思想が当時においてもいかに特異なものであったのかが分かる。
そして、こうした「ソクラテス文学」の最高峰に位置しているのがプラトンである。
ソクラテスが持っていたこのような特異性と名声──
権力に固執する者たちにとって、彼の異質さそのものが脅威として映ったのだろう。
プラトンの描くソクラテス
プラトンが『ソクラテスの弁明』で描いたように、ソクラテスは、死を恐れず、魂にのみ配慮すべきことを滔々と説く。そして、最期は、判決に従い、従容として死についた。
『ソクラテスの弁明』は、プラトンの初期対話篇に位置付けられる作品だ。書かれた正確な年代は不明だが、プラトンの信条や思想の発展形式を考えると、プラトンが一番最初に書いた作品なのではないかという気がする。
プラトンの初期対話編は、相手の矛盾と思考の不徹底さを鋭く抉り出すソクラテスの対話の手法が多く主題とされている。この『ソクラテスの弁明』においても「若者を堕落させる」という告発に対して、それが論理的に成立しないことを鮮やかに証明して見せるソクラテスの姿が描かれている。
プラトンは、この作品でソクラテスの対話の手法を描く一方、その他の部分では、ソクラテスの「知」に対する態度を多く取り上げている。ポリスという社会と個人の魂に対して誠実に生きることを説いた人格者としてのソクラテスに主に焦点を当てているのだ。ソクラテスの思想や哲学を伝える前に、まずは人としてのソクラテスを伝えようと、プラトンは意図していたように思える。その意味で『ソクラテスの弁明』は、ソクラテスの思想や哲学の革新性以前に、人格者としてのソクラテスが、弟子のプラトンにとって、極めて特異で、重視するべきものとして映っていたことを示している作品だといえるだろう。
著作を一切残さなかったソクラテスの思想は、プラトンによる「ソクラテス文学」によって後世へと伝えられていった。まず初めに自己の魂に向き合う人格者としてのソクラテスを取り上げ、彼を刑死へと追いやり、知的文化を失わせたアテナイ民主制へ警鐘を鳴らしたプラトンは、そこからソクラテスの口を借りて失われた知的遺産を取り戻すことを企てたように思える。そして、この試みこそが、西洋哲学の基礎へと発展していくことになるのだ。
引用
プラトン『ソクラテスの弁明』(光文社古典新訳文庫)より



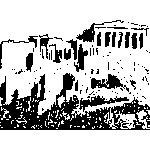
コメント