渡邊二郎・西尾幹二編『ニーチェを知る事典』(2013)
ニーチェにおける精神の軌跡とその悲劇
本書は、1980年に刊行された書籍の文庫化であり、文庫本ながら約800ページに及ぶ文字通り大著である。
ニーチェの専門家だけでなく、多様な分野の研究者50名以上が執筆に携わっており、さまざまな視点からニーチェの思想や人物像に迫っている。扱われる主題も幅広く、各記事は比較的短いため、見た目の重厚さとは裏腹に、意外にも読みやすい。
辞典形式であるため、関心のある項目から自由に読み進めることができるが、私は最初から最後まで通読してしまった。それだけ読み続けさせる力のある、飽きのこない内容であると思う。
本書が提示するニーチェ像は多様であり、一面的な理解にとどまらない。しかし私が特に強く惹かれたのは、若き日のニーチェに見られる「学術的精神」であった。それは、彼の内にあった哲学的情熱と科学的精神との緊張関係を象徴している。この二つの精神の均衡をいかに保つか──本書を読み進める中で、その困難さを深く考えさせられた。
私見では、ニーチェの悲劇は、まさにこの均衡を失ってしまったことにある。哲学的直観に傾きすぎ、かつて持っていた冷静で学問的な態度を手放したことが、後年の孤立と誤解を招いたのではないか。本書は、そのような問いを抱かせるに十分な資料と論考を提供している。
文献学者ニーチェ
ニーチェと言えば、体系的な思考を嫌い、断片的な文章の積み重ねの中から自己を表現したアフォリズム(aphorism)の作家、という印象が強い。フランスのエスプリに傾倒し、反時代的、反ドイツ的な異端の思想家、しかし、その立場ゆえに、かえって後年、彼をして近代批判、現代思想の源流へとならしめた。。。そんな印象だろうか。
しかし、彼の学問的業績は、まず古典文献学から始まっている。
彼が哲学者ショーペンハウアーに傾倒したのは1865年、21歳のときである。下宿近くの古本屋で偶然手に取った『意志と表象としての世界』に衝撃を受け、「デーモンが耳元でこの本を持って帰れと囁いた」という逸話は、あまりにも有名だ。
しかし、その深い感銘の直後に彼が取り組んだのは、哲学的な著述ではなく、ギリシャ古典に関する原典批判であった。彼はテオグニス、スイダス、ディオゲネス・ラエルティオス、アリストテレスといった古代の著作を対象に、徹底して客観的かつ実証的な研究を行っている。
哲学的情熱に突き動かされながらも、冷静で客観的な態度を要する厳密な科学的作業に没頭できた点に、彼の非凡さがうかがえる。
このような知的態度は、実のところ、容易なことではない。客観的な原典批判の力を備えないまま、哲学の真似事のような文章に耽り、稚拙な思想に酔って自己の成長を止めてしまう若者は少なくない。ニーチェはそうした落とし穴を避け、文献学という科学的学問の形式に則って、地に足の着いた学究生活を始めた。
しかし、若い頃に、ショーペンハウアーの厭世哲学から受けた最初の衝撃は、彼を激しい情動に突き動かし続けていたのかもしれない。兵役のために大学から一時離れた1867年頃から、彼は学者としての生活と並行して、自由な著述家として生きる夢を抱くようになっていったと言われている。
文献学とは、文書という検証可能な証拠のみに基づいて過去を再構成する学問である。その意味で、当時の文献学界では、「行間を読む」ような解釈は、非科学的として避けられるべきものとされていた。とくに人間精神の深層──無意識や歴史(時代精神)からの影響といった、文書には表れにくい次元──に踏み込むことは、学問としての正当性を疑われる行為だった。
だが、ニーチェとってそれは、むしろ近代的学問の欠点として映った。彼は、文献に対する厳密な分析を出発点としながら、そこからは汲み取りきれない古代ギリシャ精神の全体像を、創造的に再構成しようとした。その試みの成果が、1872年に出版された『悲劇の誕生』である。
この著作においてニーチェは、古代精神を「アポロン的精神」と「ディオニュソス的精神」という二つの象徴的概念の対立として描き出した。理性と秩序を体現するアポロン、情熱と陶酔を象徴するディオニュソス──この二つの力の緊張関係こそが、古代ギリシャ悲劇の本質であるというのが、彼の大胆な主張だった。
だが、その結果は悲惨なものだった。この作品は文献学の世界ではまったく受け入れられなかった。厳密な実証性を重んじる学界にとって、ニーチェの「再構成」は、根拠に乏しい恣意的解釈と映ったのである。ニーチェはこの一作によって、文献学者としての地位を完全に失うことになった。
哲学者ニーチェとしての歩み
1872年、『悲劇の誕生』を刊行した28歳のニーチェは、この頃から闘病と放浪の生活を送るようになる。しかし、一方で、この生活は、大学という制度的枠組みから離れ、自由な著述活動に専念できる機会ともなった。
『悲劇の誕生』に続いて彼が取り組んだのが、1873年から76年にかけて執筆された『反時代的考察』である。この著作ではすでに、「生」の概念を手がかりに、現代の思想や文化の堕落に対する痛烈な批判が展開されている。ここにこそ、哲学者としてのニーチェの歩みの第一歩が見て取れる。以後の彼の営みは、近代ニヒリズムとの格闘であり、その意味で『反時代的考察』は、後の現代思想家ニーチェの誕生を告げる書でもある。
その後ニーチェは、1870年代後半を通じて、ドイツ、スイス、イタリアなど各地を転々としながら、執筆活動に没頭していく。そして1882年、彼の思想的転機を象徴する事件が起こる──ルー・ザロメとの出会いと失恋である。
ルー・ザロメ事件───
ザロメと親友パウル・レーとの三角関係のもとで試みられた奇妙な共同生活は、すぐに破綻を迎える。この精神的打撃の直後、ニーチェはわずか10日間で『ツァラトゥストラ』第1部を一気呵成に書き上げてしまう。この事件がニーチェの内面に与えた衝撃の大きさは想像に難くないが、むしろその不安定な精神状態こそが、形式や伝統、学術的枠組みから解き放たれた自由な思想表現を可能にしたのではないかと思われる。
他に類例を見ない希代の名著『ツァラトゥストラ』はこうして書き上げられた。もうそこには、厳密な科学的態度を追及する文献学者としての精神も、『反時代的考察』に見られた世間に自らを認知させるための批評家的な態度も全くなかった。
若い頃に受けた哲学的な感興を、今は思うまま自由に述べる姿だけがあった。
理想を語る情熱と、事実を観察する科学的精神 ― ニーチェの精神史から考える
1889年、ニーチェは精神の均衡を失い、以後の10余年をほとんど廃人の状態で過ごすことになる。この壮絶な晩年を含む彼の精神史をあらためて振り返ると、学術的・科学的な冷静さと、哲学的・理想主義的な情熱とのあいだで、彼がいかに困難な均衡を求め続けたかが浮かび上がってくる。
25歳でスイス・バーゼル大学の教授に就任し、将来を嘱望されていたニーチェには、本来であれば学会における堅実な業績を積み、安定した地位と豊かな社交生活を享受する道も開かれていた。しかし、彼の内面に宿る激烈な精神は、そうした「無難な」生き方を拒み、あえて孤独な思想の道へと自らを導いた。
歴史学者ヤーコプ・ブルクハルトは、ニーチェと親交を持ちながらも、その過激な思想と行動を案じていた。ブルクハルトが『ツァラトゥストラ』を読んで、「これを戯曲にしてはどうか」と提案したという逸話は、彼の深い懸念を物語っている。ニーチェが学問的態度から逸脱し、まるで宗教的預言者のような振る舞いを見せ始めていたことに、彼は危機感を抱いていたのだろう。
激情に駆られた思想は、時にその担い手を破滅させ、読者をも誤った方向へ導きかねない。ブルクハルトの危惧は、実際に現実となった。ニーチェ自身は精神の破綻に追い込まれ、彼の思想はやがてナチズムに利用されるという、皮肉な運命をたどった。彼が理想とする古代ギリシャ精神——理性の象徴であるアポロン的精神と、陶酔と情動の象徴であるディオニュソス的精神——の緊張関係を語ったその本人が、最終的にはディオニュソス的情熱の中に沈んでいったかのように見える。
しかし、それでもなお、ニーチェのように理想と情熱を貫こうとする精神は、いかなる時代においても希少で、貴重な存在である。ニーチェの生涯は確かに悲劇的であったが、そのような精神の激しさゆえに、彼は歴史に消えることのない痕跡を刻んだ。
現代において、学問の方法論はすでに制度化され、確立している。一定の手続きに従い、指導に忠実でさえあれば、形式的には立派な学術論文を仕上げることができる。だが、そのような「正しい」論文の中で、歴史に残るほどの意味を持つものは、果たしてどれほど存在するのだろうか。
情熱なき学問が溢れる現代において、ニーチェの精神はまさに「反時代的考察」の象徴である。その激しさと誠実さゆえにこそ、今なお我々に問いを突きつけ続けているのである。
渡邊二郎・西尾幹二編『ニーチェを知る事典』(2013)


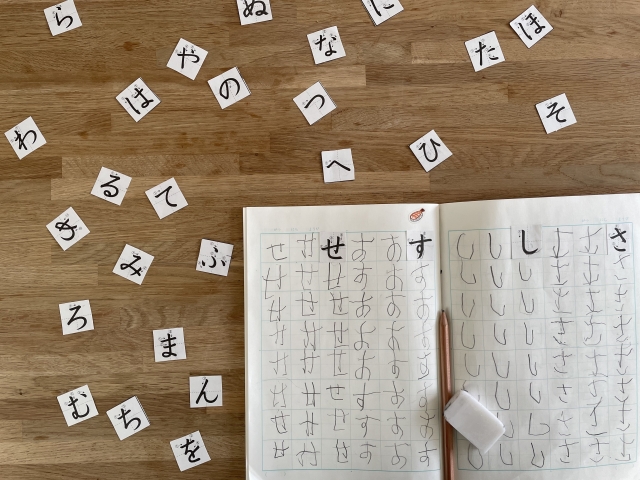
コメント