村上陽一郎『近代科学を超えて』(1986)
科学における経験的事実への懐疑
近代科学は、実験と観測的事実の積み重ねによって発展してきた―――
これは多くの人が抱く科学的知識に対する通念だろう。だが、実は、近代科学の歴史を詳細に検証してみると、信念、あるいは時によっては、信仰によって理論が構築され、それが多くの歴史的な科学的事実の発見へとつながっている。
初期の著作『科学・哲学・信仰』において、近代科学の根底に横たわる「信仰」がその発展に寄与してきたことを示した村上氏だが、この著作では、経験主義や実証主義に基づく観測的事実の積み重ねよりも、理論の構築が科学の発展において重要であることを歴史的事実を踏まえながら解き明かしている。
事実の理論負荷性
近代科学が誕生し、それが発展する最初の契機となったのは、16世紀に成立した経験主義に基づく即事実性の態度である。13世紀の哲学・自然学者ロジャー・ベーコンの実験哲学の理念が16世紀のフランシス・ベーコンによって方法論的に確立されたことによって成立した。思弁と訓詁学的な注釈が正統と見なされていた当時、過去に書かれた権威ある書物にではなく、自然に直接問いかける態度は、近代科学が成立する過程において一度は確立されなくてはならないものであった。
だが、科学的事実の発見が、理論に基づかない闇雲な実験や観測から得られるということは、およそ起こらない。理論的仮説を前提にして、それを通じて現象を観察した時、科学的な事実が発見されるのである。
たとえば、ニュートンの万有引力の法則をその例にとってみよう。ニュートン力学の根幹をなす最も基本的な理論は、二つの物体の間に働く力は、両者の距離の2乗に反比例するという「逆2乗の法則」である。だが、実験結果として得られる数値がこの法則を満たすものであることはほとんどない。
そもそも、逆2乗の法則は二体問題として定立されている。しかし、現実の経験的世界に純粋な二体問題として解けるような関係など存在していない。この二体間関係は理論的に抽象化された存在であり、実際の経験的世界では、無数の存在が複雑系を形成しており、逆2乗関係が正確に成り立っているような二体はあり得ない。したがって、観測によって得られる実験値が、正確に逆二乗の関係を指し示すこともまたないのである。
この理論には、自然界が簡潔で美しい法則に支配されているという無邪気で純粋な信念がある。経験的世界を表す数値的関係が、複雑な分数や無理数にならないという単純性への信頼である。
これはほんの一例に過ぎない。近代科学では、しばしば理論が観測的事実を生んでいるのである。
なぜ日本に近代科学は生まれなかったのか?
宗教より実利を、理念より経験を重視する日本の伝統的な思考態度は、一見すると「経験主義」のようにも見える。だが、日本の「実学」と西欧の「経験主義」とは似ても似つかないものなのである。
コツによる会得を身上とする日本の科学技術のあり方には、経験主義的な傾向を強く見て取ることができる。江戸時代初期、幕府に仕えた林羅山が林派を形成し、理論的傾向の強かった朱子学を官学化させたが、学問として日本に根付くことはなく、特に民間ではすぐに古学が復興し理論偏重への反省が起きた。
特に医学における分野では、理論偏重の態度は忌避され、古学の復興が目覚ましかった。医学における古学は「古医方」と呼ばれ、陰陽五行説に基づく判断より診察による腹診を重視した。古医方の第一人者、吉益東洞は、臨床を重視し、自ら試すことを旨とする「親試実験」を繰り返して経験的な知の蓄積に励み、その知に基づいて実践的な外科手術を行った。東洞の思想は極めて実証主義的である。
だが、彼の実証主義は極端なもので、経験を重視するあまり、理論やそれに基づく仮説を認めなかった。蘭医方に刺激された山脇東洋が日本で初めて本格的な解剖を行ったところ、東洞は、生体の常態を解剖という人為的干渉によって知ることは不可能だと解剖の意義を退けた。観察することから理論的仮説を導く、という発想に欠けていたのである。当然、このような実践的経験しか認めない実証主義は、科学の発展に対して不毛であった。
こうした事実が示しているのは、科学的な事実と呼ばれているものが、経験にではなく理論に負っているということである。これは科学の理論負荷性と呼ばれている。
科学は、経験的な事実に先立つ思考によって理論的仮説が立てられ、その理論に支えられている。観測的、実証的事実だけを積み重ね、事実に直接的に密着しようとするところには科学の体系は生まれない。事実は理論に依拠している。自然現象に対して運動、質量、速度という「概念枠」を通して眺めるからこそ、それらに準拠した「事実群」が得られるのである。
日本では、この理論に対する思想的基盤が脆弱だったのである。
17世紀の科学革命
17世紀は、科学革命と呼ばれる科学史における一大変革が起きている。この時代を機に、物理学、医学、化学が飛躍的な変貌を遂げるのだが、科学の変革はまず、宇宙像の転換として始まった。
天動説から地動説へ―――この宇宙像変遷の中心人物となったのは、コペルニクス、ケプラー、ガリレイ、ニュートンの4名である。この宇宙像の変遷は、単に天体運動の計算方法や観測方法の変更にとどまらず、当時の力学、物理学の転換も伴った。
再現可能な方法によって、誰でも追従実験ができるようにし、開かれた公開の場で自説の正しさを主張する、という方法がとられはじめたのもまたこの時代からである。
だが、この時代の科学革命は現代的な科学思想とは根本的に異なる発想の下で進展した。キリスト教の世界創造神話に基づく合理的世界秩序への信頼が、科学革命の背景には存在していた。15世紀のフィレンツェでメディチ家を中心に隆盛した神秘思想の一種である新プラトン主義の影響も大きかったと言える。それは、宗教的、哲学的信念が契機となって起きたのである。
ルネサンス期の科学革命にはまだ宗教の影が色濃く残っている。科学が脱宗教化し、現代科学にまで発展するには、科学思想の脱擬人化、価値中立化を経なくてはならなかった。18世紀において百科全書派を筆頭にキリスト教的宇宙観からの解放、すなわち聖俗革命を経て、19世紀に至り、ようやく今日の無神論的力学的世界観、近代科学としての体裁が整うのである。
では、17世紀の科学革命は、実際、どのように展開したのだろうか。本書の記述に沿ってまとめてみよう。
宇宙像の転換は、ニコラウス・コペルニクス(1473-1543)によってはじまる。コペルニクスはそれまで絶対的な権威であったプトレマイオスの天動説を退け、地動説を主張した。だが、コペルニクスは地球中心体系から太陽中心体系へと必然的に転換を強制するような観察的事実を持っていたわけではなかった。コペルニクスにこの転換を行うに至らせたのは、観察的事実ではない。その一つは、ネオプラトニズムであり、もう一つは、アリストテレス以来のドグマである一様な円運動という観念であった。
コペルニクスは、新しい観測的事実を利用して地動説(太陽中心体系)を提唱したわけではなかった。プトレマイオスの天文学理論は、2世紀に行われた天体観測に基づいて形成された。16世紀のコペルニクスの時代に観測され、知られていた天文学上の事実群は、プトレマイオス説によっても、コペルニクス説によっても全く同じ程度に十全に説明することができたのである。つまり、コペルニクスは、地動説を証明したのではなく、地球中心体系を証明するその同じ観測結果を用いて、それを太陽中心体系へと読み替えたのである。同じ事実を用いて、その解釈だけを変えたのだ。
理論体系と観察値との間に整合的な関係が保たれなくてはならないのは言うまでもない。だが、整合的な関係に対する解釈が、必ずしも一義的に決まるとはいえない。この解釈の差が、天動説と地動説の差を生んだ。プトレマイオスとコペルニクスとの間にある価値観、概念的枠組みの違いが、理論と観測との間の関係に対する解釈の違いとなって現れた、とも言える。
ヨハネス・ケプラー(1571-1630)は、自然の秩序と数学の規則性を同一視する点で、ピュタゴラス的伝統の忠実な継承者であった。彼は、数を宇宙の秩序の中心とし、天体の調和を音楽として捉えていた。自然哲学における数理主義者だった。
ケプラーの功績は、数学的な裏付けを持った物理モデルを提出するという方法の先駆者だった点にある。数理モデルによって、コペルニクスやティコ・ブラーエ、ガリレオ・ガリレイも脱却できなかった円運動に基づく天体論から、楕円運動を基本とする天体論を唱え、近世自然哲学を刷新した。彼のモデルそのものは誤っていたが、結果的にこれはガリレオ・ガリレイ、アイザック・ニュートンを経て古典物理学の成立へとつながっていく。
ただしケプラーの数学的裏付けは、まだ合理性において不十分なものであった。ケプラーの理論には、数の調和という思い込みによる予測が様々な面においてみられるのである。
ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)は、科学分野で実験結果を数学的に分析するという画期的手法を創造した。彼以前にはこのような手法はヨーロッパには無かった。さらにガリレオは科学の問題について教会の権威やアリストテレス哲学に盲目的に従うことを拒絶し、哲学や宗教から科学を分離することに寄与し、科学の父と呼ばれることになる。しかしそれゆえに敵を増やし、異端審問で地動説を捨てることを宣誓させられ、軟禁状態での生活を送ることになる。
アイザック・ニュートン(1643-1727)は、古典物理学の完成者として知られる。古典力学では、この自然界に生起するすべてに現象は、質量を持った点、質点とその運動に還元できるのであり、同時にその運動は一義的に決定できると考えられる。そのため古典物理学は、そこから逸脱するのは量子力学と相対性力学が現れるまで、物理学的決定論の世界観をもたらした。だが、ニュートン自身は、このような因果的決定論を想定していたわけではなかった。その思想には錬金術や聖書研究に窺われるように中世的世界観が色濃く残っていたのである。
ニュートン以前の正統な科学は、物事の発生する原因、目的を明らかにするという哲学上の目的論に力点が置かれていた。たとえば、ルネ・デカルトは惑星の運動や重力の原因を、空間に充満しているエーテルの圧力差や渦動によるものとする「渦動仮説」で説明を試みている。また、ヨハネス・ケプラーは地磁気が惑星の運動の原因であるとする重力理論を展開している。
これに対し、ニュートンは主著『プリンキピア』においてラテン語で“Hypotheses non fingo”(仮説により偽らず)と宣言する。あくまで観測できる物事の因果関係をのみを示すという哲学的態度を取った。よって万有引力の法則を提示するにおいて引力がなぜ発生するか、あるいは引力が何のために存在するのかという問題ではなく、引力がどのような法則によって機能するのかという説明のみに終始し、それをもたらす原因について論じる必要はないという新しい科学的方法論を提示している。神の行いについて、人間の持つ理性では理解不能であるという思想を背景としたものであったが、このような方法論は実証主義による近代科学の礎となるものであった。

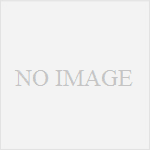

コメント