[adcode]
トーマス・カスーリス『神道』(2004)
2004年刊行。翻訳は2014年。
著者は、アメリカにおける日本思想、宗教哲学の第一人者。
神道という、日本人にとってさえ、極めて捉えどころない宗教を外国人の視点から、体系的にまとめている。
多くの日本人にとって、神道は、普段、「宗教(religion)」として意識されることは、まれだろう。しかし、意識的か無意識的かを問わず、神道的な感性に従って、日常生活を送っているのも事実だ。
著者は、日本人の神道に対するこうした曖昧な態度と非言語的な意識に寄り添う形で、神道の理解を始めている。このような著者の態度は、日本人の読者としても非常に納得の行くものだ。
神道は、「宗教(religion)」という欧米の概念で捉えようとすると、どうしてもその姿が歪んでしまう。大多数の日本人にとって、神道に対する意識は、宗教という概念には当てはまらない。だが、そうだからといって、無宗教的というわけでもない。
多くの日本人にとって、神聖と感じられる「場所」、あるいは、「もの」を前にすると自然と畏まる態度をとるのが普通の感覚だろう。本書の冒頭でも、そういった、鳥居の前では自然と頭を下げてしまう一般人男性の例が引かれている。
[adcode]
Spiritualityとしての神道
著者は、神道を西欧的な概念である「宗教(religion)」に対して、「霊性性(spirituality)」として捉えている。
神道は、神聖と感じられる場所やものを前にしたときの極めて原初的な畏れの感覚をその基底にしていて、それを儀式的に整えたものと考えるべきだろう。
神道では、神聖と感じられる場所やものに対して、注連縄などで標しを作り、神域と不浄の日常的領域を区分する。その神域を前にして、人々が、畏れの感情や畏まるような感覚を抱いたとしたら、それだけで神道としては成立するのである。
著者はこのような神道のあり方をtopology的と呼んでいる。日常のさまざまな場面で、holography的に立ち現れる神聖な領域があり、それが引き金となって、人々に原初的な宗教的感覚を呼び起こす。注連縄や鳥居は、そうした神道的霊性性へのholography的な入り口なのだ。
日常の中にさまざまに立ち現れるholography的な入り口が、神道的霊性(spirituality)へ至るきっかけになる。
神聖と感じられるものを前にして自然と畏まる態度をとることが、神道的霊性への入り口なのだ。神道が、自然や生活環境に対する人々の関わり方に深く基づくものであることが分かるだろう。山や巨木、奇岩など自然の存在や日常生活のなかの「聖と俗」「ハレとケ」の区分などが、人々の霊性性を呼び起こす。著者は、これを神道の実存的あり方と呼んでいる。
したがって、実存的な神道は、必然的に、日本の風土や自然観に深く根ざすことになる。
実存的神道と本質主義的神道
それに対して、日本が古代の氏族的な社会から、政治的な統合が進むにつれ、その象徴として、神道を体系的な宗教として整えようとする動きが、実存的な神道のあり方を基礎としながらも、現代に至るまで連綿と続いている。
このような象徴としての神道は、その社会のすべて人々にとって共通のものとして存在しなくてはならない。そのため土着的な限界を超えて普遍的な宗教としての形態を志向するようになる。古代では仏教の影響を受けながら、近代では西欧的な宗教の影響を受けながら、神道の体系化は、さまざまに試みられてきた。
これを著者は、実存的な神道に対して、本質主義的な神道と呼んでいる。そして、著者は、神道の発展の歴史を実存的な神道と本質主義的な浸透とのせめぎあいの歴史として描いている。
そして、著者の指摘で最も重要と思われるものは、神道が、その歴史の中で何度も体系化が試みられてきたにもかかわらず、それに成功した事例はほぼないという事実だ。
日本人の中にある実存的な霊性性の感覚は、本質主義的な試みを根本的に受け入れないものなのかもしれない。本質主義的な神道が、儀式や組織としての体系化、あるいは宗教として意識化に成功するのは、実存主義的な感性をうまくその中に取り込むことができた時のみだという。
逆に日本にさまざまに流入してきた儒教、仏教をはじめとした外来の宗教の中で、日本に根付くことができたものは、その実存的な感性を上手く掬い上げることのできたものだけである。あるいはそのように形を変えたものだけだ。
そのひとつの事例として、初期の仏教が、密教系として入ってきたことが重要だったという。真言宗と天台宗は、日本で最初に宗派として成立した仏教だが、どちらもその中心には密教の教義が大きな位置を占めており、原初的な宗教的感覚である霊性性(spirituality)に非常に親和性の強いものだった。
日本では仏教が流入してくると、従来の神道と互いが排斥するのではなく、神仏習合というsyncretismが進んだ。
これは、仏教という当時の最先端の知識を日本に流入することを容易にし、また一方の神道の側には、素朴な実存的な姿に、哲学的な正当化や内省的な深化、自己克己的な精神鍛錬の要素をもたらすことになった。
[adcode]
神道の歴史像
神道の歴史は、このように実存主義と本質主義の対立や融合という影響関係として見ていくことができる。
鎌倉仏教の隆盛、江戸時代の山鹿素行の神道の儒教的解釈、本居宣長による古代精神の復元の試み、平田篤胤による神道の国学化、大戦期の国家神道、こうのような神道の歴史を著者は、実存主義と本質主義のせめぎ合いとして描いていく。
本書では、実存と本質というひとつの対立軸を中心に、極めて鮮やかに、その歴史を紐解いていく。実存と本質という明確な軸を据えたことで、著者は、神道の発展を動態的な歴史像として描くことに成功しているといえるだろう。
そして、さらに著者の議論は、現代の神道のあり方にまで及ぶ。現代の神道の中心的問題となっている天皇制や靖国神社と政治のかかわり方の問題も実存と本質の違いという観点を据えると、問題の所在がまた違った形で見えてくる。
本書全体を通じて一貫して表れている著者の神道観というものは、神道は、本質主義的な試みからさまざまに影響を受けながらも、一貫して実存的なものとして生き延びてきたということだ。
それは、今後も変わることはないであろうし、神道はそのようなものとしてあるべきだと思う。
本書は、外国人の目から見た神道であるが、実存という内在的な理解に寄り添う形で描かれていて、日本人自身でも表現することがなかなか難しい神道的な感性を極めて明確に言語化している。さらに、神道を外部から眺め、客観的でかつ体系的な歴史像をも描いている。
海外に日本の神道を紹介するための本であるが、一日本人としても、普段意識しないが、行動原理の奥底で、それを規定している神道というものが、いったいどのようなものかを気付かせてくれる。日本人としての行動原理を知りたいとすれば、まず読んでおくべき本だと思う。
[adcode]

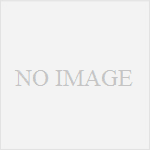
コメント