[adcode]
市川浩『<身>の構造』(1985)
初出は1985年。文庫化は1995年。
『精神としての身体』(1975) 発表以降の小論をまとめた論文集。発表された媒体は、新聞、週刊誌、学術誌と多岐に亘っていて、主題も多様である。「身体論を超えて」という副題が付いているが、補足的な論考が多く、身体論の発展的展開を論じるというところまでは達していない。
だが、個々の論考には、独特な着眼点もあり、独自性を感じさせる。
本書から興味深い論点を三つ取り上げてみたい。
[adcode]
身分け – 自己意識の形成
意識の原初的な反省が生じる場として身体を捉えたとき、それは主客同一、自他未分化の状態としてある。そうすると身体には、主客および自他を分離する契機が必要になる。それを著者は、「身分け」として概念化している。
ここでは、この身分けの働きを言語の習得過程から説明している。
言語を習得したころの子供にとって、言語は半ば行動であり、半ば観念である。しかし、学齢期になると行為としての言葉が内面化されて思考としての言語、内言になる。それとともに外に向って発せられる言葉も、行為としての身体性が稀薄になり、次第に概念的意味を伝えるだけの言語、外言になっていく。言葉は、物や人に働きかけて動かす呪術的生命力を次第に失い、その代りに論理性を表現するものに発展していく。内言と外言がこのように明確に区分されるようになるにつれて、他者と区分された自己の意識が明確になっていく。
「身」の用法
日本語の「み」という言葉は、その意味の広がりが非常に広い。内容を意味する「実」も同根と考えられる。この言葉の意味の広がりは、物体、生命、社会的立場、精神性にまで及ぶ。
「身構え」「身の丈」「身内、味方」「身をもって知る、示す」「身を立てる、身の程」「身に付く、身にしみる」
それに対し、英語のbodyは、物体としての意味が強い言葉であり、また日本語の「からだ」という語も籾殻の「殻」や枯れるの「かれ」と同義で生命のこもらない形骸としての身体や死体を意味する。
比較言語学的観点から、言葉の使い方の違いを詳細に見ていくと、身体の概念化が言語や文化によって異なることが分かる。
身体の拡大
物理的な実態としての身体は、皮膚によって限定されている。だが、皮膚の限界を超える「働きとしての身体」は、身体自身に対してメタ次元を形成する。用具、記号、制度といった仲立ちを介して拡大する身体は、それらを組み込んだ複合体を形成する。この仲立ちされた身体は、それによって外面化された自己の働きを対象化することによって、自己自身へと折り返す。
環境内存在としての身体は、環境を把握するだけではなく、環境内存在であること自体を把握する世界内存在となるのである。こうして外面的拡大は、内面的拡大を伴いつつ、より高次の意識形態を生む。
身体は、自己を中心として自己組織化し、世界と関わる。その中心化作用は、仮説的な中心を外部に投影することで脱中心化を行う。この過程は再帰的に自己組織化へと還元される。こうして自己は入子型にして、自己を拡大していく。このような柔軟な可変性にこそ、近代的自己とは対極的な自己の在り方が示されている。
果たして、この身体論は、近代的概念を超えて行くことができるのだろうか。その答えは本書からはまだ見えてこない。読者に投げかけられた課題だろう。

[adcode]

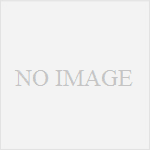

コメント