デカルト『省察』(1641)
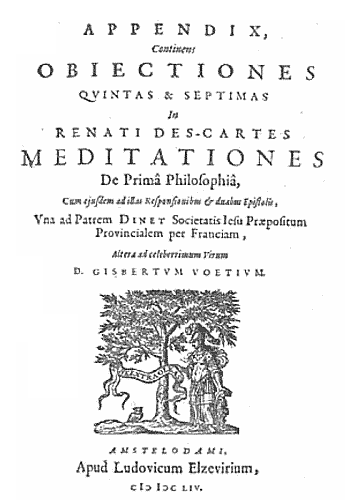
近代合理性と神への信仰
Je pense, donc je suis. ── Cogito ergo sum
我思う、ゆえに我あり
「我思う、ゆえに我あり」という言葉は、西洋哲学史の中でもとりわけ有名な命題であり、近代理性の出発点、そして近代哲学の幕開けを告げるものとして広く知られている。
この言葉を端緒とするデカルトの思想は、明晰さと確実性を重視する近代合理主義の象徴として理解されてきた。
しかし、デカルトの『省察』は、単に理性を称揚するための書ではない。『省察』は、一言で言えば、神の存在証明を試みた書物だ。神の存在を証明しようという極めて神学的な意図のもとで書かれている。ただし、デカルトの方法は、神学的な議論や盲目的な理解、あるいは教会の権威によるものではなく、理性による神の証明だった。
デカルトは、この議論が従来の権威、特に宗教的な権威に挑戦するものであることを十分理解していた。そのため、彼は、『省察』を出版する前に周到な準備をしている。自らの書物の意図とその思想へと至った思考の軌跡をあらかじめ前作の『方法序説』で説明し、不用意な宗教的反発を受けることを慎重に避けている。友人のメルセンヌを介し、当時の著名な学者たち──カテルス、アルノー、ホッブズ、ガッサンディ、ブルダン、さらにはメルセンヌ自身──に草稿を送付し、批判を募った。デカルトはそれらの反論に対する答弁も用意し、あらかじめ理論的論争としての構成を整えたうえで出版に臨んだ。
現在、広く出版されている翻訳は、1904年に公刊されたアダン・クヌリ版(AT版)を底本としており、初版本から本論のみを取り出した形になっている。
だが、初版本の『省察』は、こうした反論とそれへの答弁を含む構成となっており、はるかに広範で対話的な性格を有している。単なる哲学的独白ではなく、議論を前提とした理性の実践として構想された書物だったのである。
すべての批判に対して、それを理論的に論駁していくこと。理性的な思考を限界まで推し進めて、絶対的な正しさを証明しようとすること。このような思考態度が、盲目的な信仰や権威主義的な神学による理解を退けて、近代的な理性的思考へとつながっていった。
『省察』の前半で展開されるその徹底的な方法論的懐疑と数学的な演繹的還元主義は、まさに近代合理主義的な思考法の出発点となったものだ。そして、その方法論の確立に導いたものが「我思う故に我在り」という言葉で表される自己という認識主体の発見だった。
忘却された神学的意図
しかし、現代においては、デカルトの合理的な方法論のみが強調され、『省察』の神学的意図はしばしば見過ごされている。近代哲学の文脈において、「我思う、ゆえに我あり」は自己意識の発見としてのみ記憶されがちだが、デカルトにとってそれは出発点にすぎず、最終的な目標は神と真理の一致を理性によって確立することにあった。
デカルトの哲学は、盲目的な信仰や権威への依存ではなく、理性を極限まで用いて神を理解しようとする努力であった。そこにおいて、信仰と理性は対立するものではなく、同一の真理に向かう二つの道とされたのである。
神の存在証明とは何だったのか?
神の存在を証明しようとするデカルトの試みは、神という絶対者の存在を前提とせず思想を構築する現代にあっては、もはや過去の遺物のように見える。しかし、彼がなぜ神を必要としたのかという問いは、現在においてもなお意義を持ち続けている。
デカルトが神の存在を証明しようとした理由は、単なる信仰の擁護にとどまらない。彼の哲学および自然科学の体系を確実な基盤の上に築くこと、当時台頭しつつあった懐疑主義や無神論に理性的に対抗すること、そして自らの信仰を理性によって正当化することといった、複数の動機が密接に絡み合っていた。
1. 懐疑の徹底と知識の正当化
デカルトは、「感覚の錯誤」「誤った推論」「夢の可能性」といった段階的な方法的懐疑を通して、すべての知識を根底から疑った。その過程で唯一疑いえないものとして到達したのが、「我思う、ゆえに我あり(コギト)」である。
しかし、この命題が保証するのは、思考する主体としての自己の存在のみである。外部世界の存在や数学的真理の確実性までは担保しない。つまり、存在の証明と知識の証明はまったく異なる問題であった。
この限界を乗り越えるために、デカルトは誠実かつ全能な神の存在の証明を必要とした。神が誠実な存在であるならば、私たちが明晰かつ判明に認識するものが真であるという原理が保証される。逆に、神が誠実でないならば、最も基本的な数学的命題すら疑わしいものになってしまう。
これは、デカルトの懐疑がそれほど徹底したものであることを示している。それは、思考そのものの信頼性まで問い直す一切の妥協を許さない完全なものである。懐疑がそれだけ徹底したものだからこそ、そこから確実性を回復する鍵として神が位置づけられたのである。
2. 自己認識からの帰結としての神
デカルトにとって、「我思う」という自己認識は、同時に自身が不完全で有限な存在であることの自覚でもあった。彼は、この不完全な存在が、完全で無限な存在(神)という観念を抱くこと自体が、神の実在を示すと考えた。
無限の観念が、有限な人間の内部に自然に存在するという事実は、その観念が人間の外部にある神によって与えられた証であるとされる。神はデカルトの体系において、単なる外在的存在ではなく、形而上学の核心に位置する存在であり、そこから他のあらゆる認識が導かれる。
3. 懐疑主義・無神論への理性的対抗
デカルトが生きた17世紀は、宗教改革と三十年戦争を背景に、信仰の動揺とともに懐疑主義や無神論が台頭した時代である。彼は、ジュリオ・チェーザレ・ヴァニーニのような無神論者や自由思想家に対抗し、あらゆる人が納得するような「明晰で確実な論証」によって、神の存在および魂の不滅を証明する必要を感じていた。
さらに、デカルト自身が深い信仰心を持つ人物であり、その信仰は彼の自然観や科学的思考の土台を成していた。デカルトにとって、信仰と理性は対立するものではなく、相補的に真理を目指す二つの方法であった。
4. 普遍的な学問体系の基礎としての神
デカルトは、「普遍数学」と呼ばれる理想的な学問体系を構想し、あらゆる知識領域を明晰な原理と演繹によって統一しようとした。その体系において、形而上学は「学問の樹」の根幹とされ、その上に自然学(幹)、医学・機械学・道徳などの応用科学(枝葉)が位置づけられる。
この根幹を確かなものとするために、神の存在証明は不可欠だった。
神の不変性は、自然の摂理が時間や場所によって変わらないものであることを保証し、慣性の法則や運動量保存の法則といった自然法則の基礎となった。また、神の誠実さは、空間と延長を持つ物体の一貫性や実在性に直結する。
アリストテレス的スコラ哲学が感覚経験に依拠した不確実な知を前提としていたのに対し、デカルトは、数学的明晰性をモデルとした新たな方法論を提示した。その方法論が信頼できるものであるためには、その背後に確実で誠実な神の存在が不可欠だったのである。
神を証明する試み──存在論から認識論へ
では、デカルトはどのようにして神の存在を証明しようとしたのか。
その議論を理解するには、まずデカルト以前の中世スコラ哲学、とりわけ「普遍論争」と呼ばれる存在論的議論を確認しておく必要がある。
存在者とは何か? – スコラ哲学における普遍論争
中世哲学における中心的な関心の一つは、存在するものとは何か、すなわち「存在者」として本当に存在するものは何か、という問いだった。われわれが普段、経験によってその存在を確かめることのできる存在は、すべてそれ独自の個別の存在であり、後の近代哲学の語彙で言えば「実存的」な存在だ。決して「類」や「概念」として存在しているわけではない。
だが一方で、われわれが存在を理解する際は、すべての存在は「類」あるいは「概念」として把握されている。
たとえば、川の存在を考えてみよう。川には、常に水が流れ込んできていて、その水は決して同じものではない。絶え間なく新しい水が流れ込んでいるという意味で、川の存在は常に変化している。
しかし、「川」という言葉によって、われわれは川の存在を同一性のある一つの存在として理解する。ここで川は水の流れの「集合」として理解されている。
だとすれば、「川」という存在は、いったい何者なのか?ここでの「川」という概念は、流れる水の集合を意味するにすぎないのか、それともそれ自体が実在するのか?そう問いかけたのは、「万物は流転する」と語った古代ギリシアの哲学者ヘラクレイトスだ。実存と概念の対立は、古代ギリシア以来、哲学の中心的な主題であり続けてきた。
このような問いに対し、プラトンは「変化するもの(経験によって確かめられる実在)の背後にイデア(理念)がある」とし、そのイデアの存在のおかげで、われわれは、常に変化する存在を同一性のあるものとして把握することができるとした。そして、イデアこそ普遍的な存在として「存在的資格」を与えた。
以後、哲学はこのイデア的存在──形而上の存在者──をどう扱うべきかという議論に取り組み続けてきた。
この議論は中世において「普遍論争」として展開され、二つの立場が対立した。
- 実在論(Realism):類や概念といった普遍は、実在する存在者である。
- 唯名論(Nominalism):普遍はあくまで人間の便宜的な命名にすぎず、実在しない。
つまり、「類」や「概念」は単なる言葉か、それとも「モノ」と同じく実在するのか?この問いが、スコラ哲学の存在論的関心の核心だった。
認識論への転回:デカルトの革新
───この世界に「存在者」として存在しているものとは何か?
このように、この世に何が存在しているのか、を問う学問を存在論と呼ぶ。古代以来、哲学の議論の中心になってきたのはこの存在論である。
『省察』においてもデカルトの問題意識は、同じところにある。たとえば、彼は蜜蠟の事例を執拗に出してくる。蜜蠟は、色、形、硬さのすべてが容易に変化する。感覚によって捉えられる蜜蠟は、決して同一のものではない。川の水と同じように常に変化する存在だ。それにもかかわらず、蜜蠟という同一性を与えているものとは何なのだろうか。蜜蝋という明晰な認識は、何を根拠として成立するのだろうか。結局、ここで問われていることも、変化する実体の背後にある同一性とは一体何かということである。
「類」や「概念」があるからこそ、一つの存在を同一性のあるものとして認識することができる。では、この「類」や「概念」は、実際に我々が見て触れることのできる「モノ」とどう違うのか?同じように存在しているものとして扱っていいのか?
「類」や「概念」といった形而上の存在者は、現実に「モノ」として存在している形而下の存在者と同じ存在的資格を持つと言っていいのか?
デカルトは、この古代以来の存在論の議論にまったく新しい視点──認識論的観点──を持ち込んだ。
彼は、哲学の出発点を「何が存在するか」ではなく、「何が確実に認識できるか」に置いた。彼は、その方法論的な懐疑によって、人間にはまず何が認識できるかを最初の問題とした。つまり、存在論の前に認識論的な問題意識を持ち込み、その解決を試みた。
デカルトは、まず、経験的に知りうる知識は、見間違い、勘違いなど、誤認の可能性が常に排除しきれないため、理性的な認識の信頼には足らないとして除外した。そして、数学的な概念によって知りうるものこそが、正しい実在だとした。
このようにデカルトの認識論では、理性が実在証明の最も信頼に足る道具として据えられた。そして、イデアの世界こそが実在であると考えたプラトンと同じように、彼もまた形而上の「観念 (idea)」を「モノ」と同じ存在者として捉えている。その意味で、彼の思考は、プラトン的イデア論の近代的再構成とも言える。ここには、理性偏重の思考態度が窺える。
観念から神の存在へ:理性による証明
そして、このような認識論の枠組みにおいて、デカルトは神の存在証明を試みた。
彼の議論は次のように整理できる:
- 私たちは「不完全さ」を知っている。
- 「不完全さ」を知るには、「完全」という観念を前提として持っていなければならない。
- この「完全な観念」は、経験や自己から生まれることはできない。
- ゆえに、それに対応する「完全な存在者」が存在しなければならない。
- その「完全な存在者」こそが神である。
したがって、神は存在する。
この証明は、現代の読者にとっては言葉のすり替えのように映るかもしれない。しかし、中世的な存在論が袋小路に陥っていた状況の中で、「認識可能性」という新たな視点から神の実在を論証しようとしたデカルトの試みは、当時としては極めて画期的だった。
認識と存在のギャップ
しかし、デカルトの神の存在証明には、重大な哲学的問題がある。それは、「認識できること」と「存在すること」の混同である。
「完全という観念を持っている」ことと、「完全な存在者が実在する」ことの間には、本来、必然的な結びつきはない。「認識できる」ということと「存在している」ということの間には、絶対的な隔たりがある。デカルトの神の存在証明は、認識と存在との間の不明瞭さから来ている。現代の哲学では、そこに、存在論と認識論の安易な接合の誤りを指摘するだろう。この点は、後の哲学、とりわけカント以降の批判哲学によって厳しく問い直されることになる。
このようにデカルトによる神の存在証明は、中世の存在論と近代の認識論が、接合される形で展開する。その意味では、デカルトの思想には、中世と近代の接点、あるいは転換点を読み取ることができる。
デカルト的懐疑論から近代の認識論へ
デカルトの懐疑論は、何が存在するのかを問う前に、われわれには何が認識できるのかを問題とした。
デカルトの後、近代哲学は存在論から認識論へと移っていく。古代以来人間の認識能力は基本的に疑われることはなかった。「認識されるもの」と「存在するもの」との間に隔たりがなかったと言える。だが、デカルト以降、存在と認識は峻別され、人間の持つ認識能力の証明へと主題が変化する。
「存在者」の存在が問われなくなった現代では、デカルトの神の存在証明は、試みそのものが無意味なもののように思えてしまう。しかし、そこにある「存在への問い」「認識能力への問い」は、哲学において普遍的な主題だ。現代においても哲学が論じていることは、言葉が異なるだけで、結局は同じことの繰り返しに過ぎないとも言える。
デカルトにしろプラトンにしろ、理性的な思考を極限まで推し進めると、実在を超えた形而上的世界観を展開することになる。プラトンがイデアを実在と見なしたように、またデカルトが神の存在を証明しようとしたように、形而上的な世界観をあたかも現実の実在であるかのように扱う思考態度は、人間が陥りやすい誤りの一つだ。
このような理性偏重は、近代哲学にとっての躓きの石となる。しかし、これが問題となるのは、デカルトの時代よりももっと後、20世紀になってからの話だが。
古典というものは侮れない。一見、時代錯誤に見えるような問いの中にも、普遍的な問題が隠れている。逆に言えば、人間の考えることなんて、大して変化しないということなのかもしれない。
デカルトがなぜ神の存在証明を試みたのか、その証明は一体なんだったのか、それを現代において考えてみることも、決して無駄なことではないだろう。



コメント