M. J. アドラー『本を読む本』(1997)
原著:Mortimer J. Adler, How to Read a Book, 1940
批判的読書のために
原著は1940年の刊行。
戦前の古い著作で、単なる教養主義的な読書論を展開しただけの内容ではないかと思って長年読むのを敬遠していた本だった。だが、たまたま古書店で安く手に入ったのでふと読んでみたら、批判的読書(critical reading)の基本を説明した実践的な中身の本だった。(もっと早くに読んでおけばよかった。)
本書は、読書をいかに有効で、かつ意義あるものにするかを明確に示している。その焦点は、単なる知識の摂取や効率的な情報処理ではなく、読書を通じて自らの価値観を築き、見識を広げることに置かれている。現代の多くの読書術が速読や効率性を重視するのとは対照的に、本書は読書の最終目標を「批評精神の確立」に設定している。その核心となる方法論が、批判的読書(critical reading)である。
著者によれば、読書を正しく進めるには三つの段階がある。
第一は、読むべき本を選び出す点検読書。
第二は、著者の意図を正確に理解し、全体像を把握する分析読書。
第三は、複数の本から共通の主題を見つけ出し、深く探求していくシントピカル読書。
これら三段階を踏むことで、読書は段階的に高度化していくとされる。
とくに分析読書の最終段階では、「著者と対峙する」ことが重視される。これは、単なる感想文ではなく、著作の論点を整理し、どの点をどのように評価するのか、その理由は何かを明確にする作業である。さらに著者は、批評を行う際の知的礼節にも触れており、無理解や感情的反発ではなく、公正かつ根拠ある批評を求めている。
このように批判精神を養い、自らの価値観を形成していく過程こそが、読書を真に「自分のもの」にすることである──本書は、そのための指針を具体的に与えてくれる。
日本における国語教育の問題点
こうした読書術は、本来学校教育で教えられるべきものだと思う。日本の国語教育は、文学作品の鑑賞が中心で、感想文を書かせるだけのものになっている。文章の客観的な把握や評価が蔑ろにされて、論理よりも情操教育を重視している。
しかも感想文を書かせるのであれば、多様な考えや意見が出て当然だと思うのだが、道徳的、社会的に許容される意見のみ書かせるように教師が誘導していたりする。結果、型にはまった似たような回答ばかりになる。こんなのは、はっきり言って国語教育ではない。
話が横道にずれてしまったが。。。本書について。
「読解」というのは、著者の意図と論点を正しく把握するための技術であり、「批評」というのは、評価を与えることで自らの価値観を築いていく行為のことだ。こうした読解と批評のための技術があってはじめて批判的読書が可能になる。本書はその入門書として優れたものだと思う。
最後にちょっと翻訳について
本書の中で唐突に「シントピカル」という言葉が出てくる。ほとんど何の説明もないまま突如として現れる。文意がつかみにくいので、何かいい訳語はないかと考えてみた。「共主題」と訳して「共通の主題」という意味に捉えておけば分かりやすくなると思う。
M. J. アドラー『本を読む本』(1997)
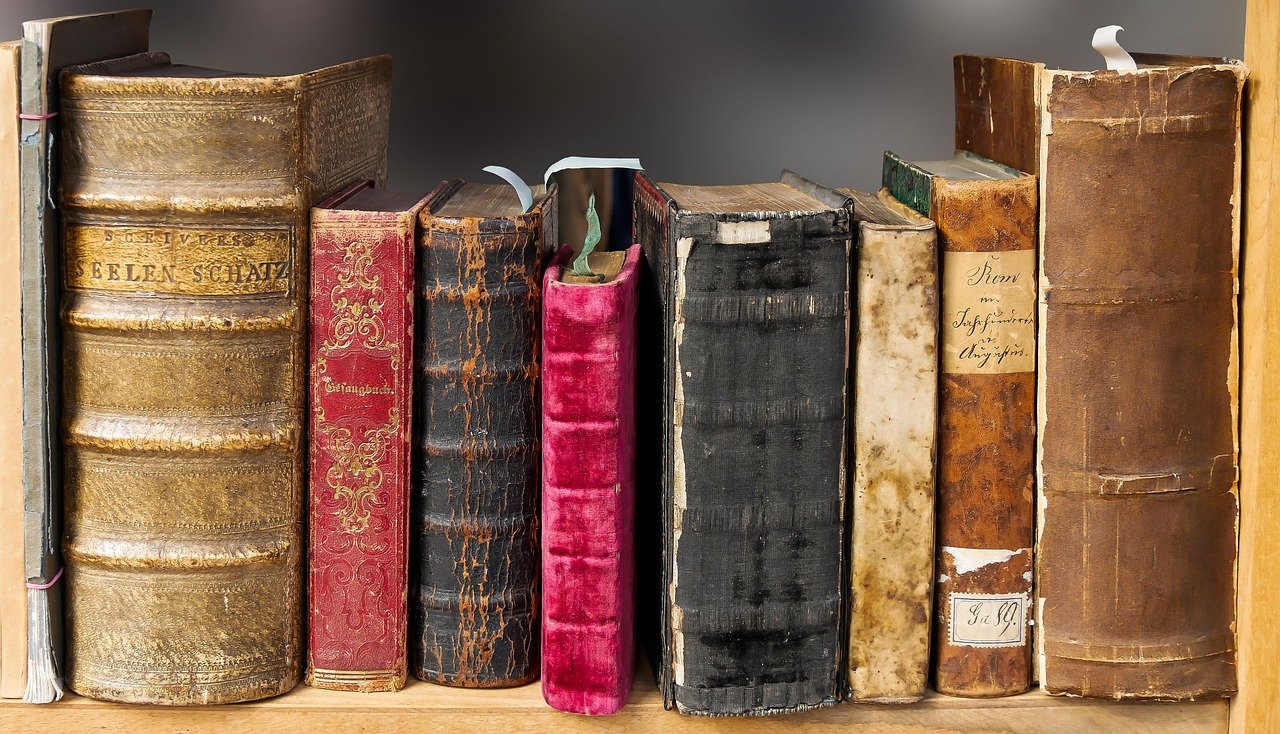
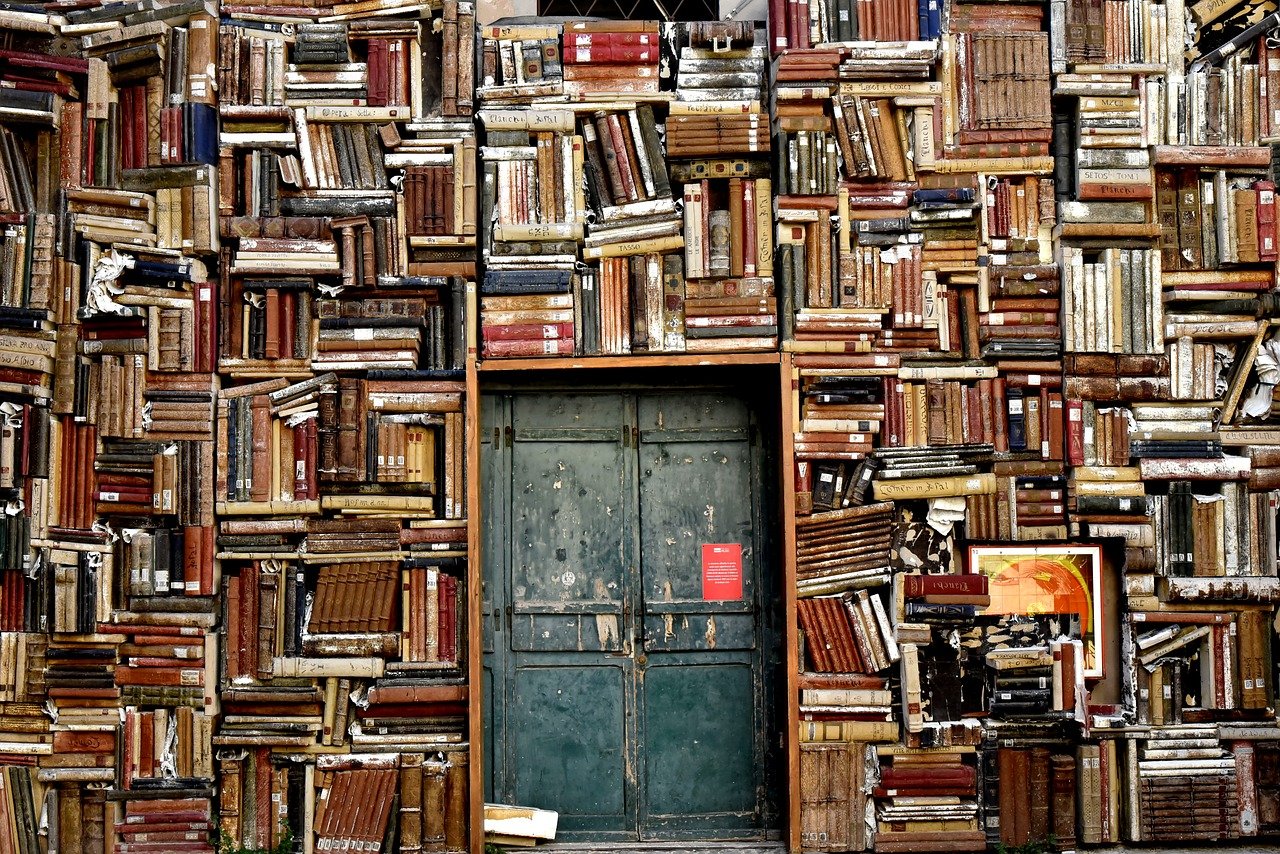

コメント