言外の伝達
かつての剣術、たとえば新陰流では、「一重身」で腰を落とす構えが一般的だった。これは「撞木の足」と呼ばれ、両足が一線上で交わる足の構え方である。しかし、竹刀を用いた稽古が主流となると、この構えは「居着く」つまり動きが鈍くなるとして使われなくなった。撞木の構えは、甲冑を着用する時代の名残であり、素早く太刀を扱うためのものではないと解釈されるようになったのである。
だが、これは誤解である。足が自由に動くようになると、体の捌きは大きく変化する。当時の武術家にとっては、それが常識であり、わざわざ言葉で説明する必要はなかった。しかし、後世の解釈によってその本質が失われていった。これは、言葉による伝達が主になることで、身体を通じた伝承が失われる典型的な例である。
武術における身体感覚は、言葉で伝えるには限界がある。『兵法家伝書』や無住心剣術の『前集』などでも、言葉にしにくい身体感覚をあえて記述しようとしている。昔の人々にとっては、読み手が理解できれば、それで十分伝わったのだろう。しかし現代においては、その意味を正確に汲み取ることは難しい。
言語外の伝達を確実に継承するためには、その文化や社会の枠組み自体を維持する必要がある。一方で、言葉に頼れば、そうした枠組みを超えていくことも可能になる。西欧では、「言葉にならないものは存在しない」という考えが強く、言語化できないものは他者に伝えられないため、存在しないものとみなされがちである。対照的に、日本文化は言葉にならない部分を重視してきた。ここに、西欧と日本の根本的な違いがある。
この「言外の伝達」を保持しようとしたのが、剣術の流派である。源平の時代から剣術の流儀は存在していたが、思想性を伴う形で体系化されるのは、上泉伊勢守以降のことである。それ以前にも中条流、念流、陰流などがあったが、詳しい内容はほとんどわかっていない。伊勢守以降は、流派の名称とともにその教えの内容も記録されている。
たとえば、無住心剣の針ヶ谷夕雲の後継者・小出切一雲は、剣術からすべての動きを削ぎ落とし、「心法の剣」として精神性を追求した。その一方で、松林左馬助無雲のように身体的動きを重視する流派も存在した。また、加藤田神陰流のように心法の剣の流れから出発し、再び動きのある剣法へと回帰した例もある。こうした流れからも、武術が結局は身体性から切り離せなかったことがうかがえる。
「心法の剣」が精神性を普遍的な教義として伝承しようとするのに対し、「技法の剣」は個人の才能に依存しがちであり、経験が体系化・一般化されずに失われやすい。伝統的な武術とは、こうした経験をなんとか積み重ねようとする試みであり、それが流派の存在意義でもあった。ただし、そうした経験の一般化が果たして可能なのか、それとも根本的に矛盾するのかという問いは残る。
身体的状況に依存した技術を超えようとすると、剣術は次第に観念的になり、やがては体制的な思想へと変質していく。柳生流の「心の剣」に影響を受けた関東の流派は、時代を動かすような力を失っていった。対照的に、薩摩の示現流のように、猿叫と呼ばれる奇声を発しながら身体的動きを重視した流派は、討幕の原動力となった。また、千葉周作の北辰一刀流は、合理主義的な剣術解釈を行い、また異なる方向性を示している。
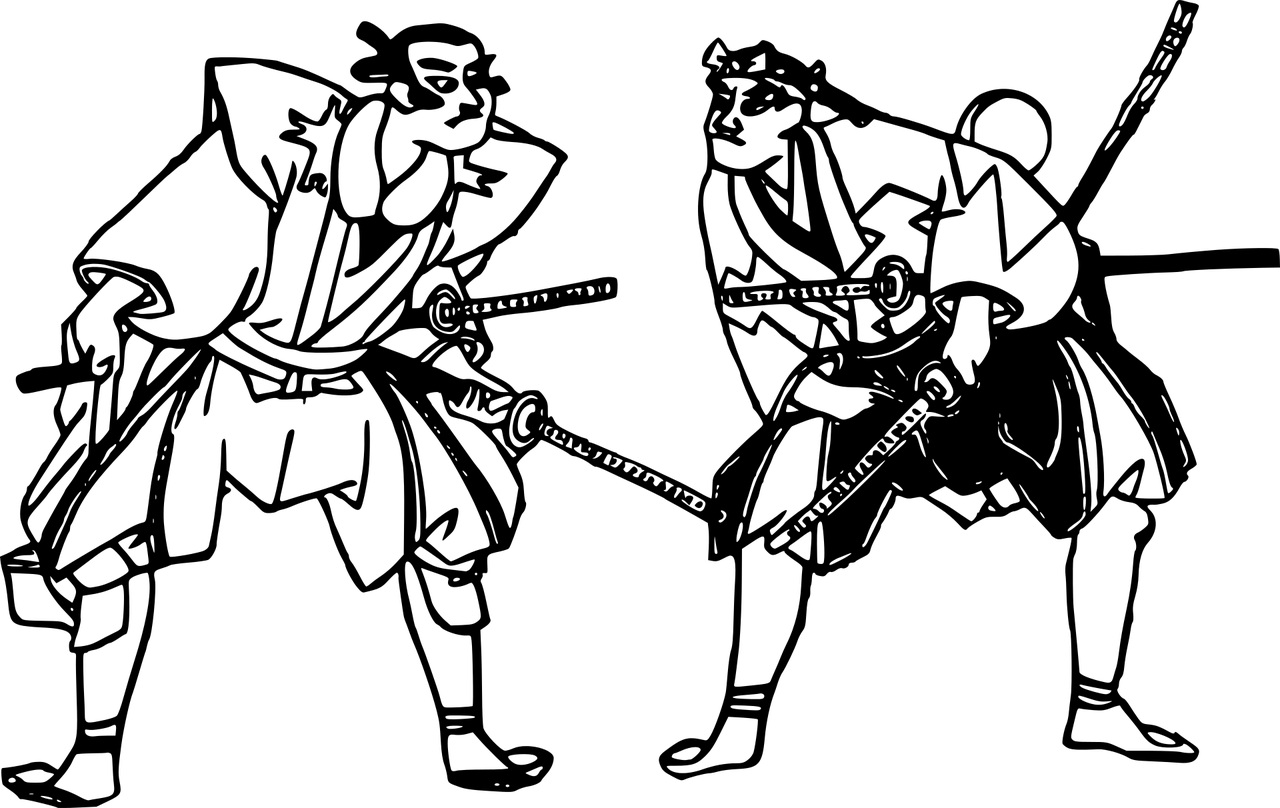


コメント