 晴筆雨読
晴筆雨読 自然の尊重と破壊:分裂する日本の自然観 – オギュスタン・ベルク『風土の日本』
オギュスタン・ベルク『風土の日本』(1986)分裂する日本の自然観晩春のある日曜日の午後、妻と私は戸山町のあたりをぶらついていた。まるで田園にでもいる思いだった。うねうねと曲がる小道、ときおり現われ出る緑、小さな丘、藪で覆われた窪地、切れ切...
 晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読  晴筆雨読
晴筆雨読 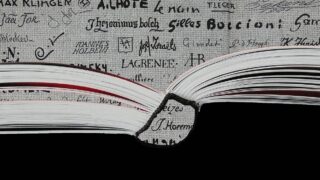 晴筆雨読
晴筆雨読 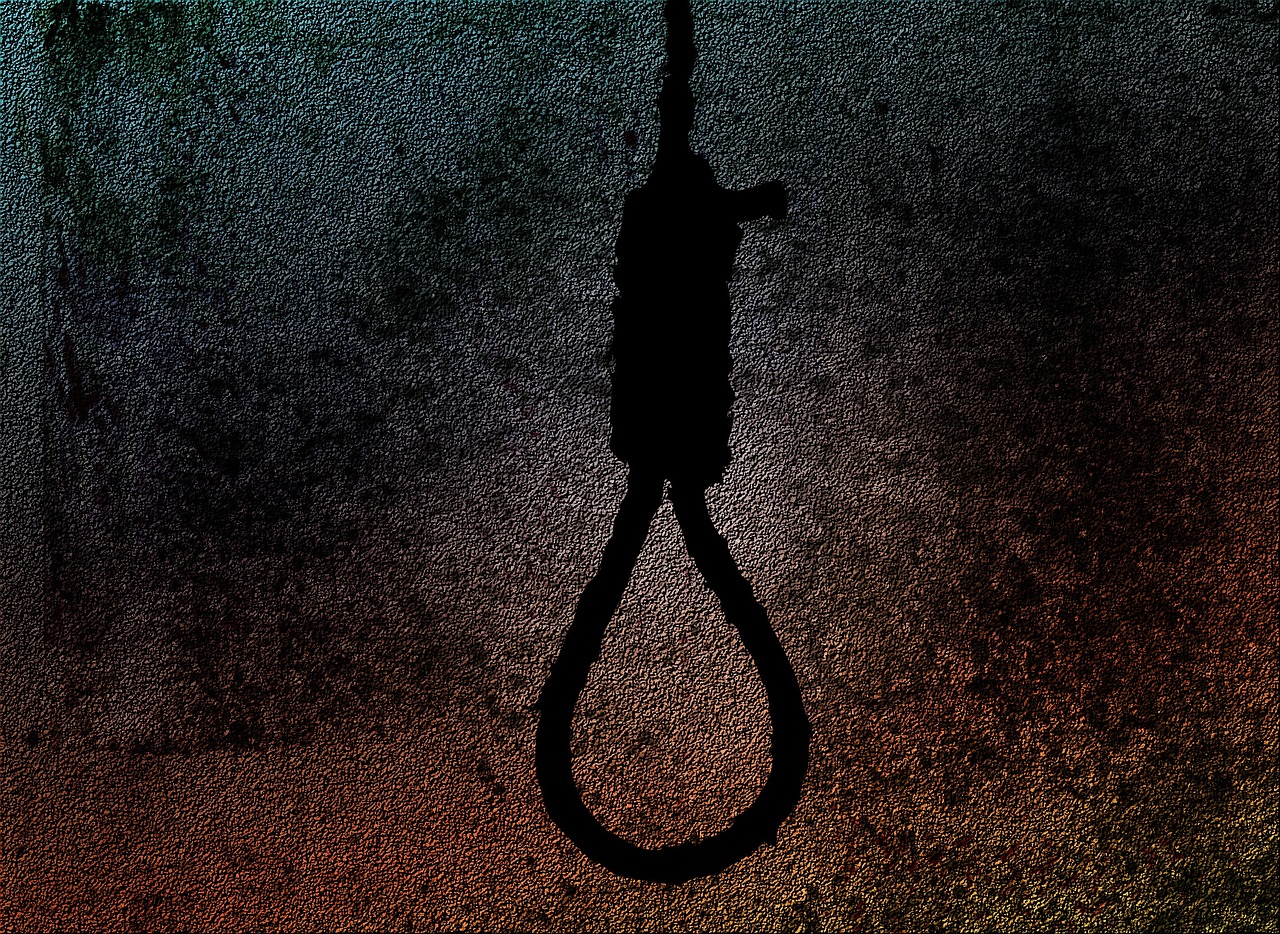 晴筆雨読
晴筆雨読