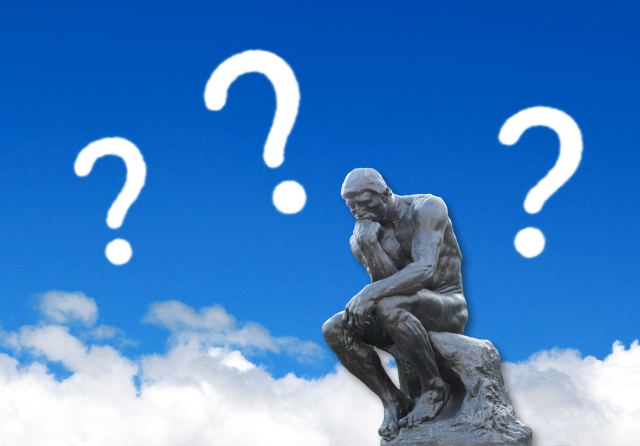 方々日誌
方々日誌 左右盲の克服方法(自己経験談)
左右盲とは? 右と左の区別が咄嗟にはつかないこと、またはそのような人の、自称。 色盲などといった既存の言葉から造られたただの俗語であり、このような病名や学術用語が実際にあるわけではない。 ごく一般には、「右」「みぎ」「左」「ひだり」と言葉ま...
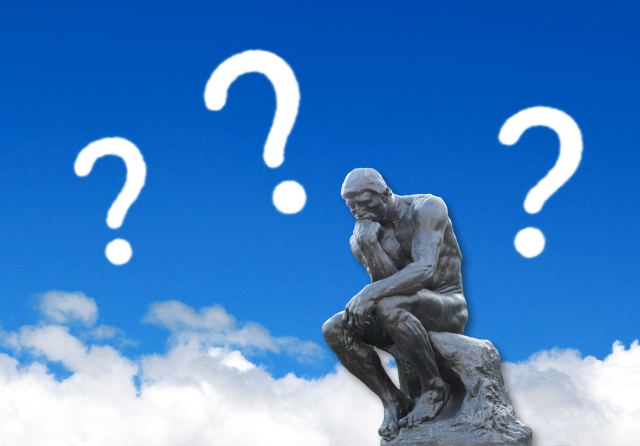 方々日誌
方々日誌  方々日誌
方々日誌  晴筆雨読
晴筆雨読  千言万句
千言万句 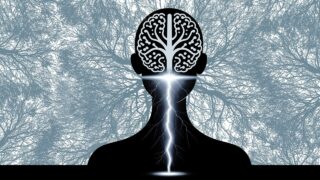 哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯  哲学談戯
哲学談戯