スティーブン・ピンカー『言語を生み出す本能』(1995)
Steven Pinker, The Language Instinct: How the Mind Creates Language, 1994
言語は本能か?
子供は、言葉に関して何も知らないまま生まれてくる。
生まれてきた子供は、適切な社会関係の中で言語に触れ、学習していかなければ、言葉を話せるようにはならない。
そして、どのような言語を習得するか、ということもその子供の育つ家庭や社会によって決まる。習得する言語は、育つ環境によってそれぞれ違う。
言語が本能によって決まるものだとしたら、すべての子供は、自然と言葉を獲得し、環境に依存せず同じ言語を話すだろう。だが、もちろん、実際はそのようにはならない。言語は後天的に獲得する社会的技術であり、その意味で、子供の言語能力は、社会的な産物だ。
世界には何千という言語が存在している。国民、民族、部族といった言語集団が、それぞれ歴史的に代々受け継いで、発展、変化させてきたものだ。言語はまさに文化的、歴史的な所産だ。
では、言語を話す能力はどうか?
適切な環境で育ち、脳や身体の言語機能に障害や疾患がなければ、誰であれ言葉を習得し、話せるようになる。この能力は、人類に普遍のものであり、本能といえる。
言語を話す能力は、普遍的なものだが、言語は社会的なもので文化的(恣意的)な存在である―――
このような考え方が、一般的なものだろう。言語学においても、20世紀の前半まではこのような考え方が一般的だった。だが、脳科学や認知科学が進展すると、脳がどのように機能して、言語を操作しているのか、少しずつではあるが解明されてきた。
言語は、世界中に多様な種類が存在しているが、どの言語も人間の脳が生み出すものであることに変わりはない。解剖学的な知見からいうと、人間の脳の構造は、全人類に普遍的なものである。だとするなら、脳の中に言語を生み出し、操作する能力、すなわち本能が存在しているのではないか?言語というのは普遍的な現象で、すべて同じ情報処理能力に基づいているのではないか?多様に見える言語はすべて普遍的な現象の異種(variant)に過ぎないのではないのか?このような疑問が、脳科学や認知科学の研究者の間から出てくるのはある意味当然のことだった。
著者のスティーブン・ピンカーは、認知科学の専門家だ。彼は、言語能力を人類に普遍的なものとして捉え、言語は自然発生的に発達すると考えている。
脳科学の進展以前に、このような考え方を最初に提唱したのは、チョムスキーである。言語に関する知識は、生得的なものであり、すべての言語を統括する普遍文法が存在すると唱えた。
チョムスキーの普遍文法は、生成文法理論と呼ばれたが、非常に理念的なもので実証できるのかどうか異論は絶えなかった。
本書は、チョムスキーの理論に拠りながら、言語が本能的な産物であることをさまざまな事象から検証していく。認知心理学の立場から、豊富な事例を紹介している。
ピジン言語とクレオール言語
言語が本能に依存して、自然発達するという考えの最も強力な証拠となるものが、クレオール言語の存在だ。
クレオール言語は、ピジン言語から発達する。ピジンとは、もともと共通言語のない人々の間で、意思の疎通を図るために、自然発生的に生まれた当座の言語のことをいう。最低限の意思の疎通を図る程度のもので、複雑な内容は表現できない。
だが、そのピジン言語を聞いて育った次の世代は、その言語を劇的に変化させる。文法や語彙を発展させ、複雑な内容の表現に耐えられるものにまで進化させるのだ。驚くべきことに、親の世代が表現できなかったことを表現し、限りなく自然言語へと近づける。このようにピジン言語から発達した自然言語をクレオール言語という。
クレオール世代は、親や社会環境からその言語を学んだのではなく、自然発生的に獲得したのだ。オセアニアや中南米など、かつての植民地時代に奴隷が大量に移住させられた地域では、原住民の言語と奴隷たちが話していた母語との間で、クレオール言語が発達し、それが現在の共通語や公用語になっている事例が多数ある。
クレオール言語の発達は、言語に関する知識が生得的なものであると想定しなければ、説明できな現象だ。
言語遺伝子は存在するか?
では、チョムスキーの言う通り、人間は生まれながらにして言語に関する知識を持っているのだとしたら、それは、遺伝として受け継がれなくてはいけない。果たして、人間に「言語遺伝子」なるものは、存在するのだろうか。
現在の認知心理学は、自然言語以前の心的言語が存在している、あるいは機能していることを示すさまざまな実験結果が発表されている。
人間の言語能力も含めた認知能力は、学習によって発達するが、そもそもその認知能力を担う心的機能部位(module)が脳内に存在しなければ、学習自体が成立しない。
ピンカーは、生得的な認知能力として、言語以外に、以下のようなものがあるのではないかと想定している。少し簡略化して、まとめてみよう。
1 力学的直観―対象物の動き、力、変形についての知識。
2 生物学的直観―動植物の仕組みを理解する能力。
3 数の認識。
4 広い領域についての心的地図。
5 住処の選択―安全で生産的な環境を見つけ出す能力。
6 危険予知―危険な場所、害をもたらす動植物の認識、発見。
7 食物―何が食用となるかを見分ける力。
8 汚染―衛生に対する直観。
9 満足感―何によって充足感を得られるかの認識。
10 心理学的直観―他人の欲求や感情を読み取り、行動を予測する知性。
11 心的住所録―個人の評価、社会関係の把握。
12 自像―他者との間で自分の価値を知る能力。
13 正義―権利、義務、功罪の感覚。
14 親族関係
15 配偶関係
このような種類に関する知識は、それを生得的に獲得するための心的機能部位(module)があらかじめ備わっているのではないか。社会的な学習は、その知識をより高度なものへと発達させる。だが、学習によって後天的に獲得しなくても、最低限、このような認知能力が生まれながらに備わっていなければ、人類はとうの昔に絶滅していたはずだ。
言語に関してもこのような心的機能部位(module)を持っていても不思議ではない。人間の社会形態に柔軟性があり、多様な言語が生じるのは、学習するための心的機能部位(module)が多数あり、独自の方法で学習の枠組みを形成するからではないか。
多様と思われる言語にも、共通項を見つけることは可能だ。
どの言語も単語を統語論によって句や分に配列する。単語は、それが担う機能によって品詞に分類できる。統語論的操作によって、無限の文章を生み出すことができる、等々。
このような言語の普遍性は、チョムスキーが指摘していることだが、チョムスキーの時代には、脳科学や認知心理学の知見が圧倒的に足りていなかった。
ピンカーのような次の世代は、人間に備わる「言語遺伝子」を発見することはできるのだろうか。
実は、本書では、この問いに対する答えは一切出ていない。認知心理学の知見から、言語が本能的に生じる事象を様々に示しているだけだ。
この本が書かれたのは、90年代半ばであり、脳科学も認知科学もまだ新しく始まったばかりの頃だ。当時は、科学の発達によって、チョムスキー理論が実証できるかもしれないという期待が沸き始めていた時代だ。研究はまだ緒に就いたばかりだったと言うべきだろう。
本書は、「生得的な言語知識」というチョムスキーの革命的な考え方を分かりやすい事例を多様に用いて、一般に説明したところに意義がある。
チョムスキーの発想は、理論的過ぎてなかなか理解できないが、これだけ豊富な事例を挙げて説明されると非常にわかりやすくなる。チョムスキー入門として読むのもよいと思う。
*補足
で。現在、言語遺伝子は、見つかったのか、というと、まだ見つかってはいない。この分野の研究は、相当、道が険しそうだ。

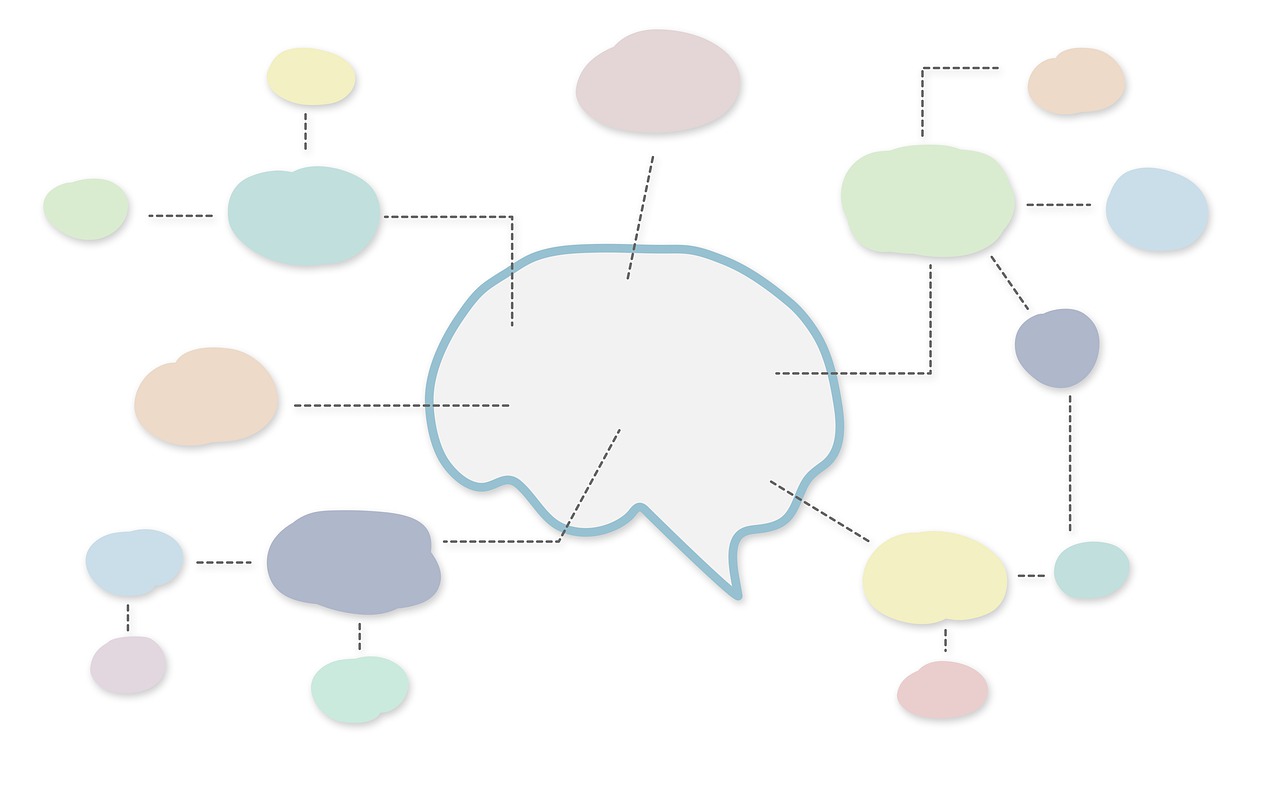

コメント