意識とは何か?──科学が挑んだ「不可視の現実」
心とは何か?そして、「意識」とはどこにあるのか?──
実証主義を基盤とする近代科学において、「意識」という現象は長らく、捉えがたい対象であり続けた。科学的手法の前提となる「客観的観察」の枠組みにおいて、意識は物質的な性質を持たず、客観的な「モノ」として定義することができない。つまり、意識は実体をもたない不可視の存在なのだ。
しかし一方で、「自分自身が意識している」という経験は、誰にとっても紛れもなく現実である。自我、感情、思考といった意識の働きは、私たちの主体的な経験の根底に常に存在しており、それを「ない」と言い切ることもできない。
このように、客観的には捉えにくく、しかし主観的には最も確実な現実であるという二面性を持つ「意識」は、科学にとってきわめて扱いにくい問題だった。では、この「捉え所のない意識」を、科学はどのように対象化しようと試みてきたのか?
本稿では、意識研究の始まりを19世紀心理学にまでさかのぼり、その後の展開を概観してみよう。
内観法──意識を観察する第一歩
19世紀中葉、ドイツ・ライプツィヒ。生理学者ヴィルヘルム・ヴントは、それまで主に哲学や形而上学の領域で論じられていた「心の問題」を、実験と観察に基づく経験科学としての心理学へと変革しようとした。
ヴントの構想は、心理学を自然科学の一部門として確立するものであり、彼の設立したライプツィヒ大学の実験心理学研究所は、世界初の心理学実験室として知られるようになる。
では、ヴントはどのようにして「意識」を科学的に扱おうとしたのだろうか?
彼が採用したのは、内観法(Introspektion)と呼ばれる方法である。これは、被験者が自らの意識の中で生じている感覚、感情、思考のプロセスを注意深く観察し、その内容を実験者の指示に従い、言語化・記録するというものである。
科学的手法としての限界
内観法は、自己観察によって心理や感情の働きを見る方法である。自分自身が体験した自己の心理の働きを自ら観察し、それを口述や筆記などによって報告する。
実験科学としての再現性を確保するために、統制された状況下で意識の観察が行われた。具体的には、例えば被験者に一定の条件下である思考課題が与えられ、その課題を考察する際の思考の流れを逐一報告させる、といった形式が取られた。
そして、意識の過程をいくつかの心理的要素――さまざまな感情や心理状態――に分け、それらが互いにどのように結びつき、どう関係するかを明らかにすることが目標とされた。
この手法によって、意識は初めて「実験科学」の対象となった。しかし、すぐにいくつかの根本的な問題点が浮かび上がる。
第一に、主観性の排除が困難であること。いかに条件を統一しようとも、被験者の報告は本人の主観に強く依存しており、その正確性や再現性には限界があった。観察対象と観察主体が同一であるため、観察結果の客観的検証が難しい。
第二に、観察される意識がごく一部にすぎないこと。内観法で記述されるのは、被験者が自覚している意識の範囲に限られる。無意識や、言語化できない心理過程は対象外となり、結果として「意識」の全体像を捉えるには不十分な手法とされた。
さらに、複数の研究者による内観の結果が一致しない、という問題もあった。意識の観察には高度な訓練と集中が必要であり、一般的な被験者に求めるには無理があった。
これらの批判によって、内観法は20世紀初頭には次第に支持を失い、代わって行動主義(Behaviorism)など、「観察可能な行動」だけに着目する心理学が台頭していく。
行動主義心理学の台頭──意識の「排除」という選択
内観法に基づく初期の実験心理学は、再現性や客観性に欠けることから、20世紀初頭には次第に限界が認識されるようになる。
このような状況の中で登場したのが、行動主義心理学(Behaviorism)である。アメリカの心理学者ジョン・B・ワトソンが提唱したこの新しい潮流は、心理学をより「客観的で科学的な学問」へと再構築することを目指した。
「行動」こそが科学の対象である
ワトソンの主張は明快だった。意識や感情のような内的状態は、客観的観察が不可能であり、科学の対象にはなり得ない。ゆえに、心理学はそのような曖昧な概念を捨て去り、観察可能な「行動」そのものを唯一の研究対象とすべきである、という立場である。
たとえば、「恐怖」や「欲望」といった内的状態を、あくまで身体的反応や行動として外から記述可能なもの(震え、逃避、発声など)に還元することで、それらを測定可能な変数として扱えるようにする。こうした観点は、心理学を自然科学と同様に「客観的・操作的・定量的」なものへと接近させた。
行動主義心理学では、刺激(stimulus)と反応(response)との因果関係に着目し、あらゆる心理現象をこの図式の中で記述することが重視された。こうして、心理学は観察者の立場からの実証的な研究が可能な学問として再編されていったのである。
意識の排除と心理学の自己矛盾
しかし、この科学化の試みによって、心理学は皮肉にも本来の対象である「心」や「意識」そのものを切り捨てる結果となった。
行動主義の立場からは、意識そのものの有無を問うことすら無意味であるとされ、研究対象から意図的に外された。これはある意味で、科学的厳密性を保つための「戦略的な無視」であったが、同時に、心理学が「人間の内面」という最も本質的な主題から遠ざかることを意味していた。
このような方法論的転回は、心理学にある種の倒錯性(paradox)をもたらした。すなわち、「心の科学」を名乗りながら、心を正面から扱うことを放棄するという逆説である。
精神分析との分岐——「内面」と「外面」の二極化
行動主義心理学がアメリカを中心に影響力を強める一方で、同じ20世紀初頭、ヨーロッパでは全く異なるアプローチが発展していた。それが、フロイトに代表される精神分析(psychoanalysis)である。
精神分析は、行動主義が退けた「無意識」や「抑圧」といった概念を中心に据え、人間の内的経験や動機、欲望に注目する。実験室ではなく臨床現場を主たる場とし、個別的な事例の解釈を通じて心の深層を探ろうとした。
こうして、20世紀前半の心理学は、行動の外的記述を重視する行動主義と、主観的内面の解釈を重視する精神分析とに大きく分岐することになる。両者は方法論も対象も大きく異なり、心理学という学問の統一性は失われていった。
意識の不在という問題
行動主義の隆盛によって、心理学における「意識」は長らく研究対象として排除され続けた。意識という現象が消えたわけではない。しかし、科学の枠組みに乗らないものは存在しないかのように扱われたのである。
だがその後、計算機科学の発展や脳科学の進歩、そして人工知能(AI)研究の展開によって、意識を再び科学的に扱うための新たな枠組みが生まれてくる。心理学の歴史は、そうした潮流のなかで「意識の復権」へと向かっていくことになる。
脳科学の登場──「意識」を可視化する技術の革新
20世紀中頃から、脳の働きを直接測定する科学技術の飛躍的な発展によって、心理学を取り巻く状況は大きく変化する。従来は主観的な報告や外部からの行動観察に頼らざるを得なかった「意識」の研究が、脳科学(neuroscience)の進展により、客観的なデータに基づいて検証可能な領域へと転換しはじめたのである。
脳波の発見──内面の可視化への第一歩
この流れの嚆矢となったのは、1929年にドイツの神経科医ハンス・ベルガーが世界で初めて、頭皮上の電極によって脳の電気的活動(脳波)を記録することに成功したことである。彼はこの電気的変動を「脳の精神活動の生理的な痕跡」とみなし、意識と脳の活動との関連を探ろうとした。
脳波(EEG: electroencephalogram)は、ニューロンの樹状突起で発生するシナプス後電位の集団的な変動を反映したものであり、生体が生きている限り休むことなく発生している。これらの電気信号は周波数によって分類され、たとえばα波(8〜13Hz)、β波(14〜30Hz)、θ波(4〜7Hz)、δ波(1〜3Hz)など、それぞれが異なる認知状態や生理的状態に対応している。
このように、意識状態の変化が脳波として客観的に観察可能になったことは、科学的な「意識研究」における大きな転換点となった。
認知革命と脳機能イメージング──再び意識が研究対象に
さらに20世紀後半、コンピュータの発展とともに情報処理の概念が心理学に導入され、「人間の心」を情報処理システムとしてモデル化する認知心理学(cognitive psychology)が台頭する。これにより、行動主義によって排除されていた「意識」への関心が再び復活することとなった。これがいわゆる「認知革命」である。
この再注目を可能にしたのが、脳の活動を非侵襲的かつ高精度に観察できる脳機能イメージング技術の登場である。たとえば:
- PET(ポジトロン断層法):脳内の血流や代謝の変化を画像として可視化する。
- fMRI(機能的磁気共鳴画像法):神経活動に伴う血流変化を測定し、特定の認知活動と脳部位との関連を明らかにする。
- MEG(脳磁場計測法):超電導量子干渉計(SQUID)を用いて、ニューロン活動による微弱な磁場を捉える。
これらの装置は、被験者に課題を与えている最中に脳の特定部位の活動をリアルタイムで記録することを可能にし、「今、何を意識しているか」という状態を脳の動きとして観測することを実現した。
意識は「現象」か「機能」か?
このように、脳科学と情報科学の発展により、意識は再び科学の対象となり、現代の心理学や神経科学においては、意識を次のように定義する見解が広まっている:
意識とは、脳による情報処理の特定の様式であり、生物が環境に適応するために進化させた高次機能である。
この立場では、意識はもはや「何かがそこにある」という存在論的な実体としてではなく、情報の選択、統合、指向性を担う脳機能のひとつとして理解されている。つまり、意識とは「私がいる」という感覚そのものではなく、「私が何をしているかを統御する機構」である。
冒頭の問いへのひとつの答え
ここであらためて、最初に立てた問いに立ち返ろう。
「意識とは何か?」
現代の脳科学や心理学において、この問いに対するひとつの答えは次のように言えるだろう:
意識とは、脳内の神経活動の結果として生じる現象であり、外界と自己をつなぎ、行動を調整する「機能」である。
つまり、意識は「存在」ではなく「機能(はたらき)」として捉えられるべきものであり、それゆえに、言語や内観だけでなく、生理学的データと計算モデルを用いて科学的に記述可能な対象となりつつあるのだ。
参考図書
苧阪直行『意識とは何か』(1996)
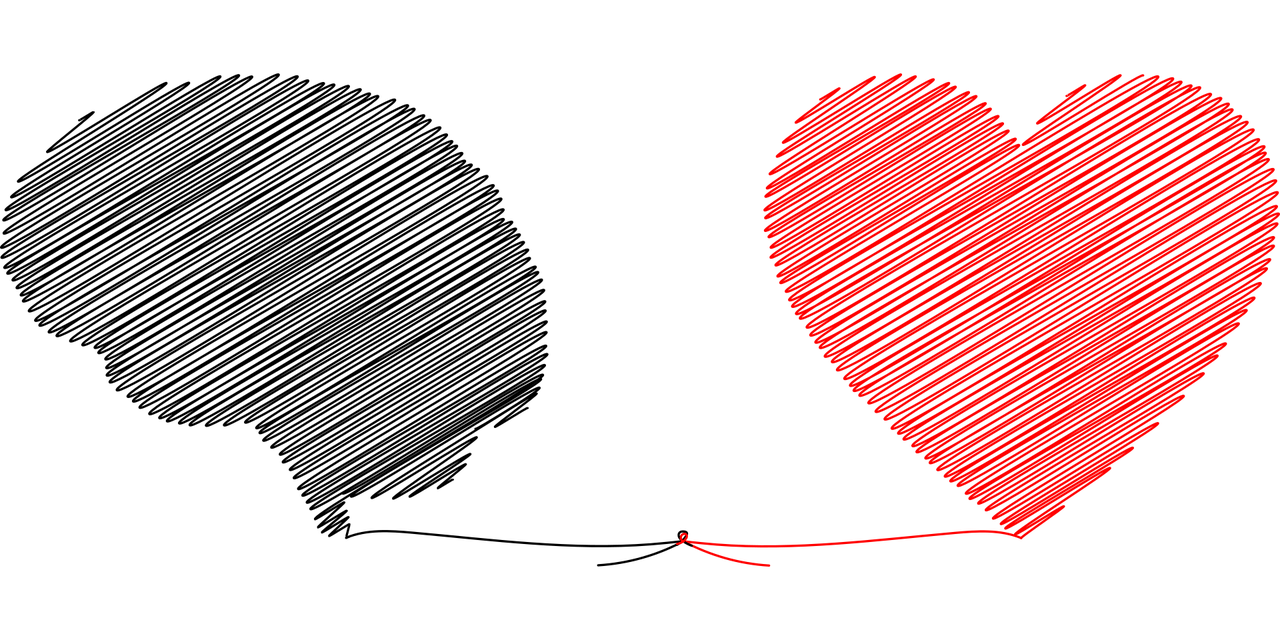


コメント