絵画:ジャック=ルイ・ダヴィッド『ソクラテスの死』(1787)
プラトン『パイドン』(385 BC?)
魂という不滅不変の存在──見ることのできないものを知る
『パイドン』は、ソクラテスが死刑執行の場で毒杯を仰ぐ最期の姿を描いた対話篇。哲学的にも文学的にも優れたプラトン中期の代表作である。
本作には「魂の不死について」という副題が付されており、死を目前にしたソクラテスが、魂が死後も存続するという思想を論じる構成となっている。議論の相手を務めるのは、ピタゴラス学派に属するシミアスとケベスであり、魂の不死をめぐる対話は、単なる形而上学的関心を超えて、プラトン哲学の中心的なテーマへと展開していく。
この中で提示されるのが、「イデア論」と「想起説」という、プラトン独自の思索の核心である。すなわち、現実の背後に存在する永遠不変の理念(イデア)の存在、そして人間の魂がそれを前世において認識していたという記憶(想起)の理論である。
プラトンは、ソクラテスの言葉を通じて、物質に対する理念、生に対する死、肉体に対する魂といった二項対立のうち、後者の方に本質的価値があると明確に述べている。これには、抽象的な数理的存在を神秘的・実在的なものとみなしていたピタゴラス学派の影響が色濃く見られる。
なお、ソクラテスの死は紀元前399年であり、プラトンが最初にシケリア(シチリア)を訪れたのはその11年後、紀元前388年のことである。南イタリア一帯は、当時ピタゴラス教団の活動拠点であり、プラトンがその地でピタゴラス思想に接したことで、イデア論や想起説の着想を深めたと考えられる。『パイドン』は、おそらくこの旅からの帰国直後に執筆されたものであり、以後のプラトンの対話篇には、彼自身の哲学が明確な形で表れるようになる。
想起説とイデア論
人間が多様な現象を抽象化し、概念として把握するという知的能力は、思考の根幹をなしている。プラトンの直感的な洞察は、それが人間の思考の本質であることを見抜いていたはずだ。その上で、彼が抱いた根本的な問いは、この本質的能力──すなわち「抽象的な概念を認識する力」を、私たちはなぜ生まれながらにして持っているのか、というものである。
この問いに対する彼の答えが、いわゆる想起説(アナムネーシス)である。すなわち、魂は生前の世界においてすでにあらゆる概念を「知っていた」のであり、われわれが学ぶという行為は、忘れていたそれらを思い出す(想起する)にすぎない、という立場である。この主張は現代人の直感からすれば受け入れがたいものであるかもしれない。だが重要なのは、プラトンが人間の知の原点を「抽象化と概念化の能力」として見抜き、それが経験に先立つ何らかの内的起源を持つと洞察した点である。
この考えは、イデア論とも密接に関係している。抽象的な概念は、言語でも数学的なものでも、現実の物質世界の中には見出すことはできない。たとえば、「小さい」「大きい」「等しさ」「善」「美」「数字(1、2、3など)」といったすべての概念は、具体的な事物を通じて認識されているにすぎず、形而下の世界においては常に不完全なものとしてしか現れない。理念(イデア)として表されるものだけが完全であり、現実で見るものはすべて普遍性を欠いた一時的で、相対的なものでしかない。
これらの概念の完全なかたちは、現実世界の背後にある理想的な次元──すなわちイデアの世界に存在するとプラトンは考えた。現実世界の事物は、イデアの不完全な模倣にすぎない。
では、現実には存在しないそれらの完全な概念を、われわれはなぜ知りうるのか。その答えが再び想起説に結びつく。人間の魂は、かつてイデアの世界にいて、それを直接認識していたというのである。したがって、魂の存在はこの世の生に限定されず、死後もまたその世界へ帰っていくということになる。こうしてプラトンは、魂の不滅という信念に哲学的根拠を与えた。
文学と哲学の融合
想起説やイデア論は、形而上の存在を実在のものとして捉える点で、現代の感覚からすれば違和感を覚える主張である。だが、人間の思考の根幹には、抽象化する能力や概念を把握する能力があるという点を直感的に見抜いていた点において、プラトンの洞察は極めて鋭い。
プラトンはあくまで古代的世界に生きている。抽象化された概念をイデアとして実在のものとして捉え、現実を超えた世界が存在すると考えた。そしてそれは、かつて魂がいた場所、そしてまた魂が帰っていく場所だった。
この魂の世界は、さまざまな神話を織り込みながら、プラトンによって美しく語られていく。ここに哲学と文学の稀有に優れた融合を見ることができる。
『パイドン』において、プラトンは魂の不滅を信じ、それを説いて聞かせることで、理不尽な裁判によって命を奪われたソクラテスの死を弔ったのだろう。
プラトン『パイドン』


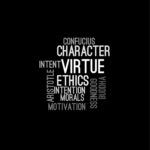
コメント