村上陽一郎『科学・哲学・信仰』(1977)
[adcode]
近代科学の源流
ギリシア文化とキリスト教的世界観―――
近代科学はこの二つの文化を背景として成立した。
近代文明は、通説的な理解では、中世的宗教観を脱し、古代ギリシア思想を復興させたことで始まったと言われるが、実際には、キリスト教の宗教的世界観が近代思想へ与えた影響は非常に大きい。近代科学は、キリスト教的一神教の世界観を実は前提として、その世俗化した形として成立している。
本書では、近代科学が古代哲学と宗教的信仰の融合の上で発展した歴史を丹念に跡付けている。
[adcode]
古代ギリシア思想
自然を自然のまま探究したことは、他の文明には見られないギリシア文化特有の特徴だと言ってよい。
もちろん、ギリシア以外の文化圏にも自然現象に対する知的興味や自然現象を説明するための体系を構築しようとする試みがなかったわけではない。多様で様々な自然現象に対して原理に遡って説明しようとする態度は、中国やインドの文化の中にも見られる。
たとえば、中国では、朱子学の中で易学が自然現象に対して精緻に理論化された体系を作り上げた。だが、その目的は、天子の正道を正しく把握することにあり、人間が関心の中心にあった。
自然の中から特に注目すべき現象を選び出し、ただその現象に対して、自然以外の説明要因を一切排除して、合理的な説明を与えようとしたのは、ギリシア人のみであったと言ってよい。
物体の「運動」という現象に着目し、落体の加速度現象や惑星の円運動などに凝縮、収斂される自然への関心、あるいは、原子論のように匂い、味、色などの物質の感覚に訴える属性を捨象して、力学的に物体を捉え、その生成変化を定性的、普遍的な原理へと還元しようとする発想などは、ギリシア人に特有の自然への接近様式だった。
そして、ギリシア人が自然の中で注目すべきものとして選び出した問題を引き継いだのが近代の西欧科学である。
キリスト教世界観
一神教的キリスト教の世界創世神話がもたらす「自然観」への大きな特徴の一つは、世界に秩序を与え、目的に向かって動かす神の意志が、自然と人間の上に普遍的な「法」として置かれているということである。「法」を意味する英語のlawもドイツ語のGesetzも語源的には「置かれる」を意味する。
このような神の意志が、日々の日常的な自然現象にも貫いたものであるのか、奇跡的な特殊な現象のみに働くのか、という点は必ずしもはっきりしていたわけではく、しばしば宗派間での論争となった。しかし、ヘブライズムとヘレニズムとの拮抗的変化の過程の中で、神の意志と理性による世界の支配こそ、自然界と人間の秩序の根幹をなすものだという考え方が次第に強固になっていく。13世紀の中世スコラ神学者たちの間では、すでにそのような解釈が共有されていたことからも明らかであろう。
そして、時代を経るにつれ、この法を認識する人間の能力が、神学的、哲学的問題の焦点となっていく。キリスト教にとって人間は神に似せられて作られた唯一の被造物である。そのため、人間は、神から与えられた理性を用いることによって神の意志を把握することができるという信念が生まれた。この信念は、法を認識する主体としての人間の存在を浮かび上がらせた。人間を認識主体として捉えるこの観念は、一方において人間と自然とを切り離し、観る人間と観られる自然という主観と客観の分離を促した。
こうしてキリスト教は、法則の存在に対する確信とそれを知りうる人間理性への信頼とを築き上げ、中世ラテン世界を通じて近代科学を導くための準備を成し遂げたのである。
[adcode]
擬人主義 – 人間中心思想の否定
自然という客体を理解しようとする時、それに対して、人間に対する理解の仕方とまったく同じ方法を用いて、同じの観念の下に理解しようとする態度が擬人主義の根底にある。すべては人間と同じという考え方が基本であり、いわば人間中心主義の思想である。このような擬人主義は世界のすべての文明に見られる。
古代ギリシアにおいても擬人主義の傾向は強く存在していた。すでに高度に体系化されていたアリストテレスの自然観の中でも、落体の加速現象の原因に、「帰心如矢」といった物が地に帰りたいというような擬人化による説明が行われていた。
アリストテレスより早い時期にデモクリトスが原子論を唱え、霊魂の働きさえ原子の運動に還元しようとしていた。この思想には、明確な非擬人主義的、機械論的態度が見られる。しかし、デモクリトスの自然観は、古代ギリシアにおいても中世ラテン世界においてもほとんど顧みられることはなかった。
中世の思想的系譜にも擬人主義的態度を否定しようとする契機は存在した。イタリアのパドヴァを中心に活動したラテン・アヴェロイストたちにはそれが認められる。イブン・ルシュド、ラテン名アヴェロエスは、アリストテレスの著作に詳細な注釈を加え、中世ヨーロッパにアリストテレスの自然観を復興させた。この自然観を継承したアヴェロエス派の思想は、その極端な決定論的世界観のために当時のキリスト教の正統教義からは、異端として排斥されたが、一部のプロテスタントに受け継がれ、彼らを通じて後の機械論的、運動力学的な決定論的世界観に影響を与えていった。後に近代科学の誕生に関係のある多くの科学者がパドヴァで学んだ。
決定論には、個々の物質現象は、同じ条件下にある完全に一義的な枠組みの中でしか生起しない、という考え方がある。アヴェロイズムでは、この現象の生起を司る力は神の意志であった。それが神の意志から、単なる自然法則へと変わった時、近代科学の基礎的枠組みが成立したのである。再現性を持つ一義的な法則が認められ、人間の心や意志のような気まぐれで不規則性なものを物の原因に当てはめることは端的に誤りとみなされるようになった。擬人主義の否定である。
近代ではこうした傾向は、人間自身にさえ適応される。人間の身体に関する機械論的な解釈が登場してくる。また、精神に関する現象を扱う場合でも、人間に内在する心や意志をそのまま研究の対象とすることは、科学的な研究とは見なされなくなった。心や意志を研究対象とした場合でも、現象として現れた観測数値や行動以外に科学の対象になり得ない。心理学や社会学においても、それが科学的とされる限りその理論的体系から心や意志といった擬人的概念は完全に追放されるようになった。
[adcode]
科学と信仰の関係
「もの」という存在に対する信頼が、科学の確実性を支える最初の根拠となった。13世紀イギリスの自然科学者ロジャー・ベーコンが実験観察を重視することで実証主義が始まる。
そして、17世紀、近代哲学の出発点となったデカルトは、「もの」の性質を延長(extentio)として捉えた。デカルトは空間内にある広がりを持つということを「もの」の基本的特性として考え、それを客観性の基準としたのである。複数の人間が共通して何かを認めるとき、最も確実なのは物の「手応え」を確かめることだ。逆にいえば、手応えを確かめることのできるものは、必ず複数の人間に共通に認められる可能性を持つことになる。
そこで近代の自然科学は、このような手応えのある物を追求する形で進展した。
だが、科学的知識において、経験がその確実性を保証するということには限界がある。一般に考えられている「もの」の確実性と科学的理論の確実性は、それぞれ別の次元のものなのだ。
直接的経験によって確かめることのできる事実というのは、実は非常に狭い範囲のものでしかない。ある科学的事実が正しいと言われるとき、たとえば原子が存在しているというとき、それは直接的経験によって確証されているのではなく、観察される諸現象が原子の存在を想定した方が整合的に説明されるという事実によって保証されるのである。ある事実が科学的に正当なものとして認められるには、その事実認定を保証する理論が、他の説明体系より簡潔かつ一貫性を持つこと、また他の理論との整合性があることが重要で、経験的実証は理論の妥当性を確かめるための傍証となるにすぎない。
つまり、科学的事実とは、我々が今構築している科学的知識のための諸理論の有機的な関連全体に依存している。そして、これは常に確固としたもにではなく、その有機的関連の全体が一度に変革してしまう可能性を持ったきわめて相対的な性質を帯びたものなのである。
その意味で、近代科学においても、経験や理論といった合理的判断の基準を超えた、直観的な決断といった信じるという行為がさまざまな場面で実行されているのである。近代における合理的な精神活動とは、実は信仰という営為を否定した結果登場してきたのではない。むしろ、それぞれの時代における「信仰」と呼んで差し支えないような理性や自然界の法に対する絶対的な確信がその根底には存在するのである。信仰とは、何らかの根拠づけによって持ったり持たなかったりするものではない。それはすべての事柄の根拠づけとなるもので、それ自体としては何らの根拠づけも必要としないような性質のものなのである。科学的確実性もその根源まで遡れば、そのような信仰と同じ性質に直面するのである。
村上氏が本書で明らかにしたように、近代科学もこのような信念に対する裏付けがあって発展してきた。近代科学の歴史には、実は信仰やその世俗化された形である信念がその根底に横たわっているのである。

[adcode]


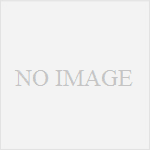
コメント