J. S. ミル『自由論』(1859)
矛盾する自由
自由という概念は、常に矛盾をはらんでいる。
自由は、近代社会を形づくる中核的な理念である。しかしそれは、社会の根幹に位置づけられる一方で、社会それ自体と絶えず緊張関係に置かれる概念でもある。とりわけ、社会的な意思決定の場である「政治」の領域において、その対立は鋭く表面化する。自由は、集団的意思決定の枠組みと根本的に衝突するのだ。
こうした「自由」と「政治」の緊張関係に対して、ひとつの理論的回答を試みたのが、ジョン・ステュアート・ミルの著作『自由論』(On Liberty)である。
この書は、自由主義の古典的名著として知られるが、現代においてもなお示唆に富む内容を備えている。1859年の出版当時、日本では安政の大獄が起こり、政治的弾圧が横行していた。すでに19世紀半ばにして、ここまで自由についての体系的な理論が構築されていたことは、驚くべきことである。
『自由論』は冒頭において、形而上学的な「意志の自由」ではなく、「市民の権利としての社会的自由」について論じると明言している。いたずらに抽象的な思弁ではなく、現実的かつ制度的な自由のあり方を主題とした書物である。そして実際に、本書で提示された自由の概念は、現代の民主制度の根幹を形づくることになる。
市民社会と自由の対立 ― 19世紀思想史の背景
ミルの思想的出発点には、当時の市民社会が抱えていた構造的な問題――すなわち、「多数派による専制」という新たな抑圧のかたち――がある。『自由論』は、こうした市民社会の限界と向き合い、それに対抗するための理論として書かれた。ミルにとっての自由論とは、台頭する市民社会への応答だったといえる。
では、ミルが直面した19世紀半ばのヨーロッパとは、どのような時代だったのだろうか。
産業革命をいち早く達成したイギリスでは、市民階級(中産階級)が台頭し、議会の寡頭的構造に対する不満を募らせていた。経済的自立を果たした市民たちは、政治的な参画を強く要求し始めていた。すでに1832年の第一回選挙法改正により、都市部の中産階級に選挙権が拡大され、議会制民主主義が制度として確立されつつあった。さらに、1848年にはマルクスとエンゲルスによる『共産党宣言』が発表され、労働者階級による政治運動も勢いを増していた。
こうして「民意」が政治に反映される制度が整う一方で、「民意とは何か」という根源的な問いが新たに浮かび上がった。およそ1世紀前に出版されたルソーの『社会契約論』(1762年)は、「一般意志」という概念を通じて民意を政治と結びつけようとしたが、フランス革命においてその理論がジャコバン派による恐怖政治の正当化に利用され、失敗した歴史がある。
議会制民主主義においても、多数決による決定が民意の表現とみなされるべきか否かは、依然として未解決の問題だった。もし単に「多数派=民意」と認めてしまえば、それは容易に「多数派による専制」や「少数派への抑圧」へと転化する危険をはらんでいた。
さらに、19世紀後半の社会主義思想の台頭により、「公共の利益」の名のもとにpaternalism(家父長主義)による個人への干渉が正当化される風潮が広まり、個人が「民意」に対して異議を唱えることはますます困難になっていった。つまり、民主主義が進展すればするほど、個人の自由が脅かされるという逆説的状況が生じたのである。
自由による民主主義の修正 ― ミルの自由主義
こうした民主主義の構造的欠陥を補い、それに対して修正を加えるために、ミルは自由主義(liberalism)を提唱した。彼にとってリベラリズムとは、単に民主主義の延長線上にある理念ではなく、民主主義を制限し調整するための原理だった。
この点において、『自由論』は民主制の理論的基盤を再考する書物である。自由とは、単に何者にも拘束されないという権利の主張だけではなく、むしろ「他者を抑圧することのない社会的な規律」として、政治的に保障されるべき価値である。そしてその自由こそが、民主主義の暴走を抑えるための「内在的な制御装置」として機能するのだ。
では、自由が民主主義を修正するとは、具体的にどういうことなのか。ここからは、ミルが主張した「自由」の意味そのものについて、さらに掘り下げて考えてみたい。
「Liberty」と「Freedom」——自由の二つの顔
ミルの『自由論』の原題は On Liberty である。On Freedom ではない。にもかかわらず、日本語では liberty も freedom も、どちらも単に「自由」と訳されるのが一般的である。これは翻訳上の便宜にすぎないかもしれないが、両者を区別なく扱ってしまうことには、大きな問題がある。というのも、この二語は、近代の政治思想において異なる文脈と含意を持つ、明確に区別されるべき概念だからである。
まず、liberty という語は、ラテン語の libertas に由来し、確かに語源的には「自由」であることを意味する。しかし、それは単なる「束縛されていない状態」ではなく、他者との共存を前提とした、社会的・政治的な文脈における自由を強く含意している。特にその形容詞形である liberal(リベラル)の意味を見ることで、liberty の本質がより明確になる。
たとえば、Oxford English Dictionary は liberal の定義を次のように示している:
Willing to respect or accept behaviour or opinions different from one’s own; open to new ideas:
(訳)自分とは異なる行動や意見を尊重し、あるいはそれを受け入れる意志をもつこと。新しい考えに開かれていること。
liberal – Oxford Dictionary
ここで明らかなように、liberal とは単に「自由な」というよりも、「異なる意見や価値観に対して寛容であること」が中核的な意味である。そのため日本語では「自由主義的」よりもむしろ「寛容な」と訳されることも少なくない。Liberty という名詞は、この形容詞が内包する寛容性、多様性の尊重、他者の権利への配慮といった価値を基盤としている。
次に、改めて liberty 自体の定義を見てみよう。Oxford Dictionary は次のように説明している:
The state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one’s behaviour or political views:
(訳)社会の中で、行動や政治的意見に対して権力によって課される抑圧的な制限から解放された状態。
liberty – Oxford Dictionary
ここで重要なのは、「within society(社会の中で)」という条件である。Liberty の本質は、他者と共存する社会の中で、抑圧を排除された状態を指す。つまり、個人の自由が無制限に保障されているわけではなく、むしろ他者の自由との調和を前提に成立する「社会的自由」である。
一方、freedom の定義は以下のとおりである:
The power or right to act, speak, or think as one wants:
(訳)自ら望むように行動し、発言し、考える力や権利。
freedom – Oxford Dictionary
Freedom はより主体的・個人的な自由を意味しており、他者との関係や社会的文脈を必ずしも前提としない。自律した個人が、自らの意思に基づいて行動する権利そのものが強調される語である。
自由主義の本質としての「Liberty」
このように見てくると、ミルが liberty を選び、freedom を用いなかった理由は明らかである。彼が論じた自由とは、「異なる意見や価値観を持つ他者との共存」を前提とした、社会的な自由=liberty だった。
ここに、ミルの自由主義(liberalism)が民主主義を修正する理念であるという主張の根拠がある。民主主義は、民意に基づく政治的意思決定を可能にするが、同時に「多数派による専制」を引き起こすリスクを常に抱えている。だからこそ、単なる手続き的な多数決ではなく、「少数意見を尊重し、多様性を認め、異なる立場に寛容である」という社会的価値が、制度の中に組み込まれなければならない。
つまり、ミルの自由主義が志向するのは、「freedom の最大化」ではなく、「liberty の保障」である。個人の自由が、他者の自由と衝突したとき、どうバランスを取るのか。その基準となるのが、liberty に内包された「社会の中での抑圧の排除」と「他者への寛容」なのである。
寛容と多様性のための自由
ミルは『自由論』において、自由(liberty)は個人のためというよりも、社会の発展のために不可欠であると主張している。なぜなら、社会が健全に成長していくためには、多様な価値観や生き方が保障され、そこに競争原理が働く必要があるからだ。自由とは、そうした多元的な社会の土壌を整えるための原理である。
この点において、ミルにとっての liberty は、単なる自己実現のための自由ではない。まず第一に、社会的多様性を保障するための制度的・倫理的な条件として意味づけられている。つまり、自由とは「自分の好きなことをする」ためのものではなく、「他者の違いを受け入れ、共に生きる社会を可能にする」ためのものである。
この観点から、ミルは明確に次のように述べる——「自由を否定する自由は認められない」。これは、liberty は freedom とは異なるという前提に立つ発言である。すなわち、他者の自由や多様性を脅かすような行為、言説、制度は、それが「自由」の名の下に主張されたとしても、liberty の立場からは認められないということだ。自由主義者(liberalist)は、社会的共存の基盤である寛容や多様性を破壊するような「自己中心的な自由」を許容しない。
したがって、ミルの『自由論』とは、本質的には「寛容」と「多様性」をめぐる政治哲学の書である。単なる個人の権利擁護を超えた、社会構成の原理としての自由を論じている点にこそ、その現代的意義がある。
社会から見た自由と個人から見た自由
ここで改めて、freedom と liberty の概念的な違いに立ち返っておこう。
Freedom は、「行為の主体者の側から見た自由」であり、自分の意思で考え、語り、行動する権利や能力を意味する。これに対して liberty は、「社会の側から見た自由」であり、他者の権利を尊重しながら社会の中で生きる自由を指す。他者との関係性のなかで成り立つ、協調と寛容を前提とした自由である。
政治思想的な文脈では、freedomは、自ら勝ち取った権利としての自由を主張する際に使われる言葉である一方、libertyという言葉には、異なる意見への尊重、多様性への志向、他者への寛容という社会的な条件としての自由が主張されている。
しかし、両者をともに自由と訳してしまえば、この違いは見えなくなる。
このような自由の二面性は、アイザイア・バーリンの有名な概念――「二つの自由(positive liberty / negative liberty)」の議論にも接続する。(バーリンの著書『自由論』も原題は Four Essays on Liberty である。)Freedom と Liberty の区別を理解していれば、自由が単一の概念ではなく、複数の含意を持つことは自然に受け入れられるはずである。
日本における自由概念の混乱
この点において、日本における「自由」概念の理解には、ある種の混乱があるように思われる。おそらくその一因は、freedom と liberty をどちらも「自由」として訳してしまっている語彙の曖昧さにあるのではないか。
たとえば、「自由とは何か」と問いかけたとき、多くの人が思い浮かべるのは「自分のしたいことをする権利(freedom)」であり、「他者の違いを認め、共に生きるための規律(liberty)」ではない。この語の曖昧さは、政治的・社会的な議論においても混乱を招いてきた。
自由は無制限に許容されるべきなのか? それとも一定の制限を受け入れることで、より豊かな共生が可能になるのか? ミルの議論は、この問いに対して非常に深い示唆を与えている。単なる功利主義の枠にとどまらず、自由と秩序、個性と共存のバランスを追求するその姿勢は、現代にもなお強い説得力を持つ。
現代への示唆としての『自由論』
たとえば、個性を尊重する教育のあり方、薬物や飲酒の規制、男女格差の是正、女性の政治参加といった多岐にわたる社会問題において、自由とは何か、どこまでが許容され、どこからが制限されるべきなのかは、常に問われている。こうした課題に対して、ミルの liberty 論は、現代社会の指針となりうる。
『自由論』は、民主主義の限界を見極めたうえで、それを支えるための思想としての自由を提示する書物である。だからこそ、この古典的著作は単なる歴史的遺物ではなく、「いまを生きるための思考の道具」として読むにふさわしい。まさに現代に生きる古典であり、自由と寛容を再考する上で欠かすことのできない一冊である。

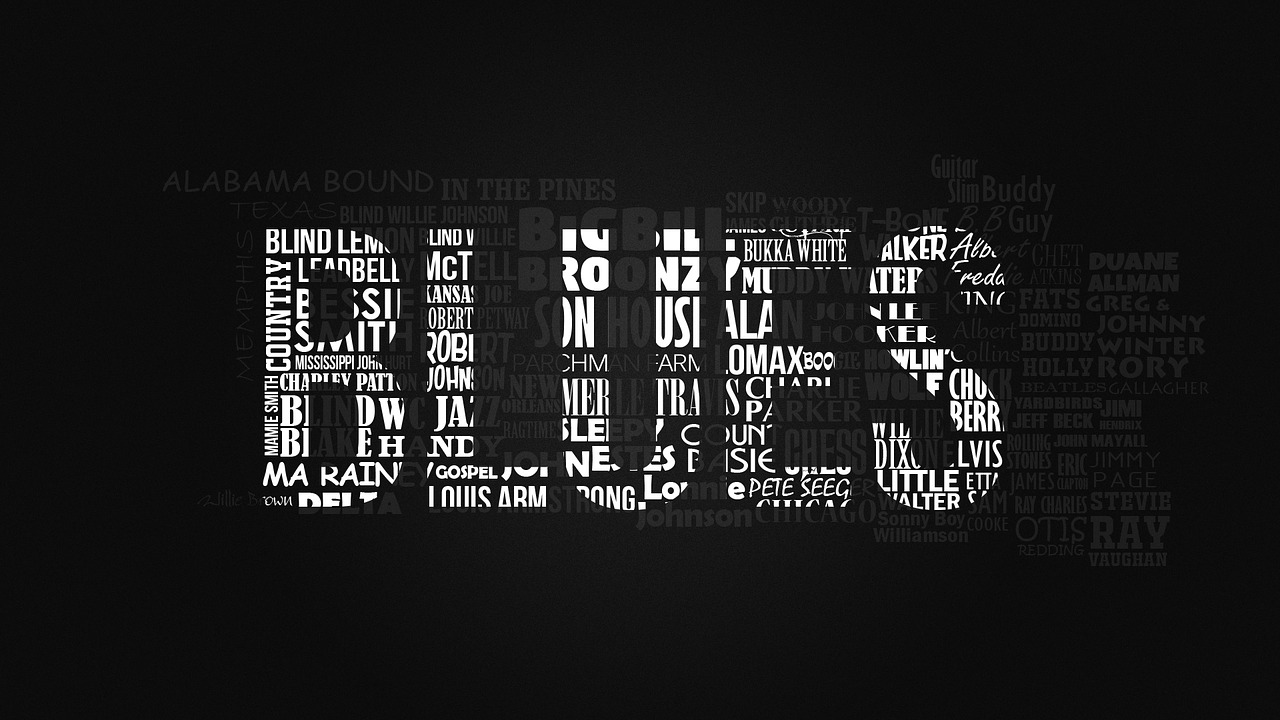

コメント